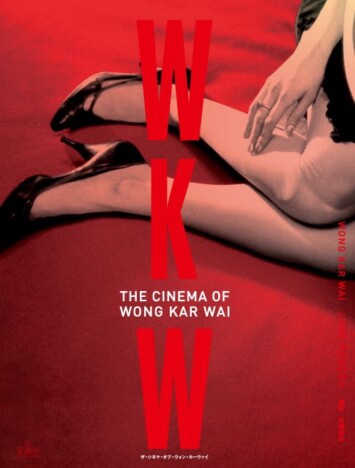菊地成孔 × 福尾匠「音楽と哲学の憂鬱と官能」対談 音楽と哲学それぞれの“引用”について

根拠のある引用、無根拠な引用

福尾:『非美学』のような本がどうやって作られるかというと、最終的には引用なんです。引用を並べて自分なりに意味付けすることをひたすら繰り返している。そこから何らかの自分なりのストーリーを作る。引用から始まるというのは、部分的だということです。全文を丸ごと引っこ抜いているわけじゃなくて、切り抜き切り抜き切り抜きでやっている。引用以外の注釈、言い換え、要約などは、引用が無根拠な切り抜きであることの言い訳をずっとしているようなものでもあります。引用を並べることにあたかも整合性があるかのように見せているわけです。でも原理的に問えば、そんな根拠なんて存在するわけない。部分的に引っこ抜いた瞬間に、ドゥルーズの全体性は既に壊してしまっている。でもその言い訳を分厚くしていって1冊の本にする。常識的に言うと、その引用が無根拠な切り抜きだということはあまり表沙汰にされません。その事実は単純に存在しないことになっている。
でも僕自身は、哲学が引用から始まること自体がすごく面白いと思います。ひとりで閉じこもって真理を洞察し、オリジナルテキストを自分で作る、という哲学者像を僕はぜんぜん信じていない。ドゥルーズ自身もベルクソン、ニーチェ、スピノザなど、いろんな人の引用、注釈、要約で、自分の哲学を形作ってきたわけです。僕自身も同じことをドゥルーズに対してやっている。オリジナルはどこにもないんだけど、でもそのつど何か面白いもの、新しいものが生まれるんです。

菊地:アカデミズムにおける引用は、それ相応の根拠があると看做されるわけですが、音楽が言葉を引用する時、むしろ論文の引用のような引用でない方が気が利いている。コラージュの命は、貼り合わせ目のギザギザさですから。それは音楽家の知恵というか、音楽家がテキスト全般にもつ、ある種の体質かもしれません。学術論文の本文と引用部分は、文字通り引用関係があるわけだから、完全に溶け込んでしまいます。
ですからあえて、引用対象を細かく明記するのでしょう。「しないと、溶け合ってしまう」わけなので。クラシックの長い曲は、敢えて全体を律するキーを1つだけ明記します。あの強制力のあり方と少し似ている気がします。非常に西欧的です。
僕が引用するのも、聴衆の人たちとのゲームみたいなもので。「何個気が付く?」と思っているんですよ(笑)。「構造と力」だったら全員が気がつきますが、デカい物件から歌詞のほんの一部まで、フラクタル状態でコラージュが行き渡っているので。
それを自分で忘れていることもあります。引用には注釈がなくてランダムに選ばれているから遊びです。小さい子のコラージュ遊び、あるいはアウトサイダーアートと変わらない。素材になっているのは映画やアカデミズムが多いんですけど。最近だとスーザン・ソンタグの書名をそのまま使ってます。
福尾:ソンタグを今使うというのはびっくりしました。誰も気にしてないですよ、ソンタグ(笑)。
菊地:市場価値があるのかどうか、自分でもよくわからない(笑)。ソンタグを使う人はおかしいですよね。なので〈『ラディカルな意志のスタイルズ』ってバンドの名前みたくない?〉という、一種の積極的な誤解や韜晦を使います。ライブの公演の名前を「反解釈0」「反解釈1」…とナンバリングするようにしました。これで誰がなんて言うのかしらね、という遊びです。
責任問題がないですから。僕は音楽家のやることは子供の遊びだと思っています。学者さんは大人のやることだと思っていて。音楽家が大人になっちゃったり、学者が子供になっちゃったりしたらそれは困るよなと。僕の方が年齢は遥かに上ですけども、福尾先生の方が大人で、僕が子供なんですよね。
福尾:構造的にはそうですよね。アカデミックなルールでは引用したら絶対どの本の何ページからのものか註に書かないといけないですし。
でもたとえば、『非美学——ジル・ドゥルーズの言葉と物』というタイトル自体が、実は菊地さんからの、註に書かれない引用という側面もあるんです。まずフーコーの本である『言葉と物』にドゥルーズの名前をくっつけちゃうというのが、菊地さんっぽいズラし(『南米のエリザベス・テイラー』みたいな)の影響がなければ思いつかなかったものだと思います。
それと、「非美学」というメインタイトルも、これはフランス語にすればanesthétique(アネステティック)で、「麻酔論」とも訳せます。実際書き始めた当初は「非美学=麻酔論」という名前で進めていました。スパンク・ハッピーにその名もズバリ「麻酔」という曲がありますが、僕の本では「麻酔」的なものを思考(言葉)と感覚(物)の分離として意味を拡張して使っていて、それは菊地さんの『服は何故音楽を必要とするか』や『アフロ・ディズニー』のテーマでもありました。菊地さんご自身が、言葉の技法である精神分析と体の技法である野口整体のキメラで治療なさったということもありますし、ある意味最初の「非美学者」だと思います(笑)。
ただ違うのは、菊地さんは一貫して麻酔的なものを官能的なものとして扱われていて、僕にはたぶんそういう側面がないということです。麻酔的=非感覚的なものが官能的=感覚的になるという逆説はとても面白いですね。
菊地:医療麻酔にしても、心理的な無痛感覚にしても、それは非常に危険な状態で、僕はラブソングばっかり書くので、多くは恋の喪失が出てきます。その時の、無痛感覚が発生し、局部麻酔で、視聴覚ははっきりしているんだけれども、声も出せないし、体も動かない。といった状態を、まあバタイユ的な意味で、官能的であるとしています。
anesthétique(アネステティック)=「麻酔論」というのはなかなか素晴らしいですね。音楽には、有名な「シンコペーション」という、リズムの活性化に関する用語がありますが、語源は言うまでもなく、具体的に「シンコペーションってなに?」と言われても、ちょっと答えに詰まるような、いわば放置されたまま曖昧に、しかし強く定着している言葉ですが、これはスペイン語圏の数詞「5=cinco=シンコ」から来ていると、一部ではいまだに思い込まれています。4拍子の枠組みに音を5個詰め込むと、弾んだ感じになるので。
ですがこれはむしろ逆で、シンコペーションというのは、ある程度規則的に、音を「抜く」ことであって、フランス語の「失神=Syncope=サンコペ」や、スペイン語の「sincope=シンコペ」が語源だとわかり、目から鱗が落ちたことがあります。連続体として出力、つまり密集的に音が連打されている状態から、失神して音が欠落する。それで連続体の持つ耐え難くも甘い、退屈さが活性化される訳です。これも麻酔的であると考えられるのではないでしょうか?