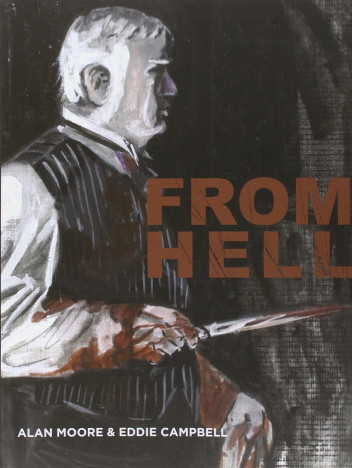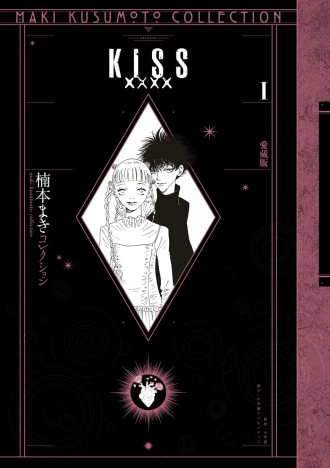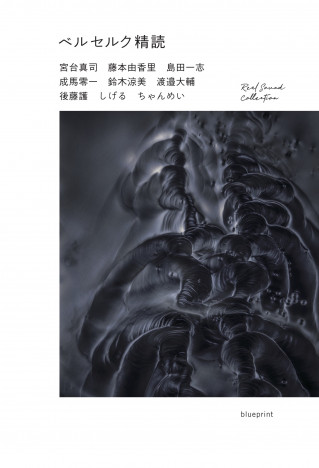後藤護 × 菊地成孔『黒人音楽史』対談 「抑圧が強くなった時代の次にはまた爆発が来る」

暗黒批評家・後藤護が著した書籍『黒人音楽史 奇想の宇宙』(中央公論新社)は、耳慣れない「アフロ・マニエリスム」なる概念を軸に、これまでにない切り口で黒人音楽史を捉え直した一冊だ。アフロ・マニエリスムとは、ドイツのジャーナリストで文筆家のグスタフ・ルネ・ホッケが1950年代に再評価した後期イタリア・ルネサンスの美術様式「マニエリスム」の理論を換骨奪胎し、ブラック・カルチャーに応用したもの。後藤護は、このアフロ・マニエリスムによって、奴隷制時代から南北戦争、公民権運動をへて真の解放をめざす現代までを総括しようと試みた。
ジャズ・ミュージシャンにして文筆家の菊地成孔は、本書『黒人音楽史』をどのように読んだのか。リアルサウンド ブックでは、ふたりの初対談をお届けする。(編集部)
歴史本を書く上で大事なのは、正史に見えること

菊地:いわゆる黒人音楽史についての本は20世紀にたくさん出ています。特にジャズ批評の多くは、歴史主義で書かれていて、ブルースからニューオーリンズ・ジャズに連結させてビーバップ以降まで書くという本が大量にある。啓蒙しようというピュアネスと、どうだ俺は物知りだろう、といういたたまれなさの融合ですが、結局、ジャズ史が、教科書の日本史みたいにセリーとして絶対に固定されている。という安心感を、本を書きながら上塗りしてるわけですよね。「歴史を書きたくなる」というのはウイルスでしょう。中村とうようさんのようにソウル史を書く人もいて、ブルース史を書く人もいる。ヒップホップに関しては、歴史書として書きやすいからか佃煮にして売るほど出ている。これらの本は大体、似たり寄ったりでありながら、ブラック・ミュージックという視点で統括される気配はなかった。でも、これだけ盤も書籍もインターネットもあるのだから、必ず優秀な方が出てきて、堂々と“黒人音楽史”と謳える本がやがて出るだろうという予断はあったんです。おそらくは最初にそれをやろうとした人の本が決定版になるに違いないと思っていて、後藤さんの『黒人音楽史』はまさにそうだと思います。これ、ペダントリーと奇説の系譜というのかな? 後藤さんご自身がコスプレ的に擬態されているわけですが、澁澤龍彦的な、特に日本の、としますが、幻想文学側の後継、と座りやすく読む人も多いと思うんですけど、音楽家、研究家としての僕からみる限り、実は調理され尽くした肉や装飾を楽しむデカダンに見えつつ、骨が存在すると思いますね。
後藤:本当ですか? 落涙失禁するほど嬉しいです。『黒人音楽史』と銘打っているもののまったく正当な通史になってないというので、ラッパーでトラックメイカーの荘子itさん(Dos Monos)から『クソ・黒人音楽史』って命名されたんですよ。ヒップホップ的な意味での「shit(クソヤバい)」を含む誉め言葉だと信じたい(笑)。僕も『黒人綺想音楽史』という仮題でハナから「イル」な感じを狙ったのは事実なので、荘子itさんの言いたいことも分かる。ですので、菊地さんがある種の正統として評価してくださってる感じに逆に驚きました。
菊地:まあ、誰もが我が国の、フランスかぶれ的な幻想文学の芳しき奴が、黒人音楽を素材とした奇書。という判断を(どのぐらい言語化できるかどうかは別として)すると思うんですけど、ブランショ、バタイユ、みたいにセリー組んでも、神経と脳的なトランスばっかで、、、、まあ幻想もペダンチックも、骨のなさが身上なんだから(笑)、それを黒人音楽という、大腿骨とかリブ(アドリブの語源はラテン語のad libtumで、クラシック音楽における「ここは自由に」という指示記号ですが、黒人ジャズミュージシャンは「add rib=この皿にスペアリブ一本乗せて」という言い方で、歌モノの間奏に即興ソロが入ることをスラング的に指していました)みたいな、骨としての素材に移した事が、結果として功を奏していますよね。下手に腰が引けた感じで「○○黒人音楽史」みたいなタイトルにしなかったのが、むしろ良かったと思います。おそらく、博覧強記ではあるものの、やはり結局ヒップホップ史が心身の教養のメインステージである荘子itくんは(彼は、DCPRGの「ロナルドレーガン」に於ける、痙攣的点描を、ディラと結び付けたりする才人です)、本書の「骨のある歌舞伎」はちょっと羨ましかったかもな。とも思います。僕が『東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録』の前書き冒頭に書いたように、そもそも人類は正史というものは編めないので、我々の書くジャズ史も偽史の一つでしかない。歴史本を書く上で大事なのは、正史に見えることでしかなく、そこには、ものの見方が一貫していることは不可欠で、この『黒人音楽史』はそれができている。歴史=偽史としての風格がありますね。
後藤:『東京大学のアルバート・アイラー』は偽史であることを強調していましたが、その後にアフロ・フューチャリズムのムーブメントは来ましたよね。リアルからフィクションへの移行を促した運動ですが、菊地さんはアフロ・フューチャリズムよりも先駆けて歴史が常にフェイクであることに意識的だった。僕が本書で掲げた「アフロ・マニエリスム」という概念も、乱暴に要約すると真と偽が同時にありながら進んでいくようなものです。この本はアナモルフォーズ(斜めから見ると別の絵が浮かび上がってくる歪曲遠近法)みたいなところがありますね。アナモルフォーズなんて喩えをしましたが、ビジュアルを戦略的に使った騙し絵的な本とも言えます。
菊地:マニエリスムのアイコンでもある、トロンプルイユ性があるから。という意味と別に、この本は音楽の本というよりも、むしろ西洋美術史の本だと思います。西洋美術史ほど、「白い」書籍はない。唯一出てくるのはジャン=ミシェル・バスキアくらいで、クラシックバレエの本だって、ヘヴィーメタルの本だってもうちょっと黒い。その「最も白い=特に、視覚的に」という選択は盲点というか、最後の手段とも言えますが、感服しました。僕と大谷能生君が『M/D』、『AA 五十年後のアルバート・アイラー』で論じた、アウトサイダー・アートと音楽の関係性についても展開的に扱っていて(僕らは、アイラーをダーガーに見立てただけだから)要するに黒人音楽史においては美術史のような図象的な見立てが、これだけ重要で、それは、牽強付会であろうと、西洋美術と対応している。ということを、ちゃんとやっている。
後藤:西洋美術史からアフロ・アメリカンが排除されているのは事実です。ハーヴァード大学出版から『The Image of the Black in Western Art(西洋美術における黒人像)』っていう伝説のシリーズが一応出てますが、あくまで黒人は被写体で、アーティストとしての黒人が出て来るのは全10巻のうしろの2巻くらいです(ちなみにサン・ラーもジャケに選んだボッスの『快楽の園』、そこに何人かいる黒人像だけ抽出して見開きでバーンっと見せつけるセンスの良い本です)。僕の本は美術史が入ったからかもしれませんが、菊地さんがどこかでおっしゃっていた「ダンシング・リスニング」と「シッティング・リスニング」という腑分けで言うと、かなりシッティングです。基本的にマニエリスムは、対象をオブジェクティブに見る行為なので、必然的に動きを標本のようにピン留めしちゃう。動的なものをあえて死滅させることのダンディズムというか、動きたいけど動かない、全身黒のモード服で不動のトランスギャルみたいな(笑)。リズムやグルーヴのようなイディオムだけでは語れない知性過剰な黒人ミュージシャンの系譜を見つけてしまったので、むしろ今までの黒人音楽史がステレオタイプに見えてしまう。いわゆるブラック・カルチャーの言説だけでは、カバラの暗号的な聖書解釈学・ネオプラトニズム・神智学を膨大に摂取したサン・ラーの大部分が説明できない。ヒップホップ・アーティストのラメルジーなんて「ゴシック・フューチャリズム」とか言っていますから、アフロ・フューチャリズムでさえ片手落ちの感がある。そういうアフロとユーロが時代も超えてぶっちがいになったキメラな想像力については、まだ全然書ける余地があると思いました。
菊地:「体が動いちゃってる」段階で、今までの黒人音楽研究書ですよね。それを止めたのは凄いし、どうやって止めたかも凄いですよね(笑)。大和田先生のように、かなりダンスを止めることに意識的な黒人音楽研究書でも、やっぱちょっと動いてるんで(笑)。
黒人もゴシックが好きだという視点があると、転倒が起こる

後藤:菊地さんにファッションについてお尋ねしたいことがあります。アメリカでは黒人と床屋についての研究書がいっぱい出ていて、Pファンクはもともとバーバーショップから始まっているんですよね。ジョージ・クリントンが経営していたバーバーショップに集まってきた奴らが、パーラメント/ファンカデリックの元になった。大和田俊之さんの『アメリカ音楽史』によると、バーバーショップ・ハーモニーこそが、実はブルーノートスケールの起源だという説もあるらしいです。黒人たちは髪質に特徴があるので、いかにスタイリングするかは重要な関心事で、この『You Next: Reflections in Black Barber Shops』という写真集を見ると、床屋の大きな鏡は「自分がアフロ・アメリカンであることの意味とは一体何なのか?」と内省する装置だったということが探求されてます。ロバート・グラスパーが最近リリースした『Black Radio III』というアルバムの2曲目に参加しているキラー・マイクというラッパーも床屋の経営者で、ジョージ・クリントンと床屋対談もしているんです。僕は黒人共同体と床屋の密接な関係性を知ったときに、今までの黒人音楽史は一体なんだったんだと思いました。アイスキューブ主演の『バーバーショップ』って映画まであるじゃねえかと(笑)。それで床屋から発展して黒人の髪の毛のことを調べていたら、洋書のタイトルに「Tangled」という言葉がたくさん出てきた。これは「絡まった」とか「こんがらがった」という意味なのですが、それは黒人の髪質そのものであると同時に、アフロ・アメリカンが突き当たるパラドックスや社会的軋轢のダブルミーニングがある。菊地さんは、彼らの髪型についてはどう捉えていましたか。
菊地:バーバーショップ着眼も、大和田先生の素晴らしい仕事の一つですが、オリジナルの発見ではない。ウェイン・ショーターは自伝で、「クラブの大きな鏡の前で手を洗ったらもうお終いで、1時間鏡を見ていたこともざらにあった」と書いています。なので僕も重要事項ではあるとは思っていたんですけれど、そこまで掘り下げて考えたことはなかったですね。僕が髪型のことで思い出したのは、有名なマルコム・Xの自伝です。彼はタングルドした髪の毛をストレートにしたくて、お金がないから自分でパーマ液を塗ろうとするんだけれど、酸がきつくて火傷してできなかったという話がありました。偉人伝のエピソードの一つということで済まされているけれど、実は非常に黒人文化的なエピソードです。トマス・ピンチョンの『競売ナンバー49の叫び』という小説では、黒人の女性がある教団に入るんですけれど、そうすると通りすがりの人間に髪型が変だと言われる。それが何度か繰り返されて、女性が自殺するというシーンがありました。黒髪黒目直毛前提の我々の感覚からするとちょっと理解できない、置いてきぼりにされてしまうシーンなんですけれど、重要なポイントとして刺さるんですよね。あとは帽子の文化も無関係ではない。サン・ラーもあるとき、覚醒してからはずっと奇妙な帽子を被っている。
後藤:確かにサン・ラーは頭にアンテナとか水晶とかヘンテコなものをずっと付けてるので、実際の髪型を思い浮かべることは熱心なファンでも困難かもしれない。黒人と帽子の文化というのは考えたこともなかったですね。
菊地:ヒップホップにおけるキャップカルチャーにも繋がる話です。スニーカーのことはめちゃくちゃ語られているけれど、黒人が帽子を被るということの意味は、白人が被る帽子とだいぶ意味合いが違うはずです。そう考えると、ジャミロクワイのジェイ・ケイとT-ペインは、帽子の被り方においてすごく重要なことをした人かもしれない(笑)。どっちもオートクチュール的ではなく、前者はロクワイ族の、後者はバイキングみたいな、要するにクレージートライバルなんですけど(笑)。
後藤:そうですね(笑)。帽子から派生するんですが、ヒップホップ・ファッションのブリンブリンに関する奇書が出てます。ジリアン・ヘルナンデスって女性が書いた『Aesthetics of Excess: The Art and Politics of Black and Latina Embodiment』って本で、ニッキー・ミナージュがロココ時代の宮廷人であるデュ・バリー夫人に扮した写真とかの転覆作用について一章を割いてます。アフロ・マニエリスムのみならず、アフロ・ロココもあるのかいと驚きました。黒人ファッションはファンクからバロック化して、「奴隷制時代の鎖をぜんぶゴールドにしてやったぜ!」という感じの過剰&誇張で突き進んでいくと思うんですけど、西洋美術史の流れとまったく同じでバロックが極まるとロココになるんですかと(笑)。
菊地:米国のどの都市からでもいいから、そのままパリに移動すると、パリという都市自体がロココではないかと思わされます。ニッキー・ミナージュがロココに目を付けるというセンスは、十重二十重に凄い。こういう風に曲線を出すのはコルセットの文化ですよね。お姫様が恐怖映画で気絶するのは気が弱いからではなく、コルセットがキツすぎて血の巡りが悪くなるからで、しかもお目当ての人の前で失神するように計算していたと。単なる美的な目的を超えている。
後藤:コルセットといえばゴス文化の必須アイテムですが、アフロ・アメリカンの女性にもかかわらず白人文化のゴシックやゴスが大好きになってしまって、『Darkly: Black History and America's Gothic Soul』って本を出したリーラ・テイラーという書き手もいます。この人はゴシック小説の『フランケンシュタイン』が刊行された1818年にアメリカ大統領が奴隷を何人買い上げたかとか、そういうことも全部調べて、つまりモンスターの側からゴシックを捉え直しているんです。本来的にゴシックは、黒人を「他者」にして怪物化する原理があるはずなんだけど、好きだからしょうがないという感じで黒人が逆にそういう文化を取り入れると、倒錯というか迷宮に入らざるを得ない。この本にしたって、いきなりバンドのバウハウスのTシャツ着てる黒人の写真とか出てきてもう意味が分からない(笑)。黒人の人がコープス・メイクしてメランコリーに陥ってる倒錯なんですが、奴隷制時代には黒人は感情のないモノとして扱われてたことを思うと、白人文化を奪取して貴族的なゴス・メランコリーを気取るのも反逆の一形態ではあるのですね。僕はマニエリスムとかゴシックという対象をオブジェクティブに見る極めて人工的な白人文化を、あえてブラック・カルチャーという躍動する生の哲学に投射したらどうなるのか、フラスコふりふりパラケルススのごとく実験しているんですよ。マッドサイエンスですね。
菊地:こういうやり方しか、黒人音楽史を統合する方法はもうないと思う。機材やリリックを研究して音楽史を編むというやり方は当然あるけれど、それでは島宇宙化してしまって、トータライズはできない。これはジャズ本がプチ歴史書になってしまうような、一種の善意的な硬化です。さっきも言ったように、美術史にはバスキアしか黒人が出てこなくて、音楽史の方は白人が黒人に憧れる話ばかりじゃないですか。黒人は差別の対象となりつつも、クールで真似をしたくなるもので、そうなると白人がブラック・カルチャーを搾取しておりまするぞという20世紀のクリシェになってしまう。でも、後藤さんの本などで展開されているように、転倒や倒錯を起こし、その状態を作らないと「美術的」に黒人音楽をパースペクティヴできない。ストリートとリアルだけで転がしてると、インドアの黒人はどうなるとか、アンリアルの導入を妨げかねない。これは「美術的」な発想でも、その行き詰まりでもないです。アニマルズ・アズ・ア・リーダーズのリーダーであり、バンド内唯一の黒人であるトーシン・アバシがどうして生まれてきたのか? これはもう、クラシック音楽の血もあって、もう、20世紀の黒人音楽把握が、聴覚的にも、視覚的にも限界にきている証しですよね。僕はエミネムやローリング・ストーンズがブラック・ミュージックを摂取したのは偉大だと思いますが、むしろシックがピエール・カルダンを着て汗をかかずに演奏したりしている。あれだって中南米はスーツカルチャーがあって、サルサの人とかスーツ着てタイドアップして、汗びしょびしょになっているわけで。要するに、ずっとジェームス・ブラウンが言っている、コールドスエットとか、汗のカルチャーが関わっているわけで、実は黒人が白人に憧れるカルチャーは、白人が黒人に憧れると同時にスタートしている。様々な研究が、ラップのリリックのコノテーションの果てにルーツとしてシェイクスピアを出したりしていますが、言葉よりリズムより、今、転倒させるのに一番有効なのは、黒人がヨーロッパの古典的な美術を搾取するというか、憧れていくことだと思います。そこにタトゥーが入ってくると、比較的簡単にその通路が描けてしまうわけだけれど、後藤さんの『黒人音楽史』はあえてタトゥー文化には触れずに、他の図象や言葉によって、西洋美術史と黒人カルチャーの結びつきを描いている。そこが達見だと思います。