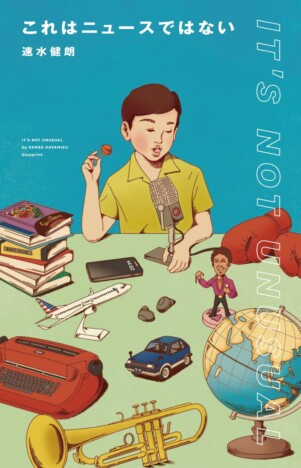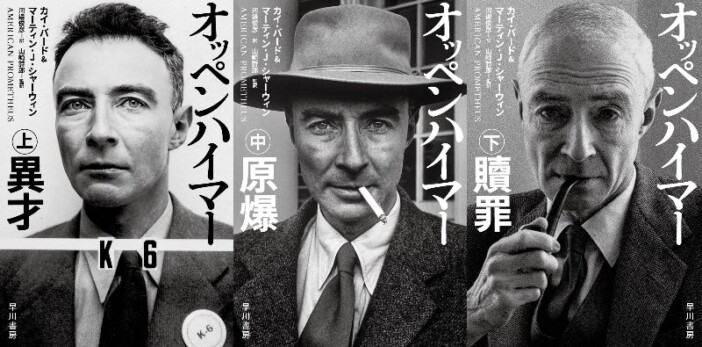映画史、「スタジオ・システム」の変遷ーーコンテンツ制作から劇場公開まで独占する仕組みをどう体系化?
■映画史本からみるスタジオ・システム

映画関連の書籍は山のようにある中で、映画史に関する本は実に少ない。筆者が入手できたのは映画史に関するものは北野圭介(著)『ハリウッド100年史講義』と四方田犬彦(著)『日本映画史110年』ぐらいである。これら二冊は、それぞれハリウッドと日本の映画史をまとめた良書といえよう。今回はそんな書籍から映画スタジオの盛衰を軸に歴史を振り返ってみたい。
■映画スタジオの盛衰
1930年代になると制作、配給、公開といったビジネスの形が整い、プロの映画監督、脚本家、俳優と言った中身に関わる人たちの地位が確立された。今では信じられない話だが、原初の映画にはまともな脚本など存在しなかったし、監督は=カメラを回して撮影する技術者だった。リュミエール兄弟は一応、「監督」としてクレジットされているが、彼らの映画は今日的な目でみると「映画」というより「記録映像」であり、そこに演出の余地を見出すことは難しい。
いわゆるスター俳優も当初は存在しなかった。俳優の名前や顔が映画ファンに定着していくのは、作品の安定した制作のために制作側と俳優が長期契約を交わすようになってからである。同じ顔と名前の俳優が何度か出ているうちに、映画ファンの間に自然と定着していったという形である。
映画監督も「撮影する技術者」と「演出家」が分業されるようになった。映画は横並び一直線構図のワンカット全編長回しから、複数のカットでシーンを構成し、複数のシーンをつないでシークエンスを作り、本編を構成する、現代では当たり前のやり方が定着していく。D. W. グリフィスは多くの手法を編み出した、この時代の先駆者のひとりである。こういった洗練前の映画がどのようなものか知りたい方はジョルジュ・メリエス監督の『月世界旅行』(1902)を見ていただくとわかりやすい。
同作は映画史上の重要作品で、「複数のシーンがある」「話の筋が存在する」といった点は特に画期的である、ただし、すべてのシーンが1カットの構成で、人物を横並びにした、まるで舞台をそのまま全体が見えるように撮影したようなやり方である。映画は舞台から多くの影響を受けているが、舞台との境目がまだ曖昧だったことを同作からはうかがい知れる。1930年代にもなると、長編、音声あり(トーキー)が当たり前になり、現代と比べて大きく変わらないものへと映画は洗練されていく。
現代と違うのは、スタジオ・システム(撮影所システム)と呼ばれる形が制作体制の主流だったことだ。この制作体制は一言でいうと、コンテンツの制作から劇場公開までを映画制作会社が独占する仕組みのことである。名前の通り、当時の大手制作会社は自社で映画スタジオ(撮影所)を所持していた。それに加えて、配給、上映まで管理下に置いていた。『ハリウッド100年史講義』の著者、北野氏の言葉を借りるなら「垂直統合」、わかりやすい表現である。
ことの起こりは1917年、フィラデルフィアの劇場チェーンが、全米の劇場系会社を多数束ねて、共同で制作会社を設立した。ファースト・ナショナル興業社連盟というこの会社が制作、配給、上映を丸ごと管理下に置くという経営方針を打ち出すと、これに続いてパラマウント、メトロ・ゴールウィン・メイヤー(MGM)が設立され、さらにユニバーサルとフォックスが設立された。その後の淘汰と再編を経て1930年代半ばには5つの制作会社(MGM、パラマウント、ワーナー・ブラザーズ、フォックス、RKO)が「ビッグ5」として映画業界の制作から公開までのほぼすべてを牛耳っていた。より具体的にはビッグ5のような少数の映画会社が寡占的に映画産業を独占していた形態を、スタジオ・システムと呼ぶ。スタジオはすべてを牛耳っていたため、コンテンツに関わる映画監督、脚本家、撮影、録音などの技術者、俳優も映画制作会社と契約していた。
これは現在の制作形態とは全く異なる。現代の映画監督は自分で制作会社を持っている場合もあるが、フリーランスの場合も多い。脚本家や、撮影や録音などの技術者もそうである。俳優は欧米の場合、エージェントと契約してエージェントが仕事を仲介する、フリーランス、自分で制作会社を持っているなどのパターンがある。日本の俳優は現代では芸能事務所に所属している場合が多い(制作者である筆者も何度もやり取りしたことがある)が、かつてはアメリカのように制作会社と契約することが多かった。(または劇団に所属する。古い日本映画を見ると出演者のクレジットに(俳優座)(文学座)などと名前の後ろについていることがあるが、もちろん所属劇団の名前である。これらの名門劇団は今も存在する)
デヴィッド・フィンチャー監督の映画『Mank/マンク』は脚本家のハーマン・J・マンキーウィッツを主人公に名作映画『市民ケーン』の裏側を描いた作品だ。映画でハーマン・マンキーウィッツはやたらと撮影所に出入りしているが、それはマンキーウィッツが映画制作会社と契約していたためである。今日的な観点では違和感のする描写だが、『Mank/マンク』の主な舞台は1930年である。当時からしたら自然なことだったのだ。
しかし、1948年にこのスタジオ・システムが、「独占禁止法に抵触する」との判決が下る。1950年代になると台頭してきたテレビとの競争で映画会社は俳優、スタッフを抱えておく体力を失い、スタジオ・システムは完全に崩壊する。スタジオ・システムで制作を行っていたのはアメリカだけでなく、日本を含むいくつかも国でもこの仕組みがかつては制作の主流だった。
偶然にも日本もアメリカと同じく大手映画会社5社(松竹、東宝、大映、日活、東映)が長きにわたって業界を寡占していた。わが国でも1958年をピークに映画の観客動員数が急降下し、経営体力が弱体化した映画制作会社が体制を維持できなくなってシステムが崩壊している。主な理由はテレビとの競争の激化である。
2020年代の今日において、古典的な映画制作会社と拮抗する存在になっているのがNetflixやAmazon Studiosなどの配信事業者である。映画監督のデヴィッド・フィンチャー、脚本家の坂元裕二などがNetflixと契約を結んでおり、大物映画監督のマーティン・スコセッシも直近の2作品は配信メイン作品(Netflix、Apple TV+)である。これらネット配信メイン作品は毎年のように米アカデミー賞をはじめとする世界各地の映画賞を賑わせており、一大勢力として完全に定着している。22世紀に新たな映画史を概観するとしたら、これら配信事業者の存在は避けて通れない存在になっていることだろう。