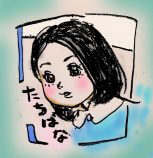立花もも 新刊レビュー 初の単著で話題沸騰、繊細な煌めきを放つ坂崎かおるをはじめ今読みたい4作品
雨宮福一『ツワブキの咲く場所』(幻冬舎)
14歳で統合失調症を発症し、今は家族と離れて暮らす涼のもとに、結婚するという妹から手紙が届いて、真実を教えてほしいと請われる。妹は、何も知らない。どこにでもいる老人にしか見えない新興宗教の教祖に、「この人があなたの運命の人です」と言われるがまま韓国で結婚した両親のことも。そのコミュニティに生まれ育った涼が、四歳のとき、教祖を「おじいちゃん」と呼んで手を振ったがために宙づりにされ、異端者だと罵られたことも。母親を呼ぶ間もなく、大人たちに殴る蹴るの暴行を加えられた涼に、母親が「私たちは皆、地獄に落ちるのよ」と言ったことも。
生まれ育ったそのコミュニティを、涼は「宗教というよりはカルト集団としか思えない奇怪で巨大なコミュニティ」と表現する。八歳になり、両親とともに日本で暮らすようになったあとも、その呪縛は解けなかった。韓国人というだけでいじめられ、近所からはカルトにハマった家の子だと陰口をたたかれる。母親は韓国に聖地巡礼を詩に行こうと誘った。そのすべてを妹は何も知らない。誠実に応えるため文字に起こすのは、涼にとって非常に苦しい行為だったけれど、主治医にすすめられるがまま参加したキリスト教会での集まりに参加し、聖書のページをめくるうちに、少しずつ変化が訪れる。
宗教に苦しめられた人が、宗教によって救われていく。その過程に、なんだかとても寄る辺のない気持ちにさせられる。人は、何か頼るものがないと生きていけない。たった一人で、自分だけの心で、立つことなんてできないのだということは、人とのつながりやぬくもりを感じさせる救いであると同時に、一歩間違えれば絶望の淵に立たされるのだろうと予感させるものでもある。それでも、著者自身が主人公と重なる経験をしてきたからこそ、その葛藤が、苦しみが、挿し込む光が、胸を打つ。あとがきに著者が添えた〈しかし神は、知恵ある者を恥じ入らせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じ入らせるために、この世の弱い者を選ばれました〉という聖書の言葉が、重い。
黒木あるじ『春のたましい 神祓いの記』(光文社)
感染症の流行によって地方の過疎化が進み、密を避けた催しが次々と中止されたことで、「祭り」も消えた。そうして、これまで鎮められていた八百万の神々が暴れ出し、日本各地でおそろしい異変が起こりはじめる。ゆえに出動を余儀なくされたのが、文化庁の秘密組織〈祭祀保安協会〉である。黒ずくめの烏みたいな九重十一(ここのえ・とい)と、やたらとなれなれしいホストのような八多岬(やた・みさき)。風変わりの男女が、地方に出没して怪異を処分し、「祭りを再開するように」と要請してまわる。コロナ禍の影響をそんな視点で描き出すのか! と驚かされること請け合いの、いっぷう変わったバディものである。
しかし怪異を起こすのは、人ならざる存在ばかりではない。蔑ろにされた怒りを発散する土着の神を退治するゴースト・バスター的な物語におさまらず、その土地で生きる人々の複雑にねじれた感情を重ね合わせて、事件を起こしていくのがこの作品のおもしろいところである。十一も岬も、怪異を解決するためには、トリガーとなった存在を見極めなくてはならない。謎をおうミステリーとしての楽しみも本作にはある。ぜひともシリーズ化してほしい!
祭りとはワクチンのようなもの、と十一が言う場面がある。集まるな、騒ぐな、遊ぶな、と禁止するのは簡単だけど、なぜその祭りが何百年も続いてきたのか、無駄と思われる手間をかけてでも存続させねばならないのか。理屈ではわりきれない、私たちが敬意を払わねばならないものについても、本作は描き出す。『ツワブキの咲く場所』とはまた違う、神の存在意義を問う物語である。