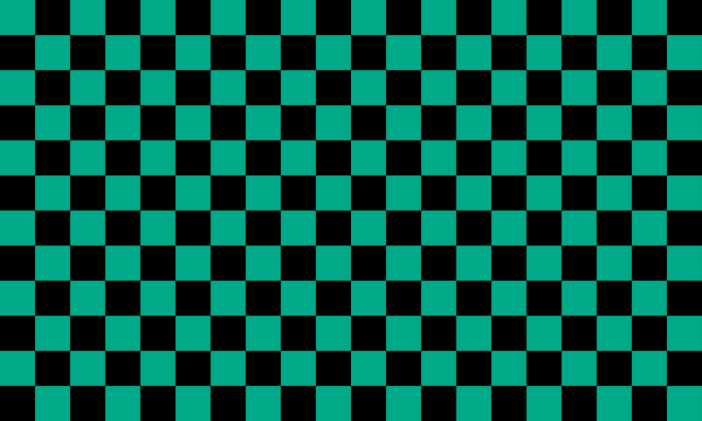大正時代を描く物語に新たな秀作誕生 浅草オペラの世界を伝える『浅草蜃気楼オペラ』演劇への熱き想い

大正時代を舞台にした小説が増加している。一番の原因は、大ヒット漫画『鬼滅の刃』及び、それを原作にしたアニメの影響だろう。作品の人気が高まると共に、舞台になっている大正時代も注目されるようになった。とはいえ過去にも大正ブームが起こったことがあるので、時代そのものが強い訴求力を持っているといっていい。
ではなぜ、大正時代が持て囃されるのか。幾つか理由があるが、ひとつ挙げるならば、都市部を中心にさまざまな文化が花開いたことだろう。その中に、本書の題材になっている“浅草オペラ”もあるのだ。作者の乾緑郎は、ミステリー・時代小説・SFなど、多彩なエンターテインメント作品を発表している小説家だが、実はもうひとつの顔がある。若い頃から演劇を志し、小劇場を中心に、俳優をしたり、演劇や舞台の脚本を手掛けていたのである。演劇方面の活動の一端は、劇作家協会新人戯曲賞最終候補作「ソリテュード」が収録されている戯曲集『ドライドックNo.8』で、知ることができる。本書は、そうした経歴を持つ作者の、演劇に対する想いが託された物語となっているのだ。
主人公の山岸妙子は、甲府の豪農の娘だ。高等女学校を卒業した彼女は、父親に反対されながらも上京。叔母の片桐芙美の家で世話になりながら、「帝国劇場洋劇部」に入団する。とはいえドン臭いところのある妙子は、端役が精々だ。指導の厳しいイタリア人演出家のヴィリトリオ・ローシーに、怒られることもある。その後、「帝国劇場洋劇部」が解散になると、ローシーが私財を投げ打って開設した「赤坂ローヤル館」に移る。といっても、やはりなかなか芽が出ない。
そんな妙子が、ローヤル館に父親と一緒に出ていた演歌師の須貝ハルと再会する。ハルのヴァイオリンの音に魅せられた妙子は、彼女と友達になった。そしてふたりは人生を交錯させながら、浅草オペラの世界で生きていくのだった。
本書は、プロローグとエピローグを除き、全三章で構成されている。第一章のラストで衝撃的な事件が起こり、妙子は甲府に帰ることになる。しかし父親と衝突し、再び上京。旧知の沢モリノに誘われ、石井獏たちが旗揚げした「東京歌劇座」に参加する。また、ハルと再会して一緒に暮らすようになる。このような展開だと、以後、妙子とハルが同じ歌劇団で奮闘するという流れになると思うが、ふたりは別々に活動。この展開がクライマックスを盛り上げるのだが、それは読んでのお楽しみだ。