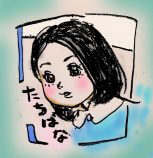“夭逝の天才”と謳われた画家・中園孔二の素顔とは? 評伝『穏やかなゴースト』を読んで

元来、体育会系の彼は、衝動と才能だけで絵を描き続けていたわけではなく、大事は小さな練習の積み重ねで成るということを体感で知っていた。絵はうそをつかない、今の自分が何を考え、何を知って、何に触れているかがすべて出るのだ、と言葉を残していたように、彼は絵を進化させるために、みずからを顧みて、思索を深めることも怠らなかった。そういう人はきっと、ずっと、さびしかっただろうと思う。恋人だった女性が、中園が存在まるごとで向き合ってくる姿勢に対して、寂しかったんじゃないか、とふりかえる場面も作中にはあるが、自己の内面をつきつめていくということは、誰とも重なることができない個を自覚するということでもある。
だから人は、ある程度のところで、考えることをやめる。なんとなく重なっているように思える“共感”の浅瀬で、心の安らぎを守る。でも、中園のように、すぐれた創作者にはそれができない。とことんまで個を追及して、それでもどこかにいるかもしれないソウルメイトを追い求めることをやめられなくて、さびしさと期待の隙間を埋めるように絵を描き続けていたのではないだろうか。
そう思うのは、中園が“いいところ”に自分の好きな人を連れて行く人だったからだ。彼は、孤高の人ではなかった。好きな人と、これだと思えるものを共有したがった。絵が売れることにはあまり興味がないけれど、絵を“わかって”もらえることを何より喜んだのは、描くことが彼にとって、他者と心をかわす手段でもあったからかもしれないな、と思う。わかってほしいし、わかりたい。自分の理解にとどまらない、もっと広くて深い世界を知って、美しい景色を手に入れたい。その貪欲さが彼の絵を、ただの自己表現にとどまらない、複雑な表現へと駆り立てたのかもしれない。
作中で、もっとも印象に残っている中園に対する弁は、藝大同期・小川真生樹(マイキ)のものである。
〈バカですよ、バカ。あいつはフィジカルに自信があって、だから大きなキャンバスにも向かっていけたけど、その身体性だけでは乗り切れないものにいずれぶつかったはずで、だからその先が見たかったのに、まだ始まってもいないんですよ、あいつは。だから描き続けなければいけない作家だった。神格化して騒ぐなんて最悪ですよ。〉身体性だけでは乗り切れないものに、実際、亡くなる前の中園は触れかけていたような気がする。それを乗り越えた先で彼がどんな絵を描くのか、見てみたかったと心から惜しく思う。
中園を語る人たちの言葉からは、彼ら自身がどう生きているか、もうかがい知れる。中園という才能をどう受け止め、どのように愛し、そしてどのように自らの創作に向き合っているのか。それは読み手の私たちも同じである。彼の絵と、言葉と、そこに残された魂の断片に触れ、何を感じるのか。内心の個性を探り続けた先で、どんな情景に辿りつけるのか。その模索を終えないことこそが、中園孔二という画家に対する、何よりの餞(はなむけ)なのではないかと思う。