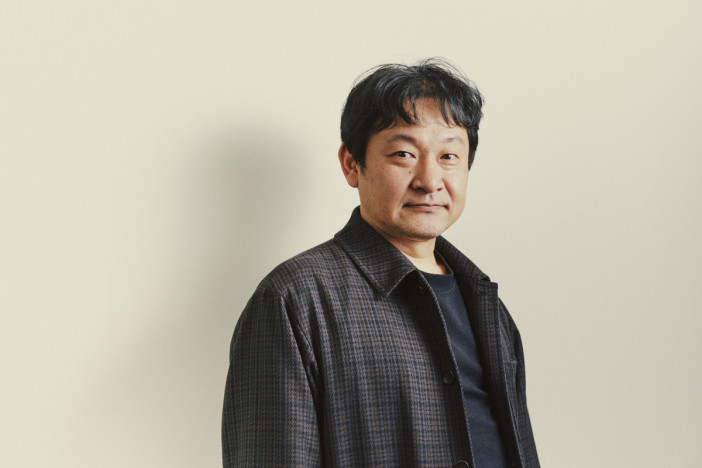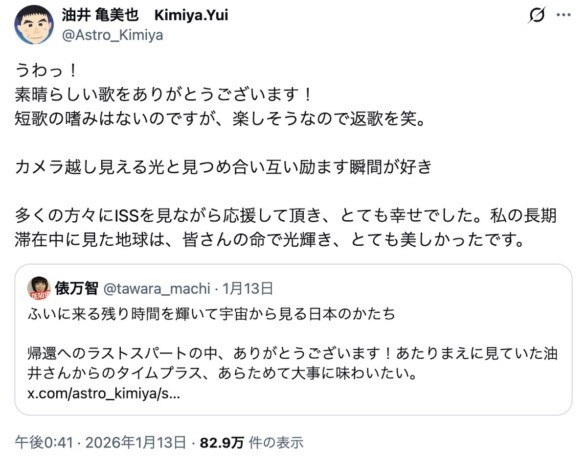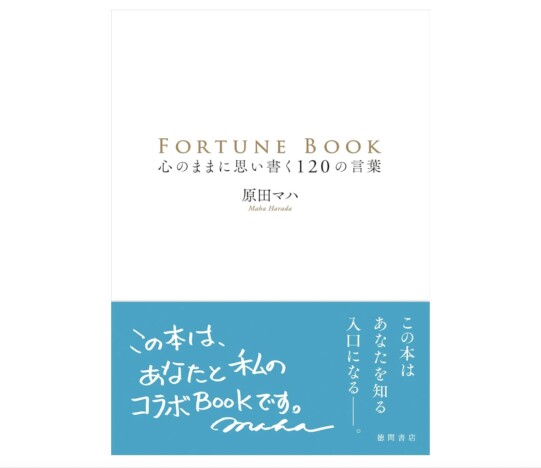「週刊東洋経済」アニメ特集で浮き彫りになった業界の”リアル”「製作」と「制作」の分断問題とは

近年、日本のエンタメ産業の中でアニメの存在感が飛躍的に高まっている。同時に、業界内外から労働環境問題など、ウェブ記事やSNSでの発信で様々な問題が指摘されている。それぞれの立場や見方・切り取り方によって意見は玉石混交だ、
たくさん意見が出ること自体はいいことだ。それだけ関心がもたれている証拠であり、需要もあるということでもある。しかし、実際のところ、アニメ業界は今どうなっているのか、断片的な情報に触れているだけではその実態が見えにくい。アニメ産業は好調なのか危機に瀕しているのか、一体どっちなのか、外から見ている人間にはわかりくい。
東洋経済の2023年月27日号(発売は5月23日)の特集「アニメ 熱狂のカラクリ」はそんな複雑に入り組んだアニメ産業の最新のリアルをわかりやすく解き明かし、問題点と可能性の両方を提示している。
アニメ「製作」と「制作」の壁
アニメ業界は複雑でわかりにくいと先に書いたが、何がわかりにくいのか、本特集の担当編集が「編集部から」欄で端的に記している。
担当の1人で昨年入社の高岡氏は、以前はほとんどアニメを観ていなかったという。そんな高岡氏がアニメ業界を理解する上で最初につまずいたのが「製作」と「制作」の違いだそうだ(P14)。 辞書を引けばほとんど同じ意味として用いられるこの2つは、アニメ業界では、企画や出資側を指す「製作」、アニメ作りの実作業を担うことを「制作」と明確に分けて用いられる。結論を先に書くと、東洋経済のような老舗の経済専門誌が特集を組むほど好調な部分は「製作」であり、「制作」にはその恩恵が行き渡っていない。この分断問題をきちんと取材で明らかにしている。
本特集は製作委員会の利益を生み出す構造と、構成する会社の変化など業界の勢力図の変化を丁寧に抑えている。ひと昔前、パッケージ販売が収益の柱だったころとは異なり、配信会社の存在が大きくなった現在では、放送前に配信契約を締結し、それが制作費計算の大きな要素を占める。その時、重要になるのは原作の知名度や制作スタジオの「格」であり、配信会社はアニメスタジオにランク付けしていて、最高Sランクの会社では30分アニメ1話に6000万円ほどの予算がつくようになっているという。平均でも現在は3000万円ほどの予算だそうで。10年前は1話1500万円ほどだったというので、現場の制作費自体は大きく伸びている(しかし、求められるクオリティが上がっているため、1話制作にかかる人数も増えている)。「6000万円もの価格がつけば放送開始前から投資回収が見えてしまう」(P41)ので、有力なスタジオを抑えることができるかどうかが、製作委員会の幹事会社に求められる能力だという。また、現在は窓口手数料が大きな収益源になっていることにも言及するなど、製作委員会のお金の流れを詳しく解説している。
しかし、その利益が「製作」に独占され、「制作」に還元されていないのが実情だという。ただ一部の有力スタジオは委員会と交渉してその権利を勝ち取っているとも書かれており、制作スタジオの「格」によって台所事情に格差があることをほのめかしている。
本特集は、制作を担うクリエイターの低賃金問題にも言及。旺盛な需要で引く手あまたを通り越して人材難になっているので、実力あるアニメーターの賃金は上昇しているが、実力がつく前の若手がその波から取り残されていると指摘している。
日本アニメーター・演出協会のアンケートによると年収1000万円以上と答えたのが全体の3.3%だそうだ。実力あるアニメーターの賃金上昇を支えているのは、スケジュールを抑える「拘束費」だ。あるスタジオが拘束費月80万円を提示したことが業界で話題になったという(P48)。それだけの拘束費に加えて従来の出来高を加えれば確かに年収1000万円以上はというのは、あり得る数字だ。
しかし、近年はスケジュールの圧迫やリモート作業の普及もあり、ベテランが若手に教えられる機会が現象していることが課題になっているという。しかし、「人手不足で仕事だけは減らないから、素人レベルのまま仕事を続けている(西井輝美氏)」(P49)問題を抱えているそうだ。
この状態は、ある種の悪循環を生んでいると思われる。若手の絵に修正指示を出すスケジュールの余裕がないから、作画監督が修正することが常態化する。若手は直されなかったので、これでいいのだと思う人が増える。そういう若手が増えるとますます修正が必要なカットが増えていき、ますます修正のための作画監督の人員が必要になり人手不足に拍車がかかる。最悪の場合は納品に間に合わず放送延期で赤字拡大となる。
この悪循環を解消し、人材の育成を充実させないと、せっかく好調でまだ伸びしろがあるアニメ産業をこれ以上拡大させることができなくなってしまう。アニメで儲けたい会社はここにも目くばせしないとこれ以上パイを増やせない、儲けるためにも人材育成は必須だということがよくわかる。
こうした製作と制作の分断から生じる課題に挑む会社の例としてトムス・エンタテインメントとMAPPAの二社が代表のインタビューで取り上げられている。二社の課題に対する取り組みは、出資側に参加し「製作」も手掛けるという点で一致している。
原作を持つ出版社はどれだけ儲けている?
さらに、現在のアニメ人気を支えている原作の供給源となっている出版社についても触れている。原作を手掛ける出版社はいったいどれくらいアニメで儲かっているのは、大手出版社が非上場企業が多いためにわかりにくかった。しかし、東洋経済は各所の資料を基に独自にグラフを作成しており、集英社、講談社、小学館の大手3社の純利益がここ数年で激増していることを指摘している。このグラフによると2018年までは、3社合計で純利益が100億円以下だったものが2022年には600億円を超えており、これを牽引しているのが、『鬼滅の刃』の大ヒットに象徴されるアニメ人気だとしている。人気マンガのアニメ化権はコンペで争奪戦となっているという。
また、配信ビジネスの明暗にも触れており、IPを上手く活用できないNetflixとグループのシナジー効果で成功しているソニーを対照的に紹介しているのも印象的で、現状をしっかりと取材できていると思う。
他にもアニソンの現状や声優業界のセクハラ問題、地方創生としての「聖地巡礼」、映画会社との関わりや海外へのグッズ展開の難しさなど、多岐に渡るアニメ産業の現状をしっかりとリポートしている。一部数字の正確性について議論も出ているが、これだけ網羅的にアニメ業界の今を取材しているのは稀有だ。
専門誌の実力と必要性を示した意義ある”総論”
アニメ業界の可能性や問題点は、それぞれ各論として様々に言及されてきた。しかし、細切れの情報だけでは、大局的な議論につなげにくい。本特集を読めば、いかに今のアニメ業界が複雑化しているのかがわかるはずだし、一つの問題に一つの原因ではなく、多くの要因が絡み合っているため、何をどう手当すべきを議論するためにも総論が必要だ。これはその総論を生むためのよいたたき台になるだろう。
雑誌の苦境が叫ばれて久しいが、このように多岐に渡る内容を丹念に取材し、わかりやすくまとめた上でパッケージングして出せる雑誌という媒体の良さを実感できる特集だ。筆者もアニメ業界の取材をウェブメディアで単発で行うことはあるが、正直各論になりがちで一つの大きな総論を導けていない、ウェブ専門のメディアではこのような大規模な特集を組むことが難しい。専門誌の力は改めて重要だと思い知らされた。
どんな課題を解決するにせよ、現在の状況を正確に把握することから始める必要がある。この雑誌はアニメ産業の今後の課題を議論する上で大きな助けになるだろう。