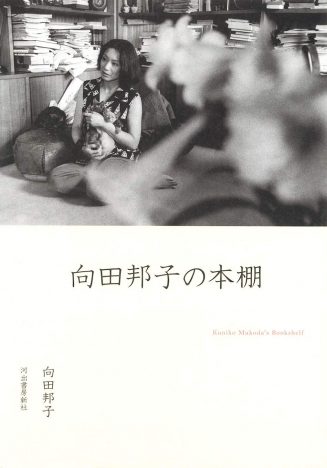インテリアスタイリストの草分け・吉本由美が振り返る、70年代の東京と雑誌文化 「いま思えば当時はとても自由だった」

7月下旬、吉本由美氏の最新エッセイ集『イン・マイ・ライフ』が刊行された。吉本氏といえば、『アンアン』『オリーブ』『クロワッサン』『エル・ジャポン』などマガジンハウスの雑誌を中心に、1970年代から活躍した雑貨・インテリアスタイリストとして知られる。
また、暮らしのスタイルや猫、動物園に水族館、雑草などなど、その時々の関心に応じてテーマを変え、繰り出されるエッセイの数々に魅了されてきた人も多いはずだ。
『イン・マイ・ライフ』は、前半に東京での若き日々のこと、後半は郷里の熊本に帰ってから現在のことと明確に2つに分けた構成を取る。「スタイリスト」といえば誰もがファッションしか思い浮かばなかった時代にインテリアを手がけた吉本氏の先見性・独自性は、70~80年代の東京の空気の輝きとしっかり通じていて、カッコいい先輩として眩しい。そして44年住んだ東京を離れ、熊本に帰る時の迷いと決断には、ヒリヒリするようなリアリティがある。
8月19日、吉本さんへの電話インタビューは、現在の熊本での暮らしを象徴するような、あるハプニングで幕を開けた。(北條一浩)
――もしもし。北條です。
吉本由美(以下、吉本):今日はほんとにすみません。まさかこんなことになるとは……(※電話で行うことになっていたインタビュー。当初の予定は14時からだったが21時スタートになった)。ブレーカーが落ちてしまったので電気屋さんに来てもらったんです。ところがいくら調べてもブレーカーが落ちた原因がわからない。「今度は建築関係の人と一緒にうかがいます」ということでひとまず今日は終わりました。
――えっ。じゃ、いま電気点いてないんですか?
吉本:リビングルームの天井灯は点いてません。卓上ランプみたいなのだけ。おしゃれな間接照明(笑)。今回は電気だけど、2週間前は排水溝がめちゃくちゃになっていて、取り替え工事をやらないといけないと言われました。その前は屋根。考えたら家のメンテナンス料金、300万円以上使っているんです。建てて65年くらい経っている古い家だし、ああ、歳取るってこういうことかと。まるで自分を見ているよう。
――マンションに移る気はないんですか?
吉本:移りたくても、「リバースモーゲージ」(※注)を始めてしまったから。この家を担保にお金を借りているので、家が売れないんですよ。なんて最初からグチばかりでごめんなさい(笑)
タイトルは平野甲賀の書き文字をイメージ

――『イン・マイ・ライフ』はまず横須賀拓さんの装丁と徳丸ゆうさんのイラストレーションがステキですね。カバーの表側は若い時の吉本さんを思わせるイラストレーションで、裏は現在という。
吉本:装丁については、横須賀拓さんにはほんとうに迷惑をかけてしまいました。というのも最初はこの本、2年前から作ることが決まっていて、平野甲賀さんが装丁することになっていたんです。ところが私がなかなか書けなくて、平野さんから「あんまり待たせたら俺は死ぬよ」と言われたことがありました。そうしたらそれがほんとに……(※編集部注:平野氏は2021年3月に逝去された)。それで急遽、横須賀さんにピンチヒッターをお願いすることになりました。平野さんの後任でしかも時間があまり無いなんて、ほんとにひどい依頼の仕方だったと思います……。それなのにサッと軽快に仕上げてくださった。
――そんな経緯があったんですね。さすが横須賀拓さん。「イン・マイ・ライフ」というタイトルがまたドンピシャですが、スッと決まったんですか?
吉本:これも平野甲賀さんと関係があって、あの書き文字が大好きなんです。そこであんまり長いタイトルだとうるさいと思って、内容をズバッと表すにはこれかな?と。平野さんの書く文字の絵も浮かびました。だから、ジョン・レノンの歌詞とか、正直あんまり関係ない(笑)。
――なかなか書けなかった、というのは、後半の熊本での現在のことが書けなかったということですか?
吉本:そうです。ずっと家に居るから動きというものがないでしょう。庭のことや、仕事どうしようと悩むばかりで展開がない。高年齢の人が、こうこうこういう経験をして、いまこうなってます、みたいな本はいっぱい出てますけど、皆さんステキな生活をなさってるわけで、私みたいに貧乏でたいへんな暮らしを書いてもしかたないな、と。
――でもそういう「高齢になってからのステキ生活」みたいな本は他にいっぱいあるわけです。いまはむしろ、「貯金が全然ないけど、気が付いたらこんな歳になっちゃった」とか、コロナ禍で東京や首都圏を離れる人も多いわけで、『イン・マイ・ライフ』の当初の意図とは違うかもしれないけど、図らずもタイムリーな部分がすごくあると思います。
吉本:それはそうかもしれない。たまたまね。
いろいろなことが始まる気配があった「東京」
――この本に書いてある60年代後半から70年代の東京の空気は、ほんとに輝いているように読めます。
吉本:学生運動もあったし、いろいろなことが始まる気配がありました。東京のあちこちで「動いてる」という感じ。あと、いまにして思えばとても自由だった。当時は「自由だ」とは思っていなかったけど、いまみたいに行き詰った東京を見ていると、「ああ、自由だったんだな」と思います。街全体がのびのびしてた。バブルまではそうだったと思います。自分なんか若い時はめちゃくちゃできたのに、いまはコロナ禍も不況もあって、外で容易にお酒も飲めないし、若い人、行くところが無いですよね。楽しみはなんだろう。
――銀座のみゆき通りを歩いていて『スクリーン』編集部を見つけ、いきなり階段を駆け上がって入って行っちゃう吉本さんの行動力に驚きます。そもそもそういう性格と言ってしまえばそれまでかもしれないけど、やはり時代と、当時の東京の空気感みたいなものを読んでいて感じるんです。
吉本:もう少し私に常識があれば、いきなり会社に行って「働きたい」と言ってもダメだということはわかったと思うけど(笑)、映画は小さい頃から好きでよく観ていて、『スクリーン』もずーっと愛読していたから、「ここが編集部か!」と興奮してしまって。
――中学時代からよく映画館に行っていたとありますね。熊本市はすごく映画館の多い街、という記述も。
吉本:ほんとによく観てたし、映画館は当時、九州でいちばん多かったらしいです。小さい頃はもちろん親に連れて行ってもらったけど、中学になってからは基本、一人。
――そしていざ『スクリーン』編集部に入ると、取材などの思い描いていた仕事は回ってこなかったんですね?
吉本:そう。でもよく考えたら、若くていちばん下っ端で経験もないから、いま私が上司でもそんな子にあれこれ頼みませんよね。でも、理解できなかったのは、当時、取材に行くのは必ず男と決まっていて、それは「なんで?」と思いました。でも、「どうして女子じゃダメなんですか?」と編集長には言えなかった……。とはいえ編集部の空気は楽しくて、おじさんばかりだけどみな仲がよかったんです。出張校正で2日間缶詰なんてなると、まるで親戚のおじさんたちと温泉に来てるみたい(笑)。そういうのですごく救われてました。そしてなんと言っても、たくさんの映画を毎回タダで観ることができる。
――『スクリーン』編集部を出て、やがて吉本さんはインテリアスタイリストとして『アンアン』『オリーブ』などで仕事されるようになります。マガジンハウスのほうはどうでしたか?
吉本:こちらは1970年時点で編集部も半分は女性だった気がします。それに出入りしているスタイリストはみな女性だから、編集部は「女の城」という感じ。
「インテリアスタイリスト」を名乗って
――「スタイリスト」という存在の当時の様子に興味があります。
吉本:高橋靖子さん(『表参道のヤッコさん』等の著者でもある)が、確定申告の申告書に「スタイリスト」と書いたのが、スタイリストが日本で職業になった最初だと言われています。それから脈々と、ファッションの人がスタイリストと呼ばれるようになるんですね。私は部屋づくりがすごく好きで、インテリアを始めた時は、編集長なんか「おまえの肩書はなんだろうね」と困って、最初は「インテリアコーディネーター」と言ってました。ところがそう名乗っていると、住宅関連の人からどんどん電話がかかってくる。それでやっぱり「スタイリスト」でないとマズイけど、ファッションに間違えられないように、「インテリアスタイリスト」にしました。
でも一度、原由美子さんに「ファッションのほうもやってみない?」と言われたことがあるんです。で、一度だけ原さんと一緒にやったけど、やっぱり「イヤだ」とハッキリ言いました。自分でこのコーディネートが好きだと思っても、モデルが着ると自分がその服に対して持っていた雰囲気が変わっちゃうんですね。私はやっぱり家具やモノのほうがいいなと。
――当時は超忙しかったですよね?
吉本:最初の頃は、インテリアや雑貨はいまみたいにもてはやされてなくて、洋服のシーズンの狭間、雑誌でつなぎの時にしか仕事がありませんでした。だから、インテリアスタイリストだけじゃ食べていけないからライター仕事もするようになりました。やがてどんどんインテリア、雑貨ブームになってからは確かに忙しかったかもしれません。