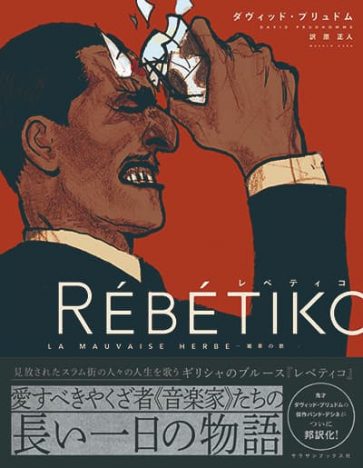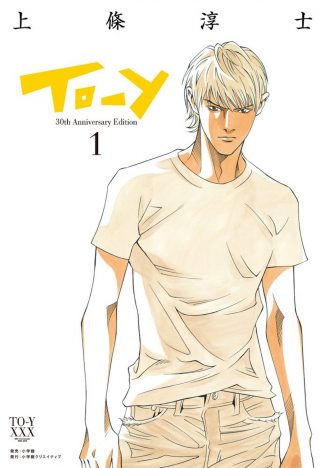Mr.Childrenの“読む”ベストアルバム『道標の歌』が示す、メンバー4人のパワーの均衡

触れられない「社会」との交錯
さて、冒頭に述べた通りこの本のコンセプトは「“読む”ベストアルバム」なのだが、「ベストアルバム」といえばファンから「なぜあの曲が入っていないのか」という声があがるのがある種の通例である。ここではそんなお約束にのっとって、本書では触れられていないテーマにあえて目を向けてみたい。
約30年間のバンドの歴史をある程度均等に触れていくこの本の構成上、いくつかの大きなトピックはあっさりと触れるのみにとどまっている。たとえば、「ミスチル現象」とも呼ばれた巨大なムーブメントを世の中全体に巻き起こしていた最中での活動休止(97年春~98年)については、その時に憶測を呼んでいた解散の噂に対する「ちょっとコンビニに行っただけなのに、捜索願いが出されたようなもの」という桜井のライブでのMCを引用し、加えて休止中における各人の音楽活動(桜井のプロ・トゥールズを使った曲作りや中川・鈴木の別バンドでの活動など)にフォーカスする形で、あくまでも「特に不穏な裏もない休み」である旨がさらりと記述されている。
一方で、当時のメディアを紐解くと、そういった雰囲気とは異なる空気を感じることができる。以下はいずれもこの時期に関する桜井のインタビューでの発言である。
「今あんまり人とコミュニケーションしたくないんですよ」(『ROCKIN’ON JAPAN』97年6月号)
「(休みの間は何をしていたのか?)まあ最初は写真週刊誌をまいたりだとかですね(笑)」(『ROCKIN’ON JAPAN』99年1月号)
前述した「ミスチル現象」の中、4人は急激に拡大するバンドへの支持を一身に受けながら走り続けていた。そこから生まれた歪みは様々な形で表面化し、桜井のプライベートなスキャンダルが大きな話題となったこともある。そんなムードの中で過激な行動をとるファンに対して、桜井がファンクラブ会報で直接警鐘を鳴らすこともあった。そういった世間のうごめきをファンとして見てきた自分(当時まだ10代の子供ではあったが)の体感と比べると、本書における活動休止前後の記述はどうにも表面的なものに終始しているという印象を持たざるを得ない。
また、ブレイク以降常に「みんなのうた」を歌う役割を担ってきたMr.Childrenは、音楽産業のあり方が大きく変化した2010年代においてどういったポジションをとるべきか難しいかじ取りを迫られてきた。そんな揺らぎは各種インタビューでも語られている。
「(アイドルの人気が高まっていることについて)かつてブロマイドを売ってた職種の人達がCDを売りましたっていう話だから、音楽界の話ではないんだろうなっていう」(『MUSICA』2015年1月号)
「どこにボールを投げていいのかわからないっていうのはすごくありましたけどね。『今、必要とされてるポップソングってなんだろう?』っていう」(『ROCKIN’ON JAPAN』2015年7月号)
「何をもってMr.Childrenという存在を定義するか」とでも言うべきこのような根源的な問いに対するスタンスが開陳されていることを本書の読了前には期待していたが、残念ながらそういった角度からの掘り下げは特になされていなかった。バンドに近い書き手による本だからこそ、直近の10年、つまりはバンドの歴史の3分の1程度を占める時期において彼らが直面していた課題に対してもっと独自に切り込んでいくことができたのではないだろうか。
「正史」をどう受け取るか
ちなみに、前述の「ミスチル現象」の渦中に上梓された『es―Mr.Children in 370 DAYS』においては、桜井の動向が週刊誌で取り上げられるような時代のムード(先ほど触れたスキャンダルではなく、ブレイク直後に散見された彼らの過去や私生活を引っかきまわすような報道)に対して苦言を呈する記述も見られた。この『es―Mr.Children in 370 DAYS』の著者は、『Mr. Children 道標の歌』と同じく小貫信昭である。
94年から95年にかけてバンドに密着してその一挙手一投足をドキュメンタリータッチで追いかけた『es―Mr.Children in 370 DAYS』には、彼らの「やんちゃ」な側面が赤裸々に記録されている。それらと比べると、『Mr. Children 道標の歌』に書かれている内容は良くも悪くも「きれい」である。また、楽曲作りそのものに対する葛藤やそこでのブレイクスルーについての仔細な記述が多数ある一方で、「そういった楽曲を社会に向けてどう投げかけるか」といった問題意識について語られるパートは本書全体を通して少ない。
冒頭でも述べた通り今回の本は「オフィシャル」な体制で作られており(本書用に改めてインタビューも行われている)、そう考えるとこの本で描かれたバンド像は「現在バンドとして伝えたいMr. Childrenのあり方」と重なってくる部分も大きいだろう。つまり、「あくまでも真摯に音楽にのみ向き合ってきたMr.Children」というのが今のバンドが打ち出したい姿であり、「世の中に現象を起こし、大衆との付き合い方に苦心してきたMr.Children」といった側面は後景化している。そしてそれは、よりフラットなスタンスで音楽を生み出そうとしている新作アルバム『SOUNDTRACKS』がまとう雰囲気ともリンクしている。
「ドキュメンタリーは嘘をつく」「history=his story」といった言い回しがある通り(前者は映画監督の森達也の書籍のタイトル、後者は実際の”history”の語源とは異なるが「歴史とは彼=勝者・為政者の物語である」といったニュアンスで使われる表現)、誰かが何かについて語ろうとするときには必ず発信する側の意図がそこに入る。『Mr. Children 道標の歌』は、Mr.Childrenの「正史」であり、それはすなわち「戦略的な取捨選択を経て紡がれる”ある側面”からの歴史」に他ならない。そういったストーリーを額面通り受け取るのも悪いことではないが、ここでは「バンドの本当の姿は本に書かれていない出来事に潜んでいるのでは?」という楽しみ方を提案したいと思う。「語られていないことにこそ価値がある」という角度からの考察は「批評」の入口に他ならないし、そんな視線がファンダムのあり方をより分厚いものにする。そしてそういったファンからの批評的なまなざしは、アーティストのアウトプットの質を必ず押し上げるはずである。
■レジー
1981年生まれ。一般企業に勤める傍ら、2012年7月に音楽ブログ「レジーのブログ」を開設。アーティスト/作品単体の批評にとどまらない「日本におけるポップミュージックの受容構造」を俯瞰した考察が音楽ファンのみならず音楽ライター・ミュージシャンの間で話題になり、2013年春から外部媒体への寄稿を開始。著書に『夏フェス革命 -音楽が変わる、社会が変わる-』(blueprint)、『日本代表とMr.Children』(ソル・メディア、宇野維正との共著)がある。Twitter(@regista13)