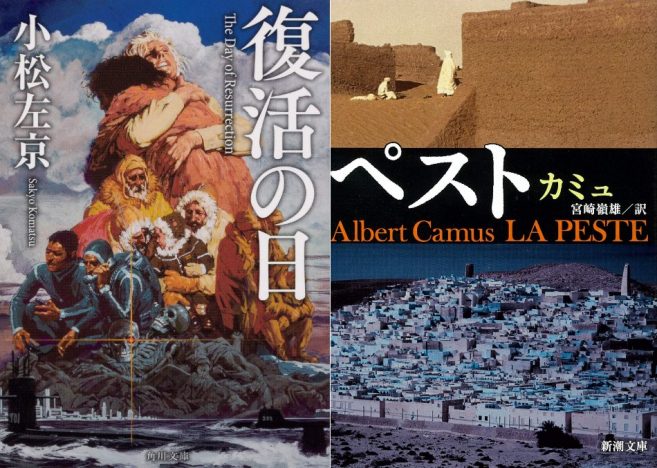人工知能、監視社会、加速主義……中村文則『R帝国』はコロナ禍の現実とシンクロする

2017年に単行本が刊行され、今年5月に文庫化された中村文則『R帝国』が、よく読まれているらしい。新型コロナウイルスに関して4月7日に国から出された緊急事態宣言が、5月25日に解除される少し前に文庫版は発売された。宣言解除後もウィズコロナの新しい日常を求められ、不安は続いている。文庫版であらためて『R帝国』を読み返すと、そんな今の気分にシンクロする内容であることに驚く。
「朝、目が覚めると戦争が始まっていた」と小説は始まる。R帝国の一市民・矢崎は、隣のB国との戦争をニュースで知る。だが、間もなくこの島国の最北にあるコーマ市をY宗国が攻撃してくる。一方、「党」が統治するR帝国では、民主主義を形だけ維持するため、極小の野党が存在した。その党首の秘書・栗原は、謎の組織Lと接触する。矢崎と栗原は、それぞれ戦時下の大きなうねりに巻きこまれる。重いテーマを有しながらも、エンタメ感満載でリーダビリティの高い作風だ。
冒頭にはアドルフ・ヒトラーの言葉「人々は、小さな嘘より大きな嘘に騙されやすい」が引用されている。作中の防衛大臣は、移民が住む区は壁で囲え、費用は移民が払えとアメリカのトランプ大統領のような発言をする設定だ。ヘイト・スピーチ、フェイク・ニュース、生活保護バッシング、自己責任論、歴史修正主義、陰謀論などのモチーフが盛りこまれ、右傾化する日本、各国で国家主義が台頭する世界の現状を風刺・批判している。国名がR、抵抗する側がLとされるのも、Right(右)とLeft(左)を含意したものだろう。Racism(人種差別)、Liberty(自由)など、RとLからはそれぞれ他の言葉も考えられ、様々な思考を誘発する記号になっている。
「党」は情報を操作して国民の支持をとりつける。また、『R帝国』では、無人兵器の発達した未来を舞台にしており、なかでも物語のキーとなるガジェットが、HP(ヒューマン・フォン)だ。それは人工知能を搭載した携帯電話であり、人格のごときものがある。持ち主と会話するだけでなく、自律的な思考もしてHP同士のやりとりも行う。HPは「党」が国民のデータを吸い上げ、監視する手段でもある。
コロナ禍では、有力政治家が有効性や精度の不確かな情報や決めつけでキャンペーンを繰り広げ、国民を戸惑わせた。一方、アメリカ政府はTikTokについて、中国が利用者の個人データを不正取得するスパイアプリだと規制に動いている。予期せぬ非常事態、為政者の情報操作、通信サービス利用の危険といった『R帝国』の諸要素は、最近の現実とシンクロしている。しかも同作では、ウイルスも物語のポイントなのだ。単行本刊行時以上に今が読み時の作品になっている。
もう1つ、時代とのシンクロとしてあげられるのは、最近の日本における加速主義への注目だ。加速主義とは、現在の政治・社会に対する思想である。それは、共産主義が世界的に凋落した後、選択肢は資本主義しかないとしたマーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』(2008年。2018年に日本語版)の考えが前提といえる。資本主義を加速させ、限界まで押し進めることでしか出口は見出せない。そのような思想であり、加速主義には左派と右派で様々な傾向があるが、シンギュラリティ(技術的特異点)に突破口を期待するSF的志向もなかにはみられる。また、右派加速主義は、ポリティカル・コレクトネスやフェミニズムなどは自由の妨げだとする新反動主義と結びついてもいる。その方面の代表的論客ニック・ランドがブログに記した『暗黒の啓蒙書』(2012年)の翻訳書が、やはり緊急事態宣言下の今年5月に刊行された。
海外のネット発の議論だった加速主義は近年、日本の紙媒体でも論じられるようになり、徐々に知られるようになってきた。コロナ禍で各国経済が減速を余儀なくされる今、資本主義の速度の意味が問い直されている。とはいえ、加速主義はまだ思想好きの一部の話題にとどまるし、『R帝国』にこの思想への言及があるわけではない。だが、同作は、資本主義世界に生きる作者が、なかば必然的に加速主義と世界観を共有して書いたものといってよい。
作中では、戦争が世界的な経済活動の一環として行われ、テロも需要と供給に応じた一種の取引であることが、政界の黒幕・加賀の口から語られる。彼はそんな醜悪な資本主義の外へ出ようとは考えない。多くの犠牲者が出ることを厭わず、効率的に戦争を遂行しようとする。資本主義の加速を是とするのだ。
しかし、『R帝国』のディストピアは、「党」が国民を一方的に圧制で支配するのではない。誰かを犠牲にして生き延びる後ろめたさを国民が抱えなくていいように、「党」は国家の正義のため、彼らは喜んで犠牲になったのだというロジックを用意する。自分は悪くない、正しいと思いたがる国民の承認欲求を、「党」はHPを通じてくみとる。その意味で民意に応えてもいるのだ。