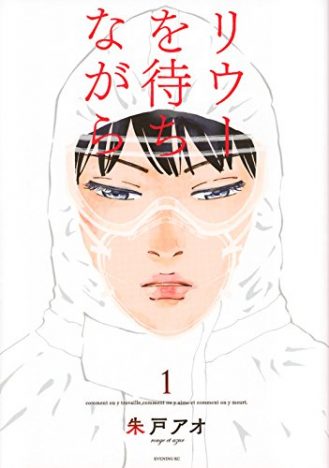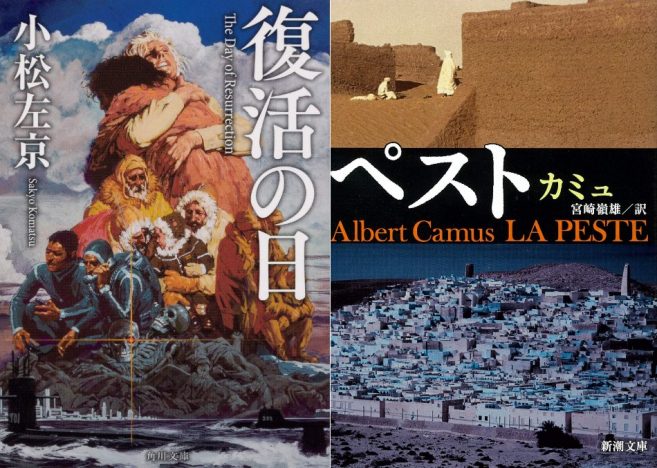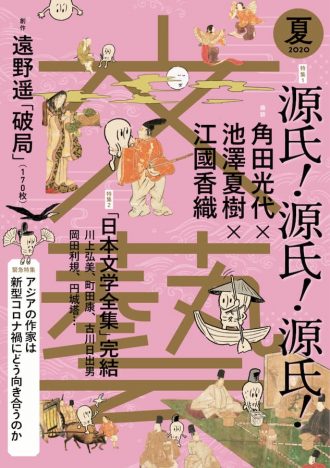小さな田舎町に漂う、不穏な同調圧力ーー吉村萬壱『ボラード病』が描くのはコロナ禍の日本か?

テレビをつけると、今日も新型ウィルスの報道をしている。耳に入ってくるのは負の情報ばかり。気が滅入りそうになる中で前に一度読んだこの本を手に取った。吉村萬壱の『ボラード病』だ。
架空の小さな田舎町B県海塚(うみづか)市。過去の災厄を乗り越え、復興を掲げる町。3カ月前に越してきたばかりの小学生の恭子は、町全体に漂う違和感を感じながらもその正体が何なのかわからないでいる。母は引っ越してきてから常に何かに対してピリピリしており、気に入らないことをすると叩かれる。海塚の人たちが目指す復興とはどういうことか。恭子が通う海塚小学校の教室に貼られている「五年二組の十の決まり」にもそれは表れている。
一 自主学習にはげもう。
二 あいさつをしよう。
三 給食を残さず食べよう。
四 決して弱ねをはかない。
五 教室で大声を出さない。
六 空気を読み取ろう。
七 自分の感覚を大切にしよう。
八 結び合おう。
九 りっぱな海塚市民になろう。
十 みんなは一つ。
海塚の子どもはこうあるべきだ。そこから外れた子どもはいらない。担任の藤村先生は海塚にそぐわない答えを出した生徒を、授業中ずっと立たせ続ける。授業の終わりには決まって「海塚讃歌」を歌わせる。恭子に与えられた選択肢はふたつ。先生の思うようないい子になるか、自分らしさを持ち続ける代わりに孤独を抱えて生きていくか。小さな存在が孤独を抱えて生きていくには、この世界は広すぎる。クラスでも浮いた存在であり、〈りっぱな海塚市民〉になりきれない恭子はそのうち同級生にも異端児扱いされるようになる。
あるとき、授業中に30分ものあいだ立たされ、そのあと具合が悪くなったのに保健室に連れて行ってもらえなかった同級生のアケミちゃんが亡くなってしまう。通夜の最後に父親が言った挨拶の中で、海塚の理想の子どもとしてのアケミちゃんが形作られていく。〈アケミちゃんは海塚市の一部になりました。〉恭子の知っていた彼女は、もうどこにもいない。
次々と亡くなっていく子どもたち、急に姿を消してしまう大人たち、海塚をうろつく背広の男たち。あんなに海塚市民として教育に力を入れていた藤村先生もいなくなり、副担任の佐々木先生が正式な担任に就くことになる。
いなくなった人についての説明はされないまま、たったひとりの肉親である母が体調不良で病院に運ばれ、恭子はひとりぼっちになる。母は恭子につらく当たっているように見えて、必死で娘を守っていた。「復興」「絆」を事あるごとにアピールする、気持ち悪く、残酷な世界から。母が不在のあいだに、恭子は海塚に取り込まれていく。〈みんなが歪んでいたのではなく、私の目と脳が歪んでいたから世界が歪んで見えていたのです。〉恭子にとってディストピアである海塚町は、「同調」したひとたちにとってはユートピアだ。そのことに気付いた恭子の前に道が拓けていく。思想ひとつで世界は反転する。