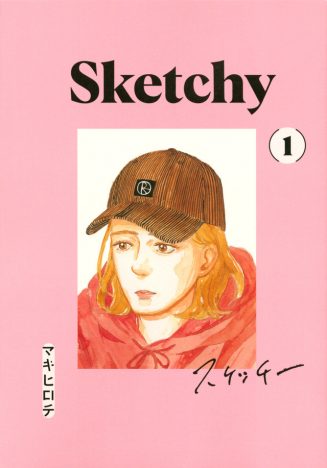『第0巻』が異例の50万部突破で再注目 『ドラえもん』の漫画的手法に見る、手塚治虫からの影響

何よりも「わかりやすさ」を目指したFの手法
昨年11月27日に発売された『ドラえもん』の第0巻が爆発的に売れている。同書の目玉は『よいこ』や『小学一年生』などの6誌に掲載された6つの異なる「第1話」の収録だが、先ごろついに50万部を突破したらしい。もちろん当初からある程度売れるのを想定して立てられた企画ではあっただろうが、この短期間での50万部越えというのはおそらく版元の予想をはるかに上回る数字だったはずであり、藤子・F・不二雄が生み出した未来からやってきたネコ型ロボットの根強い人気をあらためて世に知らしめる結果となった。
そこで、この『ドラえもん』という作品が日本の漫画史においてこれまでどういう風に評価されてきたのか、自分なりに考えてみたのだが、本作は誰もが知っている国民的な漫画でありながら、たとえば『あしたのジョー』や『デビルマン』、『カムイ伝』といった名作(あるいは手塚治虫やつげ義春の作品)ほどには、漫画批評の対象としてきちんと語られてはこなかったように思える(もちろん米沢嘉博の『藤子不二雄論』など、読むべき批評がまったくないわけではないが)。
その背景には、児童向けコミックというジャンル自体が今の日本の漫画シーンでは主流と見なされていないことなども関係しているかもしれないが、いちばんの大きな理由としては、そもそも作者の藤子・F・不二雄自身が『ドラえもん』をそうした批評家好みの作品にあえてしなかったということが考えられるだろう。
そう、何よりも「わかりやすさ」を優先させたFが『ドラえもん』という作品で目指したのは、漫画の方法論(=読み方)をよくわかっていない小さな子供でもすぐに作品世界に入っていける、大衆のための身近なエンターテインメントだった。そしてそれを単に目指すだけでなく、生涯を通してコツコツと描きつづけたことこそが、藤子・F・不二雄という漫画家の最大のすごみだったと私は思う。
では、その『ドラえもん』のわかりやすさとはいったい何か、という話をしたい。まずはコマ割りについてだが、もしお手元に単行本があるようなら、何巻でもいいので適当なページを開いてみてほしい。おそらくあなたがいま目にしているのは、8〜10個の似たような大きさのコマを4段で組んだ単調なページのレイアウトではないだろうか。なかには大ゴマを使ったページもなくはないが、基本的にはこれが『ドラえもん』のコマ割りの定型ということになる。
誤解を恐れずにいわせてもらえば、いまどきこんな古風なコマ割りをする漫画家はほとんどいない。見開きやタチキリの効果を使って緩急をつけ、見せ場の大ゴマを多用し、ワク線もタテヨコ斜めに自由自在に引く。そういう大胆なコマの連なりが現代の漫画ならではのスピード感やテンポを生み出してきた。だがFは、『ドラえもん』本編の初期の頃(70年代)ならまだしも、90年代のスペクタクル要素が強い「大長編」シリーズでも、基本的にはこのクラシカルなコマ割りにこだわっている。それはなぜかといえば、やはり漫画を読み慣れていない小さな読者にもわかりやすいレイアウトにするためだったとしか思えない。
だから当然、そのコマの中に描かれている絵も、アップや引きといった映画的なモンタージュを駆使したものではなく、演劇的な、つまり定点カメラで舞台上の役者の全身を撮ったような、誰がどういう場所で何をやっているのかがひと目でわかる平坦な構図のものが基本になっている。これは、映画的手法を漫画の世界で発展させたといわれる(注・異論もある)手塚治虫の直系といってもいいFの作風としては、やや違和感がないでもない(ちなみに「相棒」の藤子不二雄(A)のほうは明らかに手塚の映画的手法を受け継いでいる)。