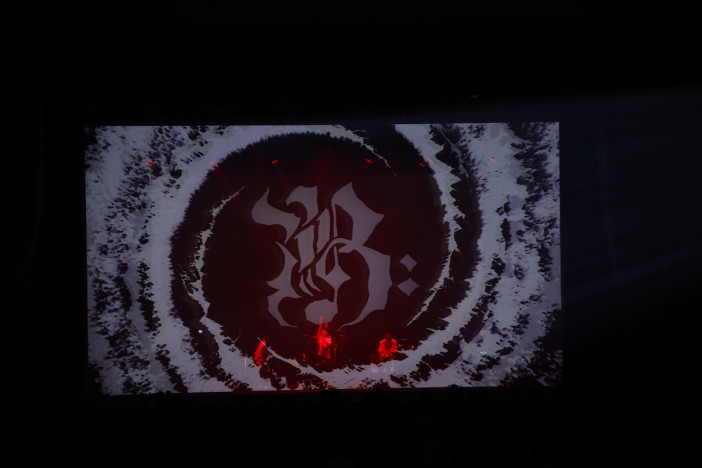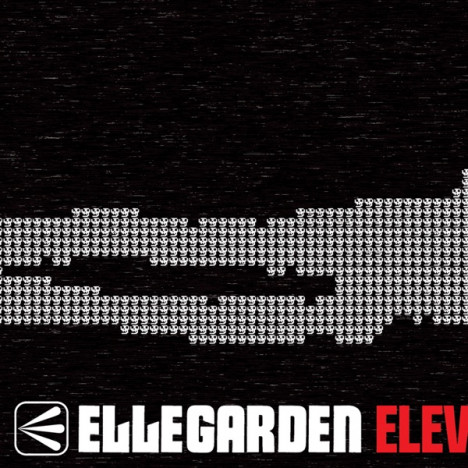BRAHMANのフルマラソンは終わらない 全76曲4時間ぶっ通しライブ『六梵全書』完遂、30周年間近のバンド力を見た

理想は、短距離走のスピードで、フルマラソンを走り切ること。
1998年、1stアルバム『A MAN OF THE WORLD』をリリースしたインディーズ時代、彼らがよく口にしていた言葉だ。まさにその結実だとは言わないが、最初に聞いた時、実にBRAHMANらしいと思ったのは事実である。
当時から26年、結成の1995年から数えれば29年となる2024年現在。ほぼ5年に一枚のペースで作ってきたアルバムの、6作品全72曲を4時間でぶっ放す。『BRAHMAN 六梵全書 Six full albums of all songs』と冠されたこのライブは、来たるべきBRAHMAN30周年の到来を告げる記念碑的な一夜となるものだ。ただ、それがどんな内容になるかはまったく予想がつかなかった。『六梵全書』というタイトルよりもインパクトの強い「72曲。4時間。」の惹句に武者震いするばかり。そんなファンが大半だったのではないか。
まず始まるのは目下の最新アルバム『梵唄』から一曲目「真善美」。〈一度きりの意味をお前が問う番だ〉と歌ったあとにTOSHI-LOW(Vo)が語り出す。いわく、「今日やるのは72曲って塊じゃねえ。一曲一曲の大事な物語だ。一度きりの意味を俺たちが問う。30年分のBRAHMAN始めます」一一。
そこからはアルバム『梵唄』どおりのセットリスト。以降はMCも何もない、ノンストップの11曲35分だ。シンプルな舞台には4人がいるだけで、「今夜」で細美武士が出てくることもなければ「守破離」でKO(SLANG)が登場するわけでもない。このままアルバムごとに時間を遡っていくのだろうか? それはそれで面白いが、まだ線の細かった初期を知っている身からすると、綺麗な終着地点は描きづらい。おっ立てた中指をピースサインに変える「不倶戴天」の包容力、「満月の夕」における観客との一体感などは、今やひとつのエンタメとして仕上がりすぎている。優しき母性と力強い父性を併せ持った人間的総合力ができすぎているのだ。さぁ、ここからどう過去に繋げるのか。まだまだ、まったくわからないままである。

「満月の夕」のあたたかい余韻を断ち切るのは、登場の際にも流れたブルガリア民謡のSE。え? また? という感じで響く二度目のそれは、はっきりと仕切り直しを、もしくは時空間の巻き戻しを意味していた。新たに始まるのは5thアルバム『超克』から「初期衝動」。これまたアルバム通りの全13曲。東日本大震災以降に覚醒した、闘うBRAHMANの登場である。
SEひとつでそんなにムードが変わるかと思われそうだが、実際は楽曲自体が当時の空気なのだ。KOHKI(Gt)、MAKOTO(Ba)、RONZI(Dr)が揃って怒号を放つ曲が、日本語でまっすぐ現実を描写する曲が一気に増えた時期。ほぼ5年に一枚、ずいぶんスローな制作ペースだから、そのぶん曲は練り込まれ、密度は濃くなり、共にひとつの空間にいた4人の呼吸が重要になってくる。怒涛のハードコア楽曲なのに確かな一体感を感じる「警醒」や、たった数分間で残された命を描き切る「霹靂」の凄まじい熱量など、すべてがドラマティックでエモーショナル。ただし、後方スクリーンに大写しになるのがTOSHI-LOWの眼球だったり両腕だったりするように、感情を増幅させる歌の土台には確かな肉体があるのだった。懸命に生きる力、その気力を宿す肉体がしっかりと認知された時期である。



そして三度目のSE。もう流れがわかってきたが、続いては2008年発表、4thアルバム『ANTINOMY』全曲再現となる。「THE ONLY WAY」に象徴される力強さを放ちながら、「STAND ALOOF」や「SILENT DAY」など、爆発力に頼らない楽曲で心の機微を表そうとしていた頃だ。気づけば前2作のタームには目立たなかったマイクスタンドがステージ中央に置かれている。現在のマイクが肉体の延長だとすれば、この時期、細長い棒を振りかざしたり肘掛け台のように使っていたTOSHI-LOWは、マイクスタンドを自分と観客を隔てる境界として使っていたように思う。支えとして寄りかかりたいが、時には容赦なくへし折りたくなる。どっちなのかと思うが、だからこそ『ANTINOMY』=二律背反だった。正直、演奏を聴くのが久々すぎて新曲みたいに響く曲が一番多かったのもこのタームであった。
強さと儚さ、ストロングとアンニュイの間で揺れ動いていた彼らも、歴史の流れで見れば必然だったのだろう。メロディックやミクスチャー勢が連帯して盛り上がった90’sパンクは、日本では主に『AIR JAM』カルチャーが牽引したが、その花火も終わり、仲間たちが次々と活動休止していく時期だ。〈辿り着いた赤/ただ燃やして消えた〉と歌い終えた「逆光」の後に続く、誰にも立ち入れないほどの静寂が、当時の奇妙な静けさとリンクするようだった。

四度目のSE。折り返しとなるこのタームからは、3rdアルバム『THE MIDDLE WAY』が曲順通りに再現されていく……のかと思いきや。一曲目「THE VOID」の直後には2ndアルバム『A FORLORN HOPE』から「BASIS」。「其処に立つ!」とステージに右手を振り下ろしたTOSHI-LOWの嬉しそうな顔が忘れられない。ほら、台本通りに進むと思うなよ。自分で敷いたレールなら自分の手でぶっ壊せるだろ。メンバーの表情から一気に硬さが抜けていく後半戦は、90年代後期から2000年初頭の曲がノンストップで披露される。90’sパンクブームの中、仲間たちと破竹の勢いでシーンを駆け上がっていった、まさに青春期のBRAHMAN登場だ。誰がどうやって持ち込んだのか、アリーナ通路にはバンドの名前が踊る大漁旗までが翻っている。わはは。もう完全な祭りであるが、当時の十倍くらいは丁寧になっているTOSHI-LOWの歌唱、一曲ずつ細やかな仕事ぶりが目につくKOHKIのギタープレイも忘れずに記しておきたい。