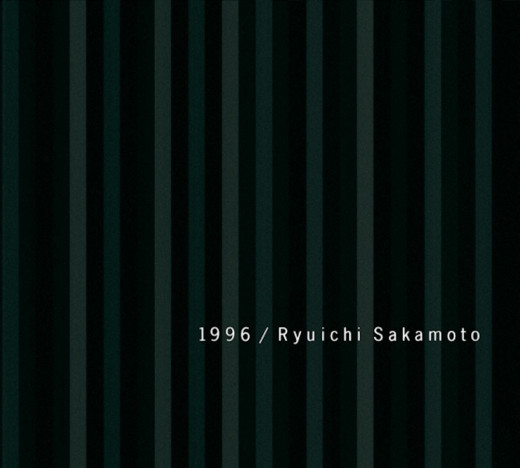坂本龍一、“最後のプレイリスト”に選曲されたデヴィッド・シルヴィアンとの特別な絆 運命的な出会いと長年の交流を辿る
今年3月28日に71歳で亡くなった坂本龍一が、自らの葬儀で流すためとして個人的に制作していたプレイリスト「funeral」をマネジメントチームが公開した。昨年6月から少しずつ曲が集められ、コラボレーターとしておなじみのアルヴァ・ノトに始まり、坂本が敬愛するJ.S.バッハやクロード・ドビュッシーに、エリック・サティ、モーリス・ラヴェル、そしてエンニオ・モリコーネ、ニーノ・ロータらによる映画音楽など、坂本が愛した33曲が並んでいる。音楽的ルーツを垣間見せるとともに、心落ち着くあたたかな静けさに包まれる選曲は、音楽家・坂本龍一の歩みを示しているようだった。

そのなかで唯一“歌モノ”な楽曲がある。坂本の長年の友人である元JAPAN、デヴィッド・シルヴィアンの楽曲「Orpheus」だ。クラシックの声楽やシャンソンなど歌唱が含まれる楽曲はあるが、ここまではっきりと、しかも字詰まりに歌われた楽曲はこのほかにない。坂本は前衛的な音楽を極めるなか、たびたび「歌モノは苦手」と発言しており、たとえ自身が高く評価するアーティストの作品であっても、歌が入るものには厳しい反応を見せた。そんな彼が「最後のプレイリスト」に自ら歌モノを選んだというのは驚きだ。
「葬式用プレイリスト」を密かに用意しているという人は少なくない。そこでは自分の好きな楽曲はもちろん、思い出深いものやメッセージが込められたもの、見送る側も見送られる側も安らかな気持ちなれるようなものなどを、思い思いに選ぶことだろう。33曲という限られた楽曲数のなかで、坂本はどんな想いでシルヴィアンの「Orpheus」を選んだのだろうか。そんな答えの見つからない想いを探してみたい。そこで今回、坂本龍一とデヴィッド・シルヴィアンという二人の音楽家の軌跡を辿り、彼らの間に芽生えた深い絆に触れてみたいと思う。
初対面から意気投合、二人の運命的な出会い

坂本とシルヴィアンの出会いは、JAPAN活動期まで遡る。JAPANは、1970年代から80年代にかけて活躍したイギリスのニューウェイヴバンドで、シルヴィアンと実弟スティーヴ・ジャンセン、そしてシルヴィアンの親友であったミック・カーンを中心に結成、1978年4月にデビューアルバム『Adolescent Sex / 果てしなき反抗』を発表した。彼らのグラムロックの遺伝子を受け継いだバンドスタイルと奇抜なルックスは、当時パンクロックやニューウェイヴが盛り上がっていた本国では受け入れられなかったものの、日本ではティーンエイジャーを中心にアイドル的人気を獲得し、デビュー段階でファンクラブの会員数が3万人を記録、初来日でいきなり日本武道館公演を開催するまでとなった。その後、ジョルジオ・モロダーとの共作シングル『Life in Tokyo』でシンセポップへ路線変更し、1979年にリリースしたアルバム『Quiet Life』では世界的な評価を高め、ゴールドディスクを獲得した。
『Quiet Life』のリリースツアーのためJAPANが再来日した1980年3月、『ミュージック・ライフ』誌のために坂本がシルヴィアンにインタビューを行うことになる。ここで二人は初対面し、すぐに意気投合。インタビュー後の坂本は「5分で昔からの友達みたいになった。デヴィッドは繊細で、忍耐強く、深く考え、そして強い」とコメントしている(※1)。この日をきっかけに、二人の音楽家は長年の友人として、さまざまなコラボレーション作品を世に放つこととなった。
坂本とシルヴィアンの記念すべき初コラボレーション作品は、同年11月にリリースしたJAPANのアルバム『Gentlemen Take Polaroids / 孤独な影』に収録された「Taking Islands in Africa」だった。制作当時、YMO(Yellow Magic Orchestra)やKraftwerkらの影響から音楽性がエレクトロミュージックへ傾倒していたシルヴィアンは、同じレコーディングスタジオで『B-2 Unit』を録音していた坂本と手を組み、坂本が作曲と演奏を、シルヴィアンが作詞を担当してこの楽曲を制作した(しかしこの曲を半ば強引にアルバムに入れたことでバンド内の亀裂を深めることとなった)。
JAPAN最後のオリジナルアルバムとなる『Tin Drum / 錻力の太鼓』(1981年)発表後、解散を迎える前にソロ活動をスタートさせたシルヴィアンは、再び坂本を迎え、シングル『Bamboo Houses/Bamboo Music』を1982年に発表。これが2回目のコラボレーションとなる。
代表曲「Forbidden Colours」が拓いた未来
JAPANが一時的に再結成し、YMOが散開した1983年、坂本とシルヴィアンのコラボレーションにおいて欠かせない楽曲「Forbidden Colours / 禁じられた色彩」が誕生した。映画『戦場のメリークリスマス』とメインテーマである「Merry Christmas, Mr. Lawrence」に感銘を受けたシルヴィアンは、歌詞とメロディを作り、歌を乗せ、三島由紀夫の小説『禁色』からタイトルを引用した。デヴィッド・ボウイ演じる俘虜の英国陸軍 ジャック・セリアズの心情を描いたと思われる葛藤と愛を綴る切ない歌詞と、憂いに満ちたシルヴィアンの歌声が、坂本が生み出す美しい旋律とともに豊かに響く。後世に残る至高のコラボレーションは、『戦場のメリークリスマス』のサウンドトラック・アルバムに収録されたのち、シングルとしてもリリースされ、全英シングルチャート16位を記録した。
「Forbidden Colours / 禁じられた色彩」はシルヴィアンの創作意欲を刺激し、初のソロアルバム『Brilliant Trees』(1984年)の制作に取りかかり、坂本はピアノ/シンセサイザーで一部楽曲に参加した。アート性やスピリチュアルな思考を突き詰めた前衛的な作品づくりを進めるなか、初期の名作と名高い『Secrets of the Beehive』(1987年)では、ピアノ、オルガン、ストリングスアレンジなど広範囲を坂本が担当し、共作的作品となった。以降も、1992年には後にシルヴィアンの妻となるイングリッド・シャヴェイズが参加する『体内回帰 / tainaikaiki II』を共同名義で発表。さらには、弟スティーヴ・ジャンセンと組んだ3人組のバンド Nine Horsesの1stアルバム『Snow Borne Sorrow』(2005年)にも坂本は参加している。
ロバート・フリップやホルガー・シューカイなど、今日に至るまでさまざまな音楽家とコラボレーションしてきたシルヴィアンだが、そのなかでも坂本は、シルヴィアンにとってあらゆるインスピレーションの源となり、数多の新しい世界を見せてくれた存在だったことだろう。たとえば、『Gentlemen Take Polaroids / 孤独な影』でエレクトロミュージックに傾倒した理由の一つにYMOの影響がある。そのYMOを知った当初、一際耳を引いたのは坂本作の「東風」で、クレジットから坂本の名前を知ったと証言している(※2)。
そして初のコラボレーションを経て制作された『Tin Drum / 錻力の太鼓』では、ドイツの現代音楽家 カールハインツ・シュトックハウゼン由来のエレクトロニクスやアンビエント、東洋などの影響を大きく受けたというシルヴィアンの音楽的趣向が顕著に表れている。この作品から窺える商業的音楽に寄り添わないアバンギャルドな姿勢と、西洋と東洋をかけ合わせた音楽性は、これまでYMOが、坂本龍一が示してきたものでもある。二人の間にもともと共鳴するものがあったことに違いはないが、坂本が与えた影響は大きいはずだ。シルヴィアンの半生を追う話題になると、必ずと言っていいほど坂本の名前が挙がることがその証拠でもある。