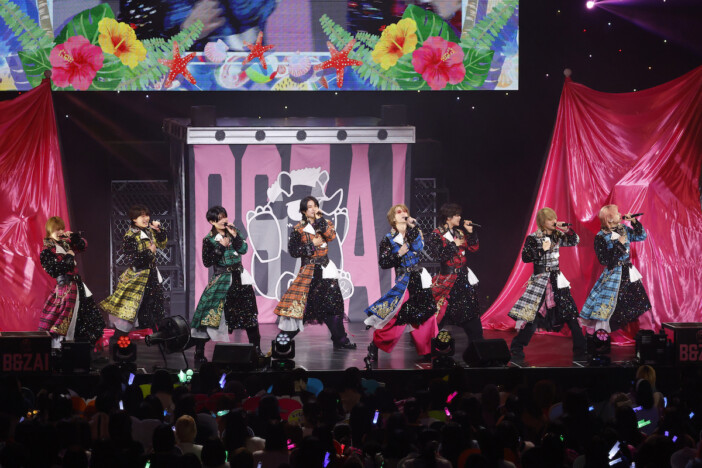King Gnu、美しいバラードの裏に宿る巧みな実験精神 「カメレオン」は多面的な表情を持つ新たな代表曲に

月9ドラマ『ミステリと言う勿れ』(フジテレビ系)の主題歌として起用され、毎週のドラマに色を添えているKing Gnuの「カメレオン」。ドラマそのものの面白さ、楽曲の素晴らしさ、そしてその両者が合わさることによって生まれる相乗効果。King Gnuが何かのテーマ曲を生み出すときはいつもそうだが、今回も実に幸福なコラボレーションとなっていることに異論はないだろう。
原作に書かれた言葉たちをリスペクトしながら、その物語世界に時折新たな角度から光を当てることで、原作ではそこまで掘り下げてはいないキャラクターたちの感情にも踏み込んでいくドラマ版『ミステリと言う勿れ』のスタンス。個人的にはとても面白いと感じている。見る角度によって、あるいは劇中で語られる言葉一つひとつの背景を想像することによって、幾通りにも見え方を変えていく『ミステリと言う勿れ』という作品に対して、ドラマがまたひとつの新しい「見方」を提示しているように思うからだ。
例えば、主人公の久能整と犬堂我路の間にあるシンパシーとは何なのか、整と風呂光聖子の間にはどんな感情があるのか、整とライカはなぜ接近せざるをえなかったのか……原作ではおそらくあえて踏み込まれない登場人物の内面が、俳優が演じることによってひとつの解釈として表れてくる。もとより多面的である『ミステリと言う勿れ』という作品を、ドラマは大胆に読み解き、さらなる多面性を描き出していくのである(余談だが、ライカを演じる門脇麦の演技によって、原作以上のインパクトを生み出した第9話のラストシーンはその好例だ)。
そんなドラマに「カメレオン」は非常にハマっている。なぜなら「カメレオン」もまた、極めて多面的な楽曲だからである。多面的な物語と多面的な楽曲の相乗効果が、画面の中で毎週起きている、それがこの「ハマりっぷり」の正体である。そして、そこにこの曲の新しさ、King Gnuの新曲としての手応えがある。まさに〈何度でも/何度でも〉好きな色で塗り替えていくんだ、というメッセージが楽曲を通して体現されていく。「カメレオン」はそんな楽曲なのだ。
「カメレオン」は、一面では「King Gnuの最新バラード」として捉えることができる。確かに、井口理の歌う美しいメロディが軸となって情景を紡いでいくという点、曲のテンポ感、サビでのドラマティックな展開などは、それこそ「三文小説」や「逆夢」あたりにも比することのできるバラードとしての強固な構造を生み出している。だが、単純に「いいバラードですね」という感想で終わらせてしまったのでは掬い上げられない何かが、この曲には間違いなくある。それは例えば、Aメロからサビに入る瞬間に何かが断絶するようなアレンジだったり、ピアノのコードの裏で鳴っているノイズのような、それでいて水面の煌めきのような電子音であったり、最初のAメロが再び現れて唐突に終わる、という楽曲の構成といった部分だ。美しいメロディを美しく歌い上げる、というバラードの基本形を、楽曲のデザインが積極的に崩しにいっているという印象を受ける。
millennium paradeとは違い、King Gnuにおける常田大希の作曲のマナーは、どちらかといえば明快なものだったように思う。つまり「BOY」のようにアグレッシブな曲はアグレッシブに、「逆夢」のようにメロウな曲はメロウに、という指針のもとに作られていることが多かった。それはKing Gnuというバンドのコンセプトが、そもそもJ-POPのシーンにアプローチして勝負するというものだったからかもしれない。唯一例外だったといえるのが、前身バンド Srv.Vinciの楽曲を原型にしてリメイクした「泡」だろうが、「カメレオン」はその立ち位置として、King Gnuの名バラードの系譜に連なる楽曲というよりも、むしろ「泡」に通じる実験精神と内面性をもった楽曲だという気がする。
「泡」はその精神性がよりダイレクトに表れた楽曲だが、この「カメレオン」は違う。それをバラードというスタイルに美しく昇華しているところに、King Gnuの楽曲としての新しさを感じるのだ。シンプルで美しいバラードという型の裏側で施された緻密なサウンドプロダクションは、この曲がバンドの新たなフェーズの幕開けを告げていることを証明しているのかもしれない。