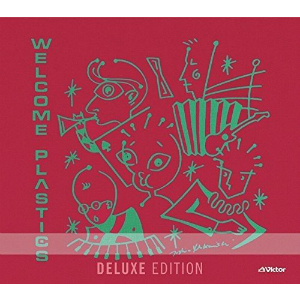荏開津広『東京/ブロンクス/HIPHOP』第6回
荏開津広『東京/ブロンクス/HIPHOP』第6回:はっぴいえんど、闘争から辿るヒップホップ史
「1970年代の頭というのは、政治の季節、70年代安保の時代でございます。あとは音楽の季節。1960年代から70年代というのは、文化の最先端が音楽でありました。それはレコードという1930年代ぐらいから作られはじめた音楽を記録する手段、それと録音技術のテクノロジーが1960年代から飛躍的に発展しまして、それまでは演奏の記録といいますか、そうしたものだったのが、レコードのなかの音世界というか、そういうものを探求する技術がものすごく発達しまして、音楽が、いろいろな絵画、演劇、文学といった文化がありますが、音楽がなによりも最先端になった時代です。そこに1970年代政治の季節、70年代安保という騒乱の時代がくっつきまして、たくさんのドロップアウトが生まれまして、そのドロップアウトした人たちが、ほとんど音楽の世界へ入り込んできたという、そのおかげで、それまでの日本の音楽にはなかったムーヴメントというのが生まれました。」(山下達郎、2015年、NHK-FM)
アメリカの空前の規模のベトナム反戦運動と公民権運動はいうまでもない。
1968年、パリ・ナンテール大学での学生のストライキを始まりとし、その2週間のうちに200万人の学生と労働者のストライキとなって、ミニスカートとレザー・ブーツ、クルーネックのセーターとコーデュロイのパンツがプロテストのメッセージを掲げる姿で一変したパリ市内の風景は、5月30日に消え去った。
こうした状況は日本国内のそれと織り交ぜられ見ることができる。1968年6月1日から東京大学医学部全学共闘の学生約100人が安田講堂占拠にふみきった。この占拠と篭城は翌年1月19日まで続き、入学試験は中止。この間に、東京お茶の水周辺では日本大学、中央大学、明治大学の学生を中心に2000人規模の“神田カルチエ・ラタン闘争”と呼ばれる街頭バリケード騒動も起こったし、当時、国公立、私立大学の大半がなんらかの形で“闘争”状態になったといわれる。
大学生だけではなく、1968年には小規模だが、高校生だけのデモも行われるようになった。3月には100人の高校生が王子で機動達とぶつかり3人の逮捕者を出した。4月26日には反戦高恊(反戦高校生協議会)というグループを中心とする200人の高校生が東京・青山の公園に茶色のヘルメットをかぶって集まった。彼らは受験勉強の合い間に、マルクスや毛沢東を読み目覚め、グループを結成したという。(※註5)
「高校生だった自分が初めて思想というものに強烈に出くわしたという感じだったの(中略)。だって、普通に学校から帰宅しようとすると電車が止まったりするわけじゃない。そうすると、「何で?」ってことになるでしょ。つまり「おまえはこの状況をどう思うんだ?」っていうことを問いかけられているわけ。で、そういった問題提起は恒常的にいろいろなところで行われていたわけ」(※註6)
のちに、新進の文学者だった、いとうせいこうと組んで前衛としての日本語ラップ作品『MESS/AGE』をリリースしたヤン富田はこう回想する。
はっぴいえんど、に戻る。

1970年ではなく、そのあとにやってきて作品として『ゆでめん(はっぴいえんど)』や『風街ろまん』といったアルバムを、日本のロック&フォークは“ここから始まった”、もしくは日本語でロックを歌うことを考えたときに“最重要”と落着させることが、どのように彼らと私たちの言語/音の空間を再配向づけたか。
そのとき、私たちが見るべき異なる風景は、1960年代のサパー・クラブ/ゴーゴー喫茶から、1970年代に加速し1977年の映画『サタデー・ナイト・フィーバー』の日本公開とともに爆発したディスコ/クラブのネオンサインとフラッシュの明滅するフロアであり、また、北アメリカとヨーロッパをのぞくと世界的にも早い段階に音楽フェスティバルが行われた日本各所である。そのうちのひとつは、コメンタリーのクリス・マルケルが“境界を取り去った映画”と呼ぶ、ヤン・ル・マッソンの監督した例外的に美しい『鹿島パラダイス』に映し出された土地、三里塚(千葉県成田市)だ。
着目したいのは、1966年から現在に至る成田空港建設反対の“闘争”についてではない。1971年に行われ、高柳昌行ニュー・ディレクションや高木元輝トリオといったフリー・ジャズ・ミュージシャンに、ブルース・クリエイション、ロスト・アラーフ、そして頭脳警察が出演したフェスティバル『日本幻野祭』である。
「事務所へ三里塚青年行動隊の有志がやってきた、成田空港建設阻止の闘争に明け暮れ、みんな祭りを忘れている、そこで祭りをやりたいのです、ぜひ頭脳警察に出てもらいたいという内容だった/ちょっと待て、祭りをやりたいのなら盆踊りをやりなさいよ、ロックコンサートをやりたいなどというのは学生達のマスターベーションにしかすぎないでしょ!と、思わず自分はそう返してしまった」(PANTA、Facebookの投稿より)
頭脳警察は当初、フロントマンのPANTAにパーカッション/ドラムスのTOSHI、ギターの左右栄一、ベースの栗野仁、エリック、ジミーという男女混成6人のバンドだったというが、『幻野祭』に出演した際には、既にPANTAとTOSHIの2人で、パフォーマンスは歌詞の政治性により発売中止になった1stアルバム『頭脳警察1』からの「世界革命戦争宣言」、「銃をとれ」などアンコールを含め4曲だった。
「世界革命戦争宣言」は、「君たちにベトナムの仲間を好き勝手に殺す権利があるのなら」、「ブラック・パンサーの同志を殺害しゲットーを戦車で押しつぶす権利があるのなら」、「君たち(註:ブルジョワジー)を世界革命戦争の場に叩き込んで一掃する」と朗読する曲だ。この詩の世界は、PANTAが同時代のロックやソウルはもちろん、フランスのシャンソンなど幅広く海外の音楽や文学に興味を持っていたことと関係すると思われる。
頭脳警察のパフォーマンスについてはこう語られている。
「日本人ってこんなに踊りが好きなのか!って驚いたくらい、当時の頭脳警察のコンサートでは、客がだんだん前から立ち上がっていくわけ。いまでいうトランスなんだろうね、あれ。それがもう好き勝手な踊りで、君らはいったい何民族なんだっていう(笑)」(※註7)
『幻野祭』で楽器はパーカッションとギターだけの頭脳警察を見ていた、もしくはダンスしていた客の1人に、その年に東京に住み始めた大学生がいた。その大学に8年間在籍していたのち中退し、同じ年にバンド、のちのJAGATARAを始める江戸アケミだ。
その江戸アケミに大きな刺激を受けたとのちに語る近田春夫は、慶應高校在学中から幾つかのバンドでプレイしたのち、1970年代の半ばまでには内田裕也のバンドでもキーボード・プレイヤーとして参加していた。
彼の初期のキャリアで注意するべきは、彼とそのバンド、ハルヲフォンが長い期間ディスコで演奏することを選んだその感受性の向きと関連する。「かっこいい人がおおかったからね。女の人なんかとくに。やっぱり見た目でかっこいいと思える人が多い場所で鳴ってる音の方が、自分にとっては魅力的に思えるんだよね。フォークの人とかって身体の動きがないんだよね」(※註8)、「俺はね、音楽ってディスコで聴くのがいちばんカッコいいって未だに思ってるんだ。日本人がディスコで成功した曲って1曲もないんだよ。ディスコを制覇したいっていうのが、夢なんじゃないかな」、「踊らせることが仕事だし。自分のこと観てるより、お客さんが自分の音で踊ってるのを観てる方が僕の性に合うんだよね。“スターのここを観てくれ”みたいなことより」(※註9)
近田春夫はその頃から、一段高いステージ上の演じ手として音楽を一方向に流すことだけではなく、その音楽を生き生きとさせる場所、それ自体に関心があったように思える。
彼とハルヲフォンは、長いディスコでの演奏活動やライブ・パフォーマンスを通して、ロックとは違う構造を持った音楽の存在にも気がついていた。
ハルヲフォンによる1975年、郡山の第2回『ワンステップフェスティバル』のライブ・パフォーマンスのフッテージは、アフロ・アメリカンと日本人の間に生まれたキャロン・ホーガンをメンバーとして「FUNKYダッコNo.1」とアレサ・フランクリンの「Rock Steady」を続けて演奏する素晴らしいものだ。おそらくほとんどの観衆は知らないだろう「FUNKYダッコNo.1」が始まったときには、おとなしく座ってステージを見ていた彼らの多くは、2分も経たないうちに立ち上がり体を動かし始める。それに気がついたメンバーが「Clap Your Hands!」、ホーガンが「C’mon, dance to the music!」と煽動していき2曲目の「Rock Steady」になだれこんでいく。今度は日本語で「踊ってよ、みんな、踊ってよ」との声がビートに乗り、観客は熱狂していく。ハルヲフォンのドラマー・恒田義見のヘヴィなプレイは、明らかにブレイクビーツを予見しうるものだ。「Rock Steady」にしても「FUNKYダッコNo.1」にしても、劇的に始まる旅が調和して終わるという物語めいた曲に酔うのではなく、リズムの反復のなかで生まれていく持続する音世界で、バンドと観客が相互に掻き立てられてダンスに向う、その様子は暴動に向っているかのようにさえ見える。
■荏開津広
執筆/DJ/京都精華大学、立教大学非常勤講師。ポンピドゥー・センター発の映像祭オールピスト京都プログラム・ディレクター。90年代初頭より東京の黎明期のクラブ、P.PICASSO、ZOO、MIX、YELLOW、INKSTICKなどでレジデントDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域において国内外で活動。共訳書に『サウンド・アート』(フィルムアート社、2010年)。
===
註1:大川俊昭・高護共編『定本はっぴいえんど』(SFC音楽出版、1986年)
註2:金坂健二著『幻覚の共和国』(晶文社、1971年)で触れられている、ドラッグとロックで作られた新しい共同体。
註3:特集「ROCK IS… 原始性への回帰 日向あき子」『美術手帳』(美術出版社、1970年10月号)
註4:渋谷陽一著『ロッキング・オン増刊 メディアとしてのロックンロール』(一進社、1979年)
註5:『安保と全学連 続・スチューデント・パワー』(毎日新聞社、1969年)
註6:ヤン富田著『フォーエバー・ヤン―ミュージック・ミーム〈1〉』(アスペクト、2006年)
註7:ダディ竹千代、難波博之、井上貴子他『証言! 日本のロック70’s ニューロック/ハードロック/プログレッシヴロック編』(アルテスパブリッシング、2009年)
註8:『シティロード』1994年1月号(エコー企画、1994年)
註9:松永良平著『20世紀グレーテスト・ヒッツ』(音楽出版社、2007年)
『東京/ブロンクス/HIPHOP』連載
・第1回:ロックの終わりとラップの始まり
・第2回:Bボーイとポスト・パンクの接点
・第3回:YMOとアフリカ・バンバータの共振
・第4回:NYと東京、ストリートカルチャーの共通点
・第5回:“踊り場”がダンス・ミュージックに与えた影響
・第6回:はっぴいえんど、闘争から辿るヒップホップ史