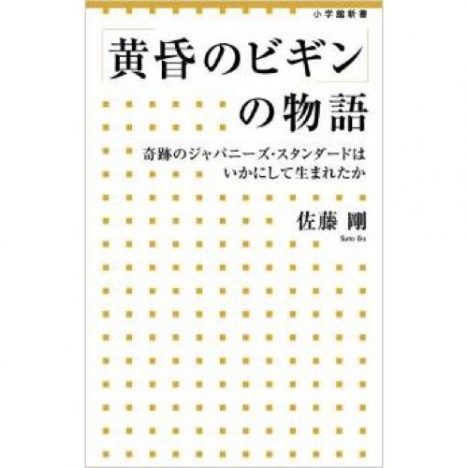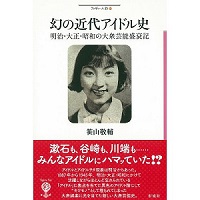栗原裕一郎の音楽本レビュー 第5回:『親のための新しい音楽の教科書』
『親のための新しい音楽の教科書』は教科書にふさわしいか 先生、西洋音楽ってイケナイものなの?
西洋音楽=資本主義!?
『親のための新しい音楽の教科書』の議論も、大体カルスタの成果に依ったものだ。西洋近代音楽中心主義批判、文化帝国主義批判、上位文化による下位文化の抑圧批判、イデオロギー永続装置である学校教育批判、マイノリティ擁護などなどの定型化した感のある議論を、日本の音楽教育と、著者の専門である音楽療法を題材に平易に説き直したものが本書であるといっていいだろう。
カルスタというのは、文化の価値決定に潜む政治性を暴き出し、価値ヒエラルキーの解体を目論むことを中心原理とするといえると思うが、本書の主張もそこにきれいに収まっている。
ひとつ例を見てみよう。
「楽しい音楽」批判の中身は、実は機能和声批判である。和声進行の技法は19世紀のロマン派のあたりで今日に通じるかたちがほぼ出来上がり、同時に感情の表現も担うことができるようになった。機能和声の情動に働きかける効果は産業と結びつき洗練され、「現代ではさらに、あるコード進行が「胸キュン」などと呼ばれ、感情を操作するテクノロジーのようなものにまでなっています」。
社会的ドグマになってしまった「楽しい音楽」はその最たるものだとされている。機能和声により喚起される感情、嬉しいとか楽しいとか悲しいというのは、特定の文化の約束事として受け取り方が決まっているものに過ぎず、約束事を共有しない他文化の人が同じように聴くとは限らない。にもかかわらず「音楽は万国共通」と考えてしまいがちなのは、音楽のグローバリゼーションおよび西洋中心主義によって引き起こされた錯覚なのである。とまあ、そういった趣旨だ。
読んでいて、実は議論そのものよりも、機能和声が感情と結び付いたこと自体を悪玉視しているような論調が気になった。別の本『音楽療法を考える』(音楽之友社、2006年)を読んだら、若尾は機能和声についてこんなことを書いていた。
和声進行の基本運動「期待と解決」について、ドゥルーズの哲学を援用した「欠乏の充足という原理」という見方があることを紹介し、それをマックス・ウェーバーに接続してこういうのである。
「この原理は、よくみるとマックス・ウェーバーが指摘した資本主義におけるプロテスタンティズムの意義を思い起こさせる。音楽の欲動やエネルギーを経済的に管理し、抜け目なく投資しながらクライマックスへと向かう、あの機能和声の音の流れは、資本主義的な欲動のあり方をベースになりたっていると考えられるのだ」
いかにも危うい議論だ。若尾はこれを「西洋音楽に潜んでいたイデオロギー」とまで言い切るのだが、つまり著者の思想においては「西洋音楽と資本主義は同じイデオロギーの上に立つ本質的に同じシステム」なのである。
カルスタはマルクス主義の批判的展開という面を持っており、やってる人は大抵左翼なので、資本主義やグローバリゼーションには否定的である。文化相対主義を掲げながらこの『親のための~』に、西洋音楽を根本的に否定したいという意志が強く滲んでいるのが不思議だったのだが、西洋音楽=資本主義と見なしているらしいことがわかってようやく合点がいった。
カルスタ的相対主義、構築主義に対する批判的潮流として大きいのは、『音楽のカルチュラル・スタディーズ』でも批判的に言及されているが、認知科学だろう。そのイデオローグで進化心理学のスティーヴン・ピンカーは『心の仕組み』(NHKブックス、2003年)で、音楽が喚起する情動について「普遍的ではないが、任意でもない」といっている。音楽イディオムにある程度慣れ親しんでいる必要はあるが、情動と結び付けるために「楽しい気分や憂うつな気分のときに聴いたりして、パブロフ風の条件づけをする必要はない」のだと。
フィリップ・ボール『音楽の科学』(河出書房新社、2011年)では、西洋音楽にまったく触れたことのない民族に西洋音楽を聴かせたところ、偶然より明らかに高い確率で、その音楽が喜びと悲しみのどちらを表しているか言い当てたという実験が紹介されている。
ただし、フィリップの紹介にはたくさんの留保が付いている。音楽と情動というのは社会的に構築された側面を多分に持つ問題であることも含んでいる。それだけ一筋縄ではいかない問題だということだ。対して若尾の議論は、機能和声の喚起する情動はほぼ完全に社会的構築物であるという前提で進んでいる。なぜそう言い切れるのか、単純にそう言い切ってしまっていい問題なのだろうか。
理想的な音楽教育は「何もしないこと」
この本で若尾は、文化相対主義的な立場を取っているはずなのだが、どうにも西洋音楽の否定ないし排除を目指しているようにしか見えないのだ。
若尾のいう「もうすこし健全な音楽のあり方」とは、したがって、西洋音楽の支配から脱した音楽ということになるだろう。12音技法やセリエリズムのような音楽は、支配からの逸脱ではなくて、西洋音楽的イデオロギーである「むずかしい音楽」の内部における尖鋭化だから失格である。
若尾が称揚するのは、「生の芸術」を提唱したデュビュッフェが趣味で自分勝手にやっていたアウトサイダーアートのような音楽であり、パンクやオルタナティヴ・ロックである。特にパンクやオルタナは、ヘタクソでも構わないという価値観の転倒を広め、完全であることを価値とする西洋音楽中心主義を転覆した点で、音楽史に特記されるほど重要であると評価している。
ポピュラー音楽を取り入れるなどだいぶ相対化されたとはいっても、根本的には西洋近代音楽中心主義にいまだ留まっている音楽教育が、こういった基準からいえばまったく無価値としてしりぞけられるのは道理で、事実そう書いている。
バンドなど学校外で自主的に行われる「インフォーマル・ラーニング(非正規の学習)」こそリアルで本質的な学びであると若尾は評価する。親が子に施せる理想的な音楽教育とは、とどのつまり、何もしないこと、子供の勝手にさせておくこととなるわけだ。
若尾はそもそも学校や教育というもの自体、近代の「発明」に過ぎないとして、アリエスの『〈子供〉の誕生』を引き合いに出している。「子供」という概念は近代になって発明されたものであり、それ以前は「子供」はおらず「小さな大人」がいただけだと説き大きな衝撃を走らせた、60年発表の本だ。アリエス説には異論や批判が出ているが(ポロク『忘れられた子どもたち』、森洋子『子供とカップルの美術史』など)、若尾は故意か過失かそういったものをネグレクトして、あたかも確定した史実であるかのように書くのである。