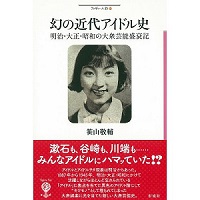栗原裕一郎の音楽本レビュー 第2回:『「黄昏のビギン」の物語』
「黄昏のビギン」はいかにしてスタンダード・ソングとなったか 名プロデューサーの快著を読む
著者・佐藤剛の狙いと、その経歴
中村八大は1992年に没した。
中村の死から数ヶ月後、ちあきなおみは、夫・郷鍈治が死去したのを境に表舞台から姿を消した。以来今日までもう20年以上も沈黙を続けている。
佐藤の推理は結局のところ、説得力のある仮設の域に留まるだろう。
しかしそれでもいいのだ。佐藤の目論見は、「黄昏のビギン」という希有な楽曲にまつわる事実をクリアにすることだけにあるわけではないし、当事者の証言があれば必ず真実に近づくというものでもない。
歌というものがいかに不可思議なプロセスで生み出されるものであるか。一度生まれるや、いかに歌い継がれるべくして歌い継がれていくものであるか。
そして何より、中村八大と永六輔のコンビが、いかに長く歌い継がれる歌を常に念頭に置き、既存の方法やジャンルに縛られない柔軟なソングライティングで実現していったか。
事実を追究する過程を通じて、そうした機微を詳らかにすること。それもまた、あるいはそちらこそが本書の狙いであるからだ。
本書は佐藤の2冊目の著作となる。前著『上を向いて歩こう』(岩波書店)は、日本の歌では唯一ビルボード1位を獲得した、最近ではBBCが「世界を変えた20曲」の8位に選んだ(参考:20 of your songs that changed the world)このスタンダード・ソングの真実と事実を、世界の音楽史のなかに位置付けて追ったものだった。「上を向いて歩こう」も六・八コンビによる楽曲であり、本書『「黄昏のビギン」の物語』は前作のスピンオフという性格を持つ。あわせて読むとより細部と全体を把握できるだろう(ちょっと重複が多いけど)。
著者の佐藤剛は、70年代から音楽業界に携わり、ザ・ブーム、宮沢和史、ヒートウェイヴ、中村一義、ハナレグミ、小野リサなどを手掛けてきた音楽プロデューサーである。先般、世界的なヒット作となった由紀さおり&ピンク・マルティーニ『1969』も佐藤の仕掛けだ。冒頭で触れた、松原すみれとセルジオ・メンデスのコラボによる「黄昏のビギン」にも、本の中にそのいきさつが書かれているが、佐藤が関わっている。
自身のツイッターで佐藤は「新米の物書き」と謙遜していたけれど、すでにおわかりのように、実に手強い「新人」である。
■栗原裕一郎
評論家。文芸、音楽、芸能、経済学あたりで文筆活動を行う。『〈盗作〉の文学史』で日本推理作家協会賞受賞。近著に『石原慎太郎を読んでみた』(豊崎由美氏との共著)。