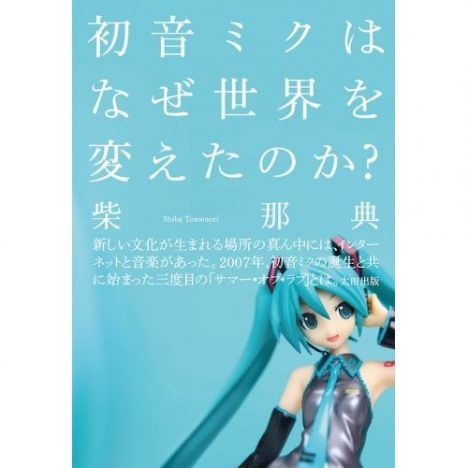新著『一〇年代文化論』インタビュー
“アーティスト”から“パフォーマンス”へ さやわかが「一〇年代音楽」のモード転換を語る
パフォーマンス系ミュージシャンは、「彼ら自身の物語」を持っている

――では2007年辺り、Perfumeのブレイク以降は、そういったパフォーマンス化がさらに進んだと?
さやわか:2007年以降は、パフォーマンスを中心にして作品作りがさらにシステマティックになったんだと思います。今回の本でも指摘しているのは、Perfumeは誰がコントロールしているのかわからないものだ、ということなんですね。これは最近のアイドルもそうだし、ボカロPとかもそうなんですが、アマチュアのレベルでも非常に分業化が進んでいて、曲を作る人、歌詞を書く人、ジャケットを作る人、ミックスだけをやる人、という感じで、みんなで一つの作品を作り上げるスタイルが増えている。Perfumeもそうで、MVを撮る人はMVしかとらないし、音楽を作る人は音楽しか作らない。僕の本ではそれらのハブというか、最終的な依り代となって作品を下ろすのが、あの三人の女の子のパフォーマンスという考え方をしています。以前だと、ある程度は誰かがコントロールしているという発想だったと思うんですけど、そうじゃなくなった。なぜそうなったかというと、先ほどの同期の話とも繋げて言えば、音と映像というものがむしろ分離可能になったからなんですよね。要は、デジタルフォーマット的な考え方が多くの人に理解されて、たとえばDVDなら、音楽や映像や字幕がひとつのコンテナの中でくっついて、1ファイルとして再生されているということがすんなりわかるようになった。だから字幕や音声部分だけをすげ替えて別言語に対応させることだってできる。複数の要素が同期再生されることでひとつの作品になるんだっていう感覚が一般にも浸透してて、それに合わせた創作スタイルによって生まれているのが、Perfumeとかボカロ以降のエンターテイメントなんだと思います。
――本書ではシステムの変化だけではなく、さまざまなエンタメ作品の変遷を追うという形で、特にライトノベルにおける内容の変化について書かれています。では音楽に関して言うと、どういった内容的な変化が見られるとお考えですか。
さやわか:僕がいま「パフォーマンス系」として触れたミュージシャンには、ジャニーズやAKB48といったアイドルはもちろん含まれるけど、彼らが一様に持っているものがなにかというと、結局のところ「彼ら自身の物語」だと思うんですね。たとえば今のモーニング娘。'14もそうで、彼女たちに勢いがあるのは曲の内容がどうこうというだけでなく、何作連続一位を目指すとか、作品の外部に強い物語を持っているせいもあると思います。つまり90年代的な「アーティスト」ではないから、歌詞の中に心情が直接的に歌われているか否かということじゃなくなっている。ももクロやAKB48の場合は自分たちの物語――つまり「成り上がって行こう!」みたいな感じを隠喩的に歌詞に盛り込むことで、ファンの側がそれを彼女たちの物語を彩る劇伴のように解釈する、ということが行われている。こういうのはアイドルだけじゃなくて、たとえばEXILEとかゴールデンボンバーとか、今どきの人気ミュージシャンはたいがい含まれますよね。それで、つまり、人気ミュージシャンは往々にしてパフォーマー化しており、場合によってはそのパフォーマーとしての生き様を想起させるような楽曲が作られるようになってきているということは言えるんじゃないかと思います。それは、シンガーソングライターが心情を込めた歌を作り魂を込めて歌うというのとは、近いようで遠いですよね。もちろん、そうじゃない音楽もたくさんあると思いますが、チャートの上位を見るとそういう傾向はある。
――なるほど。パフォーマンスとして「自己の物語」を演じるのと、「魂を込めて歌う」というのは似て非なるものだということですね。ただ、そのどちらも「本当の自分」のようなものを前提にしている気がするのですが、そのあたりはいかがでしょうか。
さやわか:この本を読んで「みんながパフォーマンス的にキャラを演じるようになって本当の自分がいなくなったから、僕らは楽に生きられる」とか、もしくは「本当の自分が持てない時代だから辛いね」みたいな解釈をする方もいらっしゃるのですが、どちらも半分だけ正しいと僕は思います。つまり役者がどのように役柄を演じるのかということが問題となっているだけで、役者の実存がなくなることが可能になったわけではない。これは本書でも触れていますが、そういう意味では「本当の自分」というポジションは、そんなものがあるかどうかはともかくとして、まだ意識されていると思います。「キャラを演じるために頑張る自分」みたいな感じで。結局、若者の悩みや辛さのあり方は昔と大して変わっていないんだと思いますよ。ただそれがひたすら固有の自分というものを追い求める中で生まれるのか、キャラを演じるための努力の中で生まれるかの違いだと思います。シンガーソングライター的な固有の内面を求める物語が好きな人は、パフォーマンス系の人を見下したりもするけれど、どちらも根底では似たような感性にドライブされる物語ですよね。
情報過多の中で音楽を流通させるには、キャラクターとか強いエモーションが有効
――物語を駆動させる装置として、主体性のようなものも生き延びているということですね。2000年代前半には社会学者の北田暁大さんが「歌詞フォビア」という言葉を使って議論していましたが、当時は一部の音楽ファンが「歌詞は音楽の本質ではない」「物語から離れて音そのものを聴くべきだ」という風に語っていて、実際にそういった志向性を持つ優れた作品も生まれていました。「音響派」と呼ばれる音楽ジャンルも発展しましたけど、さやわかさんは今その流れをどう整理していますか。
さやわか:前著である『AKB商法とは何だったのか』もそうですが、『一〇年代文化論』を書くにあたっても、音響的なアプローチについて考えざるを得ない場面がありました。音響系は、一言で言うと音そのものに収斂させていくことが音楽にとって重要なことだという考え方で、それをさらに掘り下げて解釈すると、音というのは「私の鼓膜(もしくは身体)に響いている何か」であって、つまり音楽というものは極めて個人的な体験である、ということだと思います。それは煎じ詰めれば料理のようなもので、たとえばカレーを食べて「辛い」っていっても、その「辛さ」というのは本当は誰にも共有できていない、というところにまで至ってしまう。つまり、かつてのDJブームあたりから始まるリスナーズミュージック――ミュージシャンではなくて、私たち音楽を聴いている側にイニシアチブがある、という考え方の極北に、音響というものはあったのだと僕は思います。ところが、そういう風になると音と人は、一対一の関係にならざるを得ないので、解釈の娯楽としては楽しめるかもしれないけれど、シーンとしては動かなくなりますよね。というかブームやシーンという考え自体が成り立ちにくくなる。だからリスナーズミュージックの流れのひとつの完成形を生んだ先には、個々のリスナーのレベルにまで細分化され拡散したシーンしかなくなってしまう。
――確かに、音響的な動きの中にはシーンという概念自体を良しとしない面はあったかもしれません。
さやわか:ただ僕がやりたいのは、今さらそうした音楽のあり方を否定することじゃなくて、その後で何が起きたかを知ることです。先日ちょうど渋谷慶一郎さんに取材したときにお訊きしたのは「情報がすごく増えたし、情報が錯綜するようになったから、情報に記号性とか具象性を含ませないと認識してもらいにくくなった」ということなんですよね。だから渋谷さんは初音ミクを使ったと仰った。その通りなんだと思います。情報過多の中で音楽を流通させるにはキャラクターとか強いエモーションが有効だし、それこそマッシュアップじゃないですが、素材としても手に取れる場所にあるから、ならば使おうということになる。単純に音響が退潮したというよりも、そういう風潮になっているのではないでしょうか。言い換えれば各人にとってのものとして拡散した音楽を、初音ミクなどのキャラクターを中心に置くことによって再統合する。この本でも音楽が共有されるものに変わってきている、といった指摘をしています。音楽が中心的なハブになって人々を繋げているんだと。そういう状況に対して、「音楽そのもの」が重視されていないじゃないかと批判する人もいるかもしれないけれど、僕はそれは考え方が違うのだと思います。音楽がリスナーに行き渡らないと、「音楽そのもの」について考えることも難しくなっていく。だから今が音楽にとって敗北かというと、そうではない。むしろ音楽はあらゆるメディアのハブになって、遍在するような状況になっている。先ほどのPerfumeの話もそうでしたが、要は、なにが頂点かというヒエラルキー的な考え方自体が否定されている状況なんだと思います。そこで音楽こそ至上なのかどうかと、いちいち再確認する必要がなくなっている。
――音響はある意味ではテクスト論的なアプローチというか、音を構造分析的に聴くという方法論でもあったと思います。この本もテクスト論的な面があり、分析の対象は文献から事象に広がっていますが、さやわかさん自身の体験などは可能な限り排して分析するというスタイルで書かれています。
さやわか:そうですね。僕は媒体によって書き方を変えるので、カルチャー誌のルポルタージュやレビューなら、自分の体験や主観に基づいたものも書きます。でもその書き方だと、その体験に共感できるか否かという読み方をされがちなんですよ。要するに「お前はこれを好きだからホメているが、それは真実ではない」とか「お前は現場を見て書いているから正しい」とか、そういう価値観で判断される。僕はそれに疑問があるので、自分の本では、なるべく自分の体験や主観を切り離して、誰から見ても説得性の高い本にしようとしている。正直、どっちの書き方にも良さがあるので、僕はそこで正誤がわかれるとは思ってないですね。それに仰るとおりテクスト論にも音響の話と似たようなワナがあって、なんでも構造のレベルに置き換えてしまいがちなんですよね。書き方というのはバランスが大事で、体験だけに依るのでもなく、テクスト論に終始するのでもなくて、ちゃんと補完できるような要素を用意しておくのが大事だと思うんです。だから僕は構造分析のように見せかけつつ、本全体としてはひとつの物語性を持たせるというか、エモーションに駆動されるようなやり方を著作では必ずやっています。同じライターだと僕は磯部涼さんの書き方とかが好きで、彼はライブ評などでも分析的な視点を挟みつつ、同時に「すれ違った女の子の汗がベタっとしていて気持ち悪かった」みたいなことも書くんですね。分析的な視点と個人的な体験を渾然一体にして書いていて、そういうスタイルを好ましく思っています。