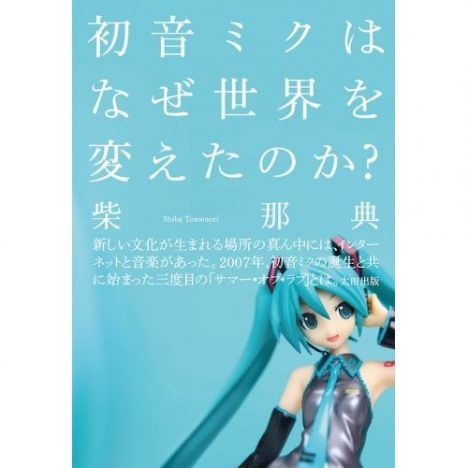新著『一〇年代文化論』インタビュー
“アーティスト”から“パフォーマンス”へ さやわかが「一〇年代音楽」のモード転換を語る
ライター・物語評論家のさやわか氏が、自身三冊目の単著となる『一〇年代文化論』を、4月24日に上梓した。『一〇年代文化論』は、「次の10年のコアとなるものは、その直前にある」という見立てのもと、2007年頃のカルチャーの変化に目を向けることによって、現段階で2010年代のカルチャーの本質を捉えようとする意欲的な書物だ。「残念」という言葉の意味の移り変わりから、アイドルやライトノベルのあり方の変化を鋭く評した本書は、10年代の音楽シーンを語る上でも示唆に富む内容となっている。そこで当サイトでは、特に音楽シーンにおける10年代の変化について、表現方法やその内容、評価のあり方といった側面から分析してもらうとともに、同氏の書き手としてのスタンスや方法論まで詳しく聞いた。
「残念」なものが、世の中で大事だと思われるように変わった
――本書では「残念」という言葉の意味合いが、2007年頃からポジティブなニュアンスを含むものに変わってきたことから、10年代のカルチャーの本質とは何かを考察しています。その言葉の変化に気付いたのはいつ頃でしょうか。
さやわか:そう思うようになったのは本当に最近ですね。ここ2、3年くらいで「残念な美人」とか「残念なイケメン」とか、そういう表現をよく見るようになり、これは意味が変わっているのかな?と関心を持ちました。僕はもともと言葉の意味の変遷に興味があって、とくにネットスラングなどがすごく好きなんですね。価値が揺らぐというか、意味が移り変わってしまうのがネット用語の面白さだと思っていて。もちろん自分の原稿ではちゃんとした言葉使いをするけれど、そういう風に言葉の意味合いが壊れるのを観察するのは好き。言葉ってもともとルーズなものですから。で、最近の「残念」の使われ方で象徴的なものを探していて、2009年に公開されたITmediaのインタビュー記事「日本のWebは『残念』梅田望夫さんに聞く」に行き当たりました。そこで使われている「残念」は従来の意味合いでしたが、今現在、この言葉がポジティブな意味合いに変わっているとすれば、梅田さんが指していた「残念」なもの、つまりはサブカルチャー的なものが、世の中で大事だと思われるように変わったといえるのではないかと。そういうアクロバティックな思考の転換が期待できそうだと思い、この本を書くきっかけになりました。
――実際に言葉の意味合いが変化し始めた時期は?
さやわか:たとえば2007年にテレビ番組『人志松本のすべらない話』の中で、千原ジュニアが兄の千原せいじを「残念な兄」として、そのエピソードを紹介していたことですね。その「残念」には、単に貶めるだけじゃなく、おもしろおかしい意味合いが含まれていて、割とポジティブに使われていました。これが新聞報道などにもそのまま使われていて、言葉の意味合いが少し変わったのを感じさせる。お笑いの世界ではそれ以前にも、2004年に波田陽区の「残念」という言葉が流行語大賞に選出されていますが、その時はぜんぜん違う意味合いです。だけど2007年の千原ジュニアの頃には、次第にポジティブな意味を含むように変わっているわけです。
――本書で指摘する新しい「残念」は、清濁併せ呑むというか、良いところも悪いところもひっくるめて対象を愛する態度が生まれてきた、ということでしょうか。
さやわか:そうですね。そもそもこの本で何を書きたかったかというと、日本文化について、最近は従来的な意味での「良さ」や「悪さ」という価値体系が壊れている、ということなんです。そのキーワードとして象徴的に使えるのが「残念」という言葉だったんですね。たとえば音楽でも、もともと「価値がある」ものと思われていたものがだんだん廃れてきて、逆にそんなによくないと思われていたものが評価されるようなことはよくありますよね。ロックに限っても、価値の転倒というのは何度も起きてきた。90年代の「オルタナティブ」「ローファイ」なんていう言葉はまさに価値の転倒によって生み出される概念です。だけど最近は、それをさらに越えた感じで、必ずしも「良い」「悪い」という嗜好性だけが大切ではなくなっている。2007年頃はマッシュアップの曲がたくさん作られていて、その考え方ってもう「良い曲同士を繋げる」「楽曲的に親和性があるから組み合わせる」といった、従来のミックスの考え方を逸脱してしまっているんですよね。ドラえもんの曲とガバ(ハードコアテクノの1ジャンル)の曲をとりあえず繋いでみた、ということが普通に行われるようになった。それは単に「できるからやる」っていう発想に近くて、良い悪いで括れる話ではないと思うんです。それから、MADのような形で全く無関係な音楽と映像が組み合わされることも非常にポピュラーになった。それまではクラブVJのような即興的なスタイルを除くと、音声と映像が的確に結びつけられたものが「公式PV」として作られているだけなのがポピュラー音楽の状況だった。つまり固有性があったわけですよね。だけど今は、音楽が好き勝手な素材と組み合されるのが当たり前のものとして捉えられるようになりました。
総合芸術としてのパフォーマンスを提示した、Perfumeの重要性
――本書では、Perfumeが時代の変化を象徴するアーティストとして取り上げられています。
さやわか:Perfumeは重要なアーティストだと思っていて、彼女たちは総合芸術という形での、音楽偏重以降のリスニングスタイルのヒントになるんですね。たとえば今やそんなことを気にする人はあまりいないと思うんですけど、彼女たちが出てきたときは、ライブで実際に歌っていないことを指摘する声が多く、ネットでも揶揄的に評する人がそれなりにいた。しかし、そもそもあれはオートチューンをかけている音楽だからライブで歌わないのは当然だと言えるし、逆にいえば、オートチューンがかかっているのにライブを重視して活動しているところが面白いグループなんです。つまり、音と動きを同期させていくライブパフォーマンスがPerfumeのやり方なんですね。音楽を流して、その歌に合わせて口も含めた全身の繊細な動きを見せることによって、あたかも歌っているかのようなパフォーマンスをする。これは極めて演技的な発想で、僕は実際のところ00年代の流れは、音楽も含めて演技的なものが台頭してきた10年だったんじゃないかとも思っています。そして、同期させるという発想は先ほどのMADの話と通じるものがあるんですね。MADは音と映像を同期させていましたけど、Perfumeの場合はそれを身体でやる。流れている歌とリップシンクすることによって、あたかも臨場感があるように見せる。ライブの現場ではその臨場感が立ち上がることに、人は感動してしまうんだと思います。AKB48は2005年に結成され、今のアイドルシーンでは代表的なグループとなっていますが、その前段階としてはPerfumeのブレイクはあったし、彼女たちが「今のアイドルがするべきことはパフォーマンスであり、演技的に臨場感を生み出すことなんだ」ということを広く知らしめたのはその後のシーンに大きく影響を与えたのではないかと思います。
――Perfumeブレイク以前のJPOP界では、シンガーソングライター的な創作姿勢を良しとする風潮が強かったように思います。つまり、確固とした思想や自我をもったシンガーが、自身の声や演奏でメッセージを伝達していくのが「本当のアーティストの姿である」という。Perfumeのようなパフォーマンス性の高いユニットが台頭してきたことによって、そうしたクリエイター像に変化が生まれたと?
さやわか:僕は「従来とは違うモードに変化した」という風に捉えています。宮台真司さんの『サブカルチャー神話解体』という書籍では「自作自演」という言葉がキーワードになっていて、シンガーソングライターがスピリットを作品に込めて、それが匂い立つものが「創作」であるという考え方が、フォーク以降の日本の音楽シーンの中では支配的だったと指摘しています。かつては、日本の音楽シーンにもいわゆる芸能界的な、作詞家がいて歌い手がいるという分業のスタイルもあったはずなんだけど、とりわけ80年代後半から、その人の主張をその人の声と楽器で演奏するのが、作曲家としての矜持になるという心理主義的な「アーティスト」性が重視されるようになった。僕はその到達点にいるのが宇多田ヒカルや椎名林檎といったミュージシャンだと思うんですよ。彼女たちがブレイクするのは98年で、ここが90年代の「アーティスト」路線のピークなんですよね。個人的には、宇多田ヒカルは若い時にデビューしているので、本当は新世代的な感覚を持っていたと思うんですよ。彼女はゲームやマンガも大好きで、もっと広い考え方で音楽に向き合える人だったのではないか。でも結果的にそうした時代が彼女に求めたのは「アーティスト」的なものなので、キャリアとしては安定していくというか、あまりリリースしない大家のようになってしまった。これは音楽メディアの問題としてもしばしば指摘されることなんですけど、音楽家はリリースするたびに毎回、人生のなんたるかを込めるわけではなく、本当は何も込めないで自由に創作したっていいはずなんですよ。しかし、それを良しとしない空気がメディアの後押しもあって作り上げられてしまった。それでヒット作を飛ばす人ほど高尚な「アーティスト」化して作品をリリースしなくなり、シーンとしても動きがゆったりしていってしまった。そういう風潮に対するオルタナティブとして、パフォーマンスが台頭してきたんじゃないかと思います。つまり、歌を歌うっていうのには「心を込める」ということとはまた別のレイヤーがあって、技術というものがちゃんとあるんだと。
――パフォーマンスの鑑賞を通して、技術的な面への注目が進んだということですね。パフォーマンス自体の台頭は2000年代以前からあったようにも思いますが――。
さわやか:たしかにそうなんですが、たとえば90年代末からは『ASAYAN』なんかであからさまにリスナーも教育されていった面があるんじゃないかと思います。たとえばモーニング娘。なら「恋はダイナマイト」と歌わないで、「ザイナマイト」と歌う方がかっこよく聴こえるとか、ギターを持つときに下の方で持った方がかっこよく見えるとか、そういうことがテクニックとしてあって、それをうまくやるために精神的な克己があるんだということにみんなが気付いていった。昔はテクニックよりも単純に「私は魂を込めて歌っている」という方が良いとされていたんだけど、90年代後半あたりから一般のレベルで改めてパフォーマンス性が見直されたんだと思います。本書の中で「次の10年のコアとなるものは、その直前にある」ということを指摘していますが、98年に宇多田ヒカルら「アーティスト」が90年代的な路線を極めてから00年代的な「パフォーマンス」の時代が台頭するというのは、わかりやすいのではないでしょうか。