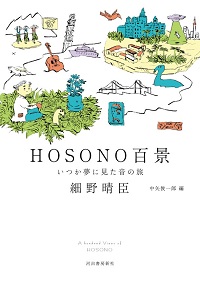新著『HOSONO百景』インタビュー(前編)
細野晴臣が語る“音楽の鉱脈”の探し方「大きな文化の固まりが地下に埋もれている」

はっぴいえんど、YMOなどで活躍した日本を代表するミュージシャンであり、今もなお第一線で作品を発表し続ける細野晴臣。彼がLA、ハワイからロンドン、パリ、東京まで、世界各地の土地柄と音楽について語り尽くした書籍『HOSONO百景』(河出書房新社)が評判を呼んでいる。雑誌『TRANSIT』人気連載を元にした同書は、氏の旅行記の体裁を取りつつ、随所で音楽に関する深い考察が披露されており、音楽ファンにとっても必読の一冊といえる。今回、リアルサウンドでは同書の刊行を期にインタビューが実現。聞き手に音楽評論家の小野島大氏を迎え、現在の音楽観や、ルーツに対する考え方を中心にじっくりと話を聞いた。(編集部)
「知れば知るほど、自由が効かなくなるっていうのはある」
――非常に楽しく拝読させていただきました。興味深い記述はいくつもあったんですが、まずニュー・オリンズの音楽の話のところで(「ニュー・オリンズの”ガンボ”に誘われて」144P)、ニュー・オリンズの音楽に惹かれたのならニュー・オリンズ詣でしようと思わなかったのか、と問われて「レコードがすべてを与えてくれるから。何かと何かが交じり合ったところにいつもおもしろい音楽ができる。それはある特定の場所ではなく、音楽家の頭の中でごった煮になるんだ。だから、どこへ行って録音しようとかは全然思わない」と答えられているくだりです。非常に印象的なご発言であると同時に、細野さんの音楽家としての基本的なスタンスを表していると思いました。
細野:あのね、自分の好きな音楽って漠然と聴いてたんですけど、聴いていくうちに、やはり混じりあった音楽がとても面白く聴こえるんです。それはいろんな混じり方があって、西と東だったり、時間軸でも混じりあってるし。過去と未来とか。あるいは人種間だったりね。もちろんそれも文化ですけど。で、自分自身も、音楽に限らず、混沌として混じりあったものが好きなんだってことが、だんだんわかってきたんですね。たとえば、東京で言えば下町の商店街の混沌とした感じとか。阿佐ヶ谷の街の作り具合とかね。そういうのを整理しちゃってる港区がほんとうに面白くないな、と。港区に住んでますけど(笑)。綺麗になりすぎてて。歩いてて楽しいのはビルの下じゃない。そのまま入っていけるような小さな商店が並んでいる道が面白いんで。ビルばっかりになっちゃったのが、あまり好きじゃない。そういう混沌としたところが好きなんですね。
――その土地のことは現地に行かないとわからない、というのが一般的な考えなのかもしれませんが、細野さんは、現地に行かなくても、音楽家が自分の頭の中でイマジネーションを働かせることで、ミクスチャーされた音楽ができるんだというお考えですね。
細野:そうですね。そうやって作ってきましたから。たとえば『トロピカル・ダンディー』(1975年)ってアルバムを作ったのは六畳一間の…一間じゃないか。二間ぐらいあったかな(笑)…アパートですよ。エアコンもない。夏になると熱帯夜に襲われる部屋で「熱帯夜」って曲を作ったりね。
それでイマジネーションが湧いてくるわけですよ。実際に見るとイマジネーション湧かないですから。固定されちゃうんで。自由にならなくなっちゃう。知れば知るほど、自由が効かなくなるっていうのはあるんですね。
――なるほど。しかしそうは言っても、この本にもある通り、世界中いろいろな場所を訪ね歩いておられるわけです。事前に思い描いていたイメージと、実際に見聞きするもののギャップを感じることもおありになる。
細野:うん、だいたい行くときはね、あまり音楽的なことは考えないで行くんです。さっき言ったように、街を歩いて楽しいかどうかが僕の基準。だからヨーロッパの都市は面白いですよね。なんかこう…想像以上でも以下でもない。ここに僕は住めるなっていう等身大の感覚があって、唯一例外がインドですかね。インドは…僕にはとても巨大なエキゾティシズムの固まりの国だったんですけど、そこに行っちゃうと、呑まれちゃうぞと。本体のエネルギーにね。楽しめないんじゃないかと、行くなら最後だろうと思ってたんですけど、早々に行っちゃいましたね、横尾(忠則)さんに誘われて。(1978年。本書184ページ)
――インドは合う人と合わない人がはっきりしてるって言いますよね。
細野:横尾さんや三島由紀夫がそんなことを言ってたんですけど。で、誘われるままに行って、病気になっちゃって。
――そのエピソードも本に登場しますね。この本の冒頭で「本当は地球上で誰も訪れたことがない場所に行ってみたいんだ。でも、そこは必ずしも辺境の地とは限らなくて、都会にも人を寄せ付けない場所がある」(19P)と述べられてますね。これはすごく至言だと思ったんですが、音楽への接し方にしても、誰も知らない辺境の音楽だけではなく、人が見過ごしがちな、たとえば過去の音楽とか、そういうものを見つけ出してくるのも、ひとつの新しいものとの出会いに繋がるのかなと。
細野:うん、うん。最近特にそうですね。まだまだ知らない音楽がいっぱいある。なんかこう…鉱脈っていうのがあって。昔の森が埋没して地下に埋まっているような。それを掘るとエネルギーが出てくるわけですけど、それに近いことですね。音楽の鉱脈が埋もれている。それはひとつやふたつじゃなくて、大きな文化の固まりが地下に埋もれている。
――文化の固まり。
細野:ええ。50’sとか。20世紀のど真ん中の時代の文化っていうのが、すごいなと、今思うんですよ。エネルギーがね。うるさいぐらい騒々しかったので、一時期僕は苦手だったんですけどね。今はそれが貴重なエネルギーに思えてね。
――本書でも、50年代から60年代初頭までの――とは、ビートルズ登場までの、ということだと思うんですが――ポピュラー・ソングは、印象が変わらず飽きないと。そして特に50年代の歌詞は特殊で「世界を信じていた時代のものだった」と語られているのが印象的でした(50P)。やはりそのあたりを境にポピュラー音楽の質が変わっていったとお考えですか。
細野:うん、その頃は毎年劇的に変わっていったんですけどね(笑)。
――特にロックに関しては60年代後半以降、「悩みながら聴くもの」というものになっていきましたね。
細野:うん、そういう時代も経験してますね。ヒッピー・カルチャーが出てきてサイケデリックが出てきて。踊らせない音楽っていうのが出てきたんですね。それまではたぶん踊ってたんですね。
――ロックはそもそもダンス・ミュージックだった。
細野:ええ。それが座って聴く音楽になった。それを日本ではアート・ロックと言ってたりね。そんな時代を20代の前半で経験してますから。それに影響されてそういうバンドを作ったりしてましたからね。はっぴいえんどもそうですし。