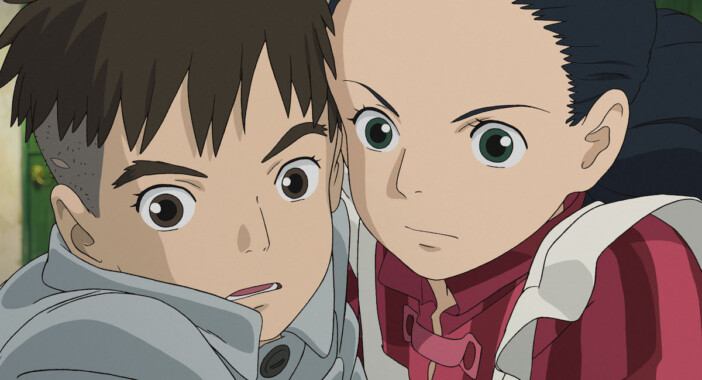『オッペンハイマー』のオスカー圧勝は完璧な“世代交代”に 『ゴジラ-1.0』快挙の意義も

クリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』が作品賞を含む最多7部門を制する圧勝で幕を下ろした第96回アカデミー賞。事前の予測では作品賞など複数の部門での受賞が当確状態で、「何部門を受賞できるのか?」という点に大きな注目が集まっていたわけだが、それを踏まえると授賞式の前半、ほとんど賞を獲れないまま進んでいった状況はなかなかスリリングなものであった。とはいえ最終的には、概ね順当な結果である。
強いていえば、音響賞で『関心領域』が『オッペンハイマー』を逆転したことぐらいが今年のビッグサプライズであろう。美術賞と衣装デザイン賞で『オッペンハイマー』が受賞を逃し、『哀れなるものたち』が受賞にこぎつけたのも、両部門の前哨戦でリードしていた『バービー』の作品としての勢いが目に見えて落ちていたからであり、結果的にメイクアップ&ヘアスタイリング賞も受賞した『哀れなるものたち』は、史上5作品目の美術・衣装・メイクの3冠を達成。この時点で主演女優賞もエマ・ストーンになる可能性がぐっと高まり、その通りになった。
それは同時に、マーティン・スコセッシの『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』を史上7本目となる“10ノミネート以上を獲得したのに無冠に終わった作品”へと変えることになる。しかもその7本のうち3本がスコセッシ作品というのだから、名誉なのか不名誉なのかわからないユニークな記録が生まれてしまった。

さて、この『オッペンハイマー』。原爆の開発者J・ロバート・オッペンハイマーを描いているということから日本国内でさまざまな議論が重ねられ、日本公開に漕ぎ着けるまでかなり長い時間を要した(結局アカデミー賞授賞式後の公開になるが)のは周知のことであろう。実際に観てみると、不思議なほど“原爆の映画”という印象よりも“赤狩り”の映画という印象が強い。むしろそのことが、この作品をアカデミー賞に導いたのではないかと感じるほどである。
歴史上の1人の人物の身に起きた出来事と心情を綴る典型的な伝記映画として作品賞に輝くのは『英国王のスピーチ』以来(一応、『グリーンブック』も伝記のようなものだが、典型的な伝記映画ではない)。そもそもノーランが伝記映画を撮るという意外性もさることながら、“ノーラン節”とでもいうべきだろうか、圧倒的な情報量の多さが従来の伝記映画とは一線を画す。切り返しショットの連続で重ねられていく会話のシーンに、複雑に絡み合う時間軸。トリニティ実験のシーンを除いたら“じっくり見せる”シーンはほぼ皆無で、ひたすら途方もない情報量と人物のやり取りを3時間という長尺に詰め込み、ノーランらしく終盤は予告編のように一気に畳み掛けてくる。
それだけに、現行の作品賞の投票システムで順当にトップに立てるのかどうか少々不安になったのもまた事実。かつての1作品を選んで投票するシステムから優先順位付き投票制に変わったことで、言葉は悪いが“当たり障りのない”作品が選ばれやすくなってきたのが近年の作品賞の傾向だった。『ソーシャル・ネットワーク』よりも『英国王のスピーチ』、『ゼロ・グラビティ』よりも『それでも夜は明ける』。『ROMA/ローマ』や『女王陛下のお気に入り』よりも『グリーンブック』。『DUNE/デューン 砂の惑星』や『パワー・オブ・ザ・ドッグ』よりも『コーダ あいのうた』といったように。

それでも作品賞まで突き抜けたのは、前述の“赤狩り”要素ももちろんのこと、現代の映画界を牽引する存在であるノーランに「ここで獲らせなきゃいつ獲らせるんだ」という心理が会員のなかで強く働いたことも一理あるだろう。監督賞のときにはプレゼンターがスティーヴン・スピルバーグ。作品賞のプレゼンターは、スコセッシやフランシス・フォード・コッポラ、リドリー・スコットといったレジェンドたちと仕事をしてきたアル・パチーノ。しかもパチーノはノーランの初メジャー映画『インソムニア』の主演俳優と、完璧な“世代交代”のお膳立てができあがっていたのである。