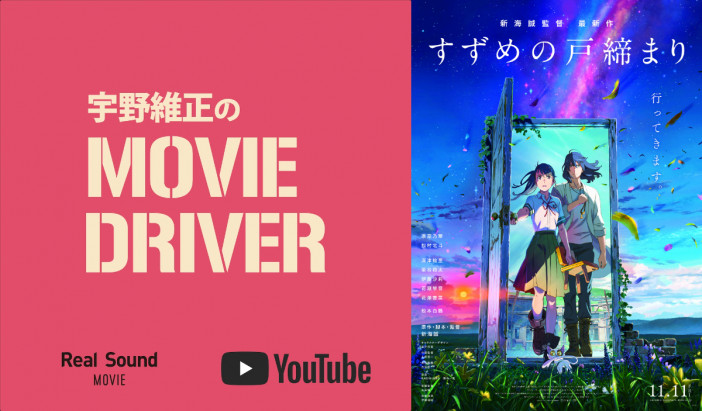『すずめの戸締まり』に新海誠が込めた切実な思い “生きる意味”の問いに応える一作に

人はいつか死ぬ。それだけは確実に決まっている。
そして、この国だっていつか終わる。終わりがあると知っていて、人はそのことを見て見ぬふりをして、あるいは忘却して日々を過ごしている。
しかしそのことを忘れていたとしても、人の終わりは突然訪れることがある。そういう理不尽な終わりが身近に襲ってくることに、普通の人は耐えられない。だから、また忘れる。
そんな理不尽に人は耐え続けることができるだろうか。そんなことに耐えながら、1分、1秒でも長く生きることに意味はあるだろうか。
終わりがあると知りながら、それでも1分・1秒でも長く生き永らえる意味はあるだろうか。
新海誠監督の最新作『すずめの戸締まり』は、それに応える作品だ。生きる意味はあるかとの質問に答えるのではない、そう思う気持ちに「応える」作品だ。
日本列島は人の力ではどうしようもないほどに自然災害が多い。いつ何どき、理不尽な終わりがどこで襲ってくるのかわからないこの土地で生きるとはどういうことか、新海誠は今回、その生き方の一つを謳いあげているのである。
自然災害と向き合う作家としての必然
本作は、東日本大震災にかかわる物語だ。新海監督にとってこれを描くことは、必然だった。
本人は小説版『すずめの戸締まり』のあとがきでこう記している。
僕にとっては三十八歳の時に、東日本で震災が起きた。自分が直接被災したわけではなく、しかしそれは四十代を通じての通奏低音となった。アニメーションを作りながら、小説を書きながら、子供を育てながら、ずっと頭にあったのはあの時感じた思いだった。
<中略>
あの後も世界が書き換わってしまうような瞬間を何度か目にしてきたけれど、自分の底に流れる音は、二〇一一年に固着してしまったような気がしている。
(小説『すずめの戸締まり』P369、角川文庫)
東日本大震災は、日本という国全体にとって決定的に大きな出来事であったことは間違いないが、アニメーション作家としての新海誠にとって、国の重大事とは別個に重要なものになったに違いない。
新海誠は、景観の描写に想いを託してきた作家だ。自主製作として作り上げた『ほしのこえ』の頃からそれは一貫している。雨、雪、雲、そして太陽の光。都市空間であろうと、地方であろうと、新海作品には自然現象の中で息づく人間の営みがあり、キャラクターの芝居以上に景観が饒舌に登場人物たちの感情を豊かに表現していた。
その景観は常に美しかった。ある意味、自然の美しい部分を拝借してきたという面が、初期の新海作品にはある。
その新海監督が、作風において決定的な断裂を迎えたのは2016年の『君の名は。』だ。過去作を観てきた人なら、それ以前の作品とは娯楽性の高さやストーリーラインの快活さなど、いくつも過去作との相違点を見つけることができるだろう(過去作との連続性も大量にあるが)。

『君の名は。』にあり、過去作にないものの一つに、自然災害という要素がある。この時、新海誠が自然災害を作品内に取り入れたのは、東日本大震災の影響であることは当時の種々のインタビューで公言している。
『君の名は。』で男性主人公の瀧は、女性主人公の三葉に入れ替わり、糸守町での暮らしを経験する。その時の記憶を頼りに糸守の風景を絵にする。その絵を頼りに三葉を訪ねると、糸守町は彗星の落下で消滅していた。
この描写は、景観を重視してきた新海誠にとって自然災害がどんなものであるかを端的に示している。自然災害は、想いを託すべき景観を一瞬で破壊するのだ。
景観描写を得意としていた新海監督にとって、自然のこうした理不尽さを、東日本大震災を経た後に無視することなどできなかっただろう。もし、そこに向き合わなければ、それは社会に対しての不誠実というより、自身の作家性に対して不誠実になっただろう。

続く『天気の子』では、これまで幾度も作品の中で多用してきた雨を題材にした。雨によって水没する東京もまた、やはり自然災害によって失われる景観があることに目くばせしている。
『君の名は。』も『天気の子』も、それ以前の作品から引き続き美しい景観描写も武器としている新海監督だが、その美しい自然が猛威をふるい、美しいままに人を殺し、風景を奪い去ることがあることを描き始めたのが『君の名は。』以後と以前の作風の違いと言える。それは自然風景に対する新海監督の構えが変わったことを示している。