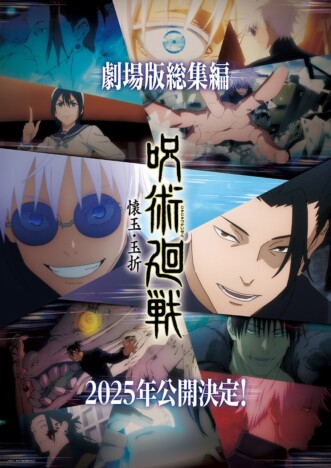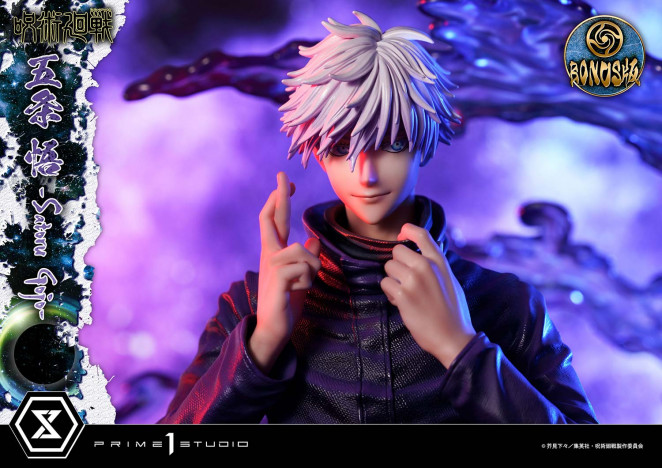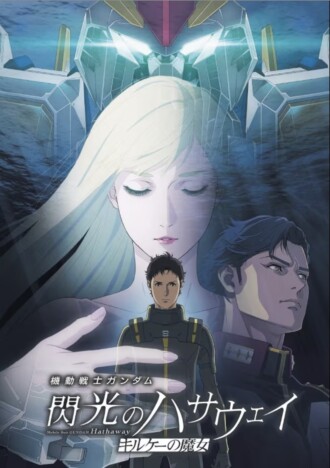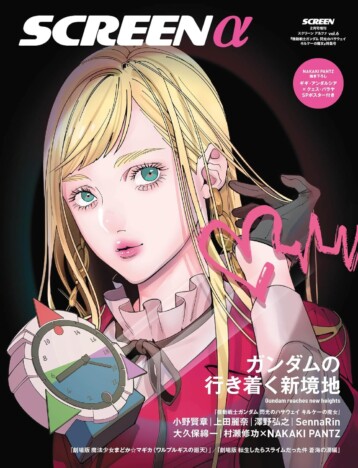『呪術廻戦』なぜ宿儺は虎杖に負けたのか “呪い”と“呪術師”を分ける決定的な違いとは?
虎杖と宿儺の命運を分けたものは?
とはいえ、「呪術師は大切な人との絆に突き動かされて戦う」と表現すると聞こえはいいものの、そこにあるのは必ずしもいい面だけではない。逆に“誰かの言葉が呪いに転じる”という負の側面も存在するからだ。『呪術廻戦』のもう1つのテーマとは、この呪いを解くことにあると思われる。
たとえば虎杖は「渋谷事変」において、宿儺や真人の凶行によって心が折れる一歩手前まで追い込まれるが、七海建人が遺した「後は頼みます」という言葉で再起を果たす。しかしこの言葉は七海自身も理解していたように、後に“呪い”へと転じることに。虎杖はその後、何か大きなものの「歯車」のように敵を倒し続けることが自分の役割だと語るようになり、人間らしさを失って戦いに没入していく。
また、禪院真希が身代わりのように死んでいった妹の真依から「全部」「壊して」という遺言を託され、実の母を含めた禪院家を容赦なく全滅させたことも、一種の“呪い”が作動した結果と言えるだろう。そのほか乙骨憂太と祈本里香の関係や、五条悟と夏油傑の関係においても、こうした描写が見て取れる。
それを踏まえて最後の戦いである「人外魔境新宿決戦」を読むと、虎杖と宿儺の勝敗を分けたのは、他者を受け入れるかどうかという姿勢の違いだったように思われる。
虎杖は死闘の果てに、自分を「歯車」と思うことをやめ、人間らしさを取り戻す。それは宿儺をたんに殲滅するのではなく、“言葉”によって説得しようとすることによく表れている。それに対して宿儺は虎杖が歩み寄ることを認めず、最後まで他者を拒絶した生き方を貫き通した。
印象的だったのは、宿儺の内に沈んでいた伏黒の魂が息を吹き返し、虎杖のためにチャンスを作り出した場面だ。伏黒は姉・津美紀を失って生きる気力を失っていたが、虎杖の言葉によって希望を取り戻し、“もう一度誰かのために生きる”ことを決断できた。すなわちこの戦いで宿儺を追い詰めたのは、人に影響を与え、人から影響を受けるという呪術師たちのあり方そのものだったのではないだろうか。
実際に、宿儺自身もその敗因を理解していたようだ。戦いに負けて消滅した後のこと。循環する魂の通り道で真人と言葉を交わした際、宿儺は今までの人生で2回、「違う生き方」を選ぶきっかけがあったことを漏らす。
つまり宿儺は誰かに影響を受ける可能性があったにもかかわらず、虎杖とは違ってそれを拒絶したということだ。逆に虎杖も、言葉という“呪い”に囚われたまま生きていれば、宿儺のようになっていたのかもしれない。
この小さな、しかし決定的な違いこそが、2人の命運を分けた。だからこそ“呪いの王”が誰かのために生きるという価値観を認める場面は、物語のクライマックスにふさわしいと言える。
なお言葉によってつながるのは、生きている仲間だけではない。最終決戦後の日常を描いた第271話では、虎杖が五条から託された「期待してる」という言葉を受け継ぎ、未来に向けて歩み出すところが描かれていた。
絶望的な展開をいくつも描きながらも、最後には読者を希望に満ちた結末へと導いてみせた作者・芥見下々。『呪術廻戦』は見事な大団円を迎えたが、その作家性は今後どのような形で発揮されていくのだろうか……。