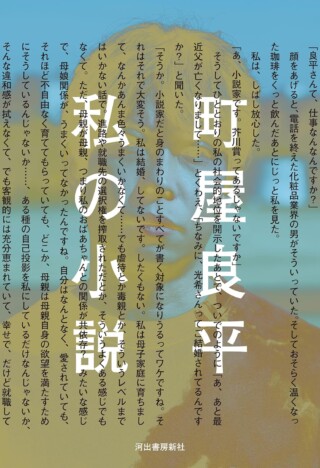多彩なテクストのサンプリングで描く、沖縄という土地の走馬灯 豊永浩平『月ぬ走いや、馬ぬ走い』レビュー

書名の『月ぬ走いや、馬ぬ走い』は「ちちぬはいや、うんまぬはい」と読むらしい。沖縄に伝わる「黄金言葉」(くがにくとぅば)と呼ばれる俚諺、ことわざで「馬さながらに歳月は駆け抜けてしまいますから、時をだいじにすべし、けれど苦悩は結局なくなるものとして抛ってしまいなさいな!」という意味だという。「黄金言葉」に馴染みのない私が、まずタイトルから連想したのは「走馬燈」という言葉のほうだった(と思って読み進めたら、実際、二人目の語り手の兵士のパートに「走馬燈」という言葉が登場した)。ぼんやりとした脳裏に思い浮かぶ、過去のさまざまな記憶。まさに本書は、沖縄という土地がいつか見るやも知れない「走馬燈」のようである(そして、戦後に発表されたさまざまな小説の残影が否応なく脳内にちらちら浮かぶ本作は、忘れられゆく(戦後)文学の走馬燈のようでもある)。
「かなちゃん」が「ユーレイとは話せないよ」というのに対し、浩輔の「オバア」が「べつにあたりまえみたいな感じで、話せいさあ、って言いながらまた誰かと仲良くおしゃべりする」ように、作者は引用を通じて、さまざまな不在の言葉たちと交流する。そこでは、エリオット『火の説教』や、谷川俊太郎/パウル・クレー『クレーの天使』のような古典的名著から、『グラップラー刃牙』や『呪術廻戦』のようなポップカルチャーまで、文化の硬軟を問わず、本書では多彩なテクストがサンプリングされている。なかでも本作の重要なインスピレーション源が、ヴァルター・ベンヤミン「歴史の概念について」である。そこで述べられるベンヤミンの「歴史をエピソードとしてみるのではなく、ひとつひとつの破壊された瓦礫の積みかさなった、できあいのものとして見ること」が重要だという態度は、まさに本書全体のアイデアに関わるものであるだろう。
血脈のごとく代々受け継がれ(てしまっ)た暴力が生んだ数多の「瓦礫の積み重なった」場所から立ち上がる物語は、そのラストにかけ、ある点(ある事件と事故)に向かって収斂していく。そののちに語られる結末は、「物語は世界をうごかすに足るものだ。わるい物語はよい物語を改竄してしまう。その逆もまた然り」と語らせる作者ならではの、暖かな着地であり、思わず強く胸を打たれてしまった。
本書中盤、比較的作者に近いと言ってよいだろう人物のラップパートがある。この「小さな巨篇」の、さらに小さな断片に過ぎないものの、この一文には、作者の、本作の、魂(マブイ)が、確かに込められているように思う。要するに、ここには本書の全てがある、ということだ。
〈消えてゆく街の灯、この島に降り注いだ戦火、そしていまここに生きているおれらは何? 歌が明かすのはこれからの偽りのない日々、眼を閉じれば瞼のうら浮かぶビビッドな島の歴史、それなら歌い続けよう、たとえポエマーだと馬鹿にされようと、犬掻きして、必死をこいて、波をさらい見えるのは宝物と何? 死に死に死んで死の終わりに冥し、だとしてもおれらは生まれ生まれ生まれ生まれてやるのさ〉