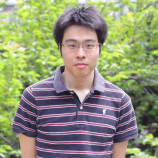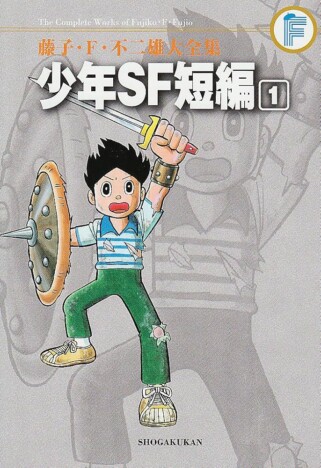藤子・F・不二雄が描いた核戦争への不安 NHK BSドラマ『マイシェルター』原作を読む
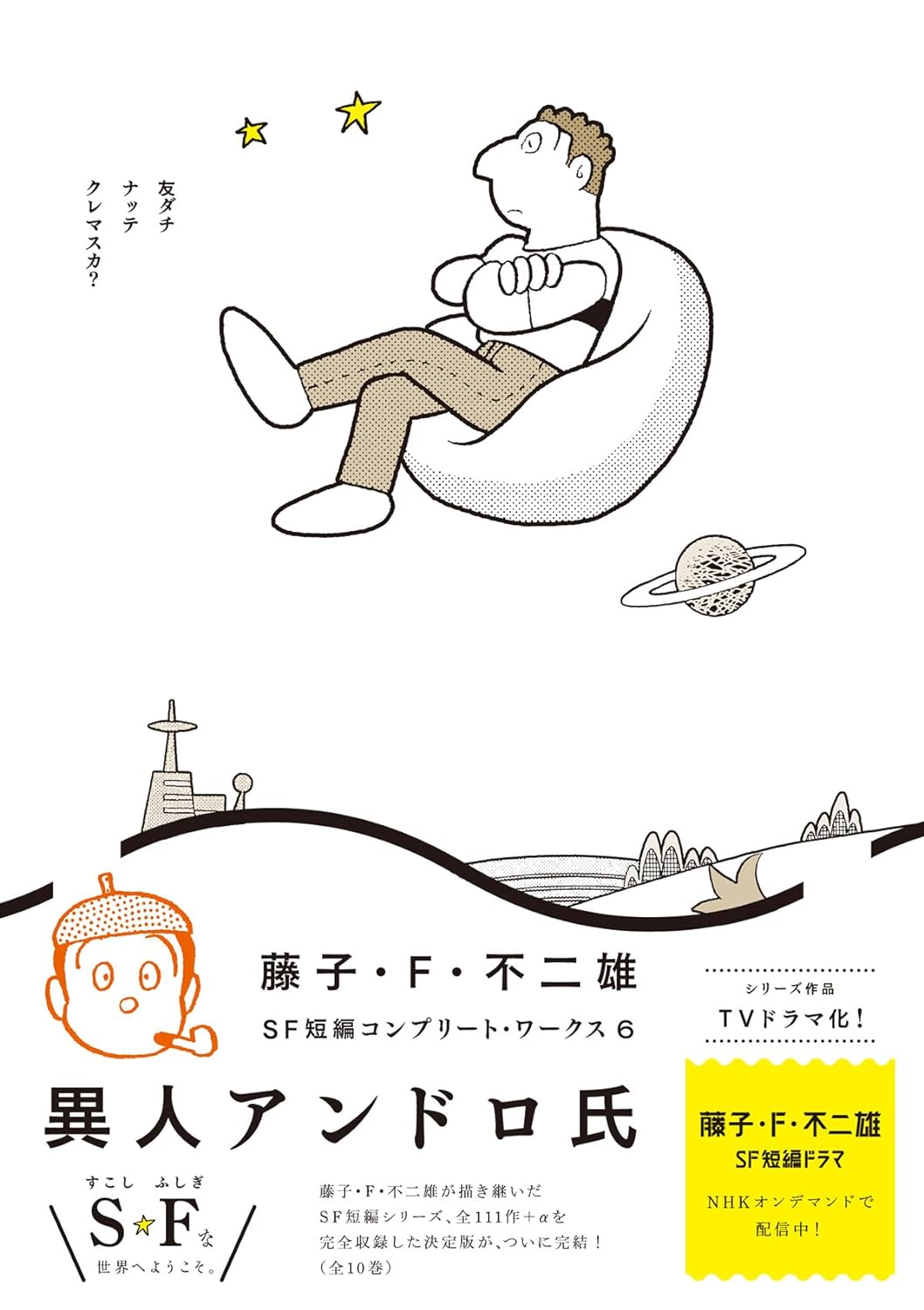
『マイシェルター』でも同様に、シェルターの問題は物理的なものから、次第に倫理的なものへとシフトしていく。主人公は最後に、核戦争での爆風で大やけどを負ったシェルター外の人たちを、シャットアウトできるかどうかという問いを突き付けられる。人の生死を決めるボタンを前にした、主人公の決断は……。
家族の説得はできたとする。シェルターに入り、一次災害は避けられたとする。放射能の影響も避けられたとする。シェルター生活でのストレスも不問とする。倫理観は麻痺して何も感じなくなったとする。……しかし、それでもまだまだ、希望にはほど遠い。放射能が消滅してシェルターを出たとして、そこには何が残っているのだろうか? 藤子・F・不二雄の過去作を参照しても、核戦争後の世界は「地球の全表面はキノコ雲に包まれた」(『どことなくなんとなく』)「草一本残らないという状況」(『カンビュセスの籤』)など、もはや人間が住むことが不可能な環境であることが示唆されており、結局、シェルターなどはあくまでも、一時しのぎの手段でしかないことが予期されるのではないか。
では、シェルターが希望の箱舟(言い忘れていたが、セールスマンから紹介されるシェルターには「箱舟」という名前が付けられている)にならないとすれば、人類にはどのような手段が残されているだろうか。おそらく、それは二通りにわけられる。一人ひとりが「反核」という声をあげ、核の危機を未然に阻止するか、もしくは「苦しい時の神頼み」として、人智を超越した存在に助けを求めるかである。
本作のラストでは、この二つの選択肢が、どちらもありうるというような形で示される。未読の読者のために詳細は伏すが、より作中の時代が、人類の終末期に近づいた『カンビュセスの籤』や『宇宙人』では、人類の暮らす世界は、自身たちの努力による改善は不可能な状況にまで追い込まれる。つまり、この二作においては、「神頼み」しかもはや選択肢はなく、主人公たちは一心にそれにすがろうとする。それと比べれば、『マイシェルター』には読後感の苦さはあるとはいえ、まだどこか希望を感じさせる。
とはいえ、本作の発表から40年あまりを経た現在の状況を鑑みると、そうした希望の萌芽を無条件に受容することはできないだろう。ウクライナ戦争やイスラエル・ガザ戦争、また台湾有事への懸念など、ふたたび「核」をめぐる危機はアクチュアルになりつつある。ドラマにはノスタルジックに藤子・F・不二雄の世界を振り返るのみではなく、どのように現在進行形の脅威として「核」に向き合うかという問いへの、今だからこそできるアプローチを期待したい。