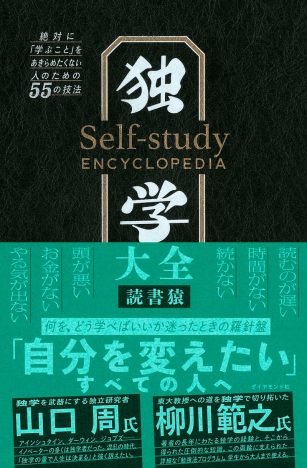文筆家にして編集者・吉川浩満インタビュー 情報収集術から人文書の潮流まで語り尽くす

文筆家として、編集者として、八面六臂の活躍を見せる吉川浩満氏。昨年にはロングセラーとなった『理不尽な進化』の増補新版(ちくま文庫)も発売された。しかし編集者としてのキャリアには紆余曲折があったそうで……。今回は、そんな吉川氏に、企画の立て方や情報収集の仕方について伺った。(中垣内麻衣子)
文学青年、逆ギレして出版社を辞める
――まずは、どのような理由で編集者を志したのか教えてください。
吉川:私は2020年から晶文社で仕事をしていますが、編集の仕事はこれが初めてではありません。じつは1994年の新卒時に「特殊版元」などとも呼ばれる国書刊行会という出版社に就職し、少しだけ編集の仕事をしたことがあります。
私が本を読むようになったのは大学に入ってからでした。それまでほとんど部活動(卓球)のことしか考えていなかったので……。大学生になって初めて、知的なものに自覚的に触れるようになったんですが、すべてが新鮮で、何もかもが面白く感じられました。遅れを取り戻そうとするかのように本を濫読するうちに、すっかり「遅れてきた文学青年」みたいになっていましたね。
そうこうするうちに、本を作る仕事があるということを知り、本の企画編集の仕事をしてみたいと思うようになりました。それで非常な熱意をもって国書刊行会の求人に応募して、ありがたいことに入れてもらったんですが……すぐに辞めちゃったんです。
国書刊行会には、後に『龍彥親王航海記――澁澤龍彥伝』(白水社)で読売文学賞を受賞することになる礒崎純一さんや、膨大な数の海外文学・ミステリ・怪奇幻想小説の企画編集を行う藤原義也さん(後に藤原編集室)といった超絶優秀な編集者がいました。理想だけ高くて視野の狭かった私は、すごすぎる先輩たちを見て「自分には無理だ」と早々に諦めちゃったんですね。ほとんど逆ギレみたいな感じです。
もし思うような結果が伴わなくても、好きなことを続けられるならそれでいいじゃないかという考えもあったはずなのですが、当時はそんな風には考えられませんでした。それですぐに辞めてしまったので、その時は1年くらいしか編集の仕事をしなかったことになります。

――理想が高かったからこそ、自分が理想からかけ離れているように思え、耐えられなかったということでしょうか。
吉川:おっしゃるとおりです。青かったということでしょうね。いまとなっては、飛び抜けた能力をもつ人は少ないこと、自分は「それなり」でしかないことがよくわかるし、わざわざそれでショックを受けることもありません。でも当時は若かったし、「やるからには優秀じゃないと意味がない」みたいな気持ちがあったんですね。
それで国書刊行会を辞めてヤフーという会社に入りました。1996年の夏ですから、ヤフーができた年のことです。当時隆盛しつつあったインターネットに興味があったからというのもありますが、なにより、誰もやっていないような仕事がいいなと。それならいちいち逆ギレしなくても済みそうだし。
実際、ヤフーでの仕事は誰もやっていないような仕事でした。いまでは考えられないかもしれませんが、当時のデファクトスタンダードであったヤフーの検索エンジンはディレクトリ型といって、ウェブサイトを手動で分類して紹介文を付すといったやり方でデータベースを作っていました。このデータベースの中身を作るスタッフ――ウェブサーフィンが仕事のようなものなので「サーファー」と呼ばれていました――を6年ほどやりました。
ヤフーを辞めてから、いろいろな仕事をしてきました。ライトノベルや学会誌の校正をしたり、ケーブルテレビ局の日本法人で編成の仕事をしたり……。このころ始めた卓球のコーチはいまでも続けています。
そしてコロナ禍のあおりを食らって職を失い、途方に暮れていたときに、晶文社から声をかけてもらったんです。期せずして、25年ぶりに編集者に戻ることになりました。
『心脳問題』で文筆家の道へ
――2004年には最初のご著作である『心脳問題――「脳の世紀」を生き抜く』(朝日出版社)を山本貴光さんとの共著で出されていますね。これはどのような経緯で出版に至ったのですか。
吉川:まだ個人のウェブサイトがそれほど多くなかった1997年、山本くんと一緒に「哲学の劇場」というサイトを立ち上げて、書評を書いたり書誌情報をまとめたりしていたんですね。その「哲学の劇場」に掲載していた、脳神経科学に関する本の書評やコメントを読んでくれた朝日出版社の編集者・赤井茂樹さんから執筆依頼をいただいたのがきっかけです。
書名にもなった「心脳問題」――心と脳の関係やいかに、という哲学問題――に興味をもったのは、まともに考えようとするとジレンマに陥ってしまうような問題に対する愛好からだったと思います。ジレンマとは、ふたつの相反する事柄の板挟みになる状態をいいます。
私たちが「心」について語るときに伝統的に用いてきた語彙(痛いとか悲しいとか)と、近年の脳神経科学が明らかにしつつある語彙(ニューロンの発火とかシナプスの連結とか)とは、双方を真剣に受け入れようとすると、とうてい両立しないように思えてくる。じゃあどう考えればよいのか? という。世の中にはさまざまなジレンマがありますが、心脳問題はその中でもとびきり根本的かつ困難なものに思えました。
これは余計な話かもしれませんが、私は知的なことそれ自体というより、知的なトラブルや問題が生じる状況といったものに興味があるようです。おそらく知識欲はそれほど強くありません。学者肌というよりレポーター肌なのではないかと思います。

――その後、現在に至るまで何冊も著作や翻訳を出されています。この間も他のお仕事をずっと続けていらしたということですが、執筆に専念しようとはされなかったんでしょうか。
吉川:よく聞かれるのですが、執筆だけで食べていこうという気持ちはありませんでした。私の場合、それをやると、むしろ辛くなってしまうような気がします。書くのが大好きというわけではない、というか、書くことはほとんど苦痛以外の何物でもないですし……。兼業というのは時間のやりくりという面で難しいところもありますが、フルタイムの仕事で生活費を工面しながら執筆をするというやり方のほうが気楽で好きです。
でも、これは人によるでしょうね。書くことに身を捧げたいとか、書くこと以外のことはできるだけしたくないという人もいるでしょうし。そういう人にとっては、私のやり方は「なんで執筆と関係ない仕事を一日8時間もやらないといけないんだ」とストレスを感じるのではないでしょうか。