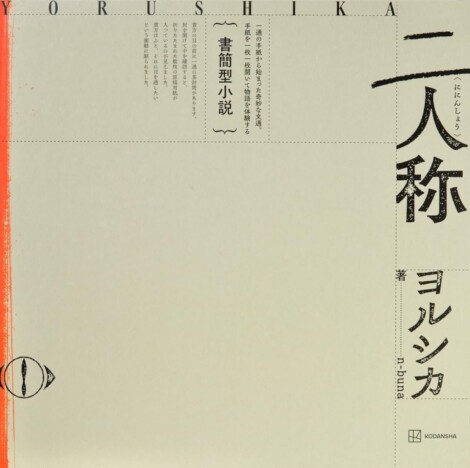連載:道玄坂上ミステリ監視塔 書評家たちが選ぶ、2022年1月のベスト国内ミステリ小説

今のミステリー界は幹線道路沿いのメガ・ドンキ並みになんでもあり。そこで最先端の情報を提供するためのレビューを毎月ご用意しました。
事前打ち合わせなし、前月に出た新刊(奥付準拠)を一人一冊ずつ挙げて書評するという方式はあの「七福神の今月の一冊」(翻訳ミステリー大賞シンジケート)と一緒。原稿の掲載が到着順というのも同じです。
いやいや本当に寒い日が続きます。オミクロンの鎮静化を待つ意味でも、しばらくは自宅読書が吉かも。本年1月分の各人ベストをお届けします。
野村ななみの一冊:宮内悠介『かくして彼女は宴で語る 明治耽美派推理帖』(幻冬舎)
日本版『黒後家蜘蛛の会』である。全六話の舞台となるのは、明治末期に実在した耽美派のサロン「パンの会」。木下杢太郎や北原白秋、石井柏亭といった面々が料理店に集い、それぞれが持ち込む謎を議論する。怪しげな事件に〈迷〉推理合戦、伏線を回収し軽快に謎を解く人物、時代の雰囲気溢れる情景描写、アシモフに倣って附された「覚え書き」……作品の構成要素すべてに魅了されてしまった。ミステリとしてだけでなく、己の才能と生き方に悩む若き芸術家たちの青春小説として読むことができる点も外せない。圧倒的な密度で描かれた一冊。
千街晶之の一冊:逸木裕『五つの季節に探偵は』(KADOKAWA)
1月は有栖川有栖や宮内悠介の新作なども面白かったので、選ぶのに少々迷った。そんな中から『五つの季節に探偵は』を選んだのは、たとえ依頼人や関係者を傷つけても真実を暴かずにいられない榊原みどりという探偵のユニークな造型もさることながら、一篇ごとに趣向が異なる手数の多さを評価したから。最先端のテクノロジーをよく扱う作家というイメージが強い逸木裕が、香道やクラシック音楽の世界を扱うとは誰が予想しただろうか。各篇のどんでん返しも切れ味抜群で、短篇ミステリならではの楽しさを存分に味わえる一冊となっている。
藤田香織の一冊:佐野広実『誰かがこの町で』(講談社)
自分が赤ん坊のときに失踪したとされる家族のことを知りたいと訴える19歳の少女と、6歳の息子を何者かに殺された女。はからずもその真相を追うことになったのは、5年前娘が自殺し妻も仕事も失った男。徐々に見えてくる「安全安心な町」のうす気味悪さが耐え難く、その苦々しさが読みながら自分にはね返ってくるのがたまらない。保身と正義。偏見と区別。トカゲの尻尾を切り落とし、鈍化することで自分を守ろうとする姿を醜悪だと思うのに、目が逸らせなくなる。江戸川乱歩賞受賞第一作にして、久々の超ど級「イヤミス」である。