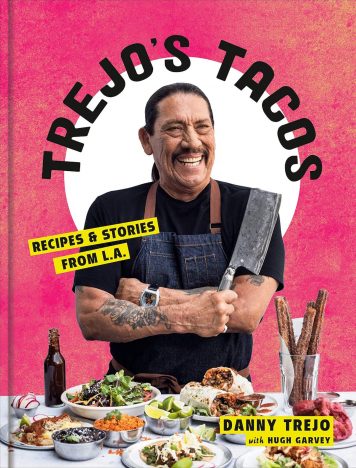児童文学に学ぶ、“ジェンダー問題” 子どもたちに今、伝えるべきメッセージとは?

「どっかの政治家が『ジェンダー平等』とかってスローガン的にかかげてる時点で、何それ、時代遅れって感じ」というセリフが物議を醸している報道ステーションのウェブCM。好意的に解釈すれば「ジェンダー平等なんて、もはやわざわざ言うまでもなく当たり前に浸透している」ということだったのだろうが、実際問題、浸透なんて全然していないし、若い世代が男女区別をあまり感じなくなってきているのだとしたら、それは不平等に疑問を抱いた先人たちが何度も何度もくりかえし「言う」ことによって、新しい価値観を醸成していったからにほかならない。と、ポプラ社から刊行された小説『わたしの気になるあの子』(朝日奈蓉子)を読んで思う。
当たり前からこぼれ落ちて見過ごされている人たち
『わたしの気になるあの子』の主人公・瑠美奈は小学6年生。1年生の弟・たけるの入学式にあわせてやってきた祖父は、たけるを跡継ぎだともてはやし、女性が強い態度に出るのをいやがる、典型的に保守的な老人だ。「今時、こんなじいさん、いる?」と思うほどあからさまな男尊女卑に、冒頭からイライラしてしまうのだけど、よく考えてみれば失言で世間を騒がせている男性たちは、孫どころかひ孫がいてもおかしくない年代だ。瑠美奈のクラスメートでとにかく“女の子らしさ”にこだわる沙耶も、発言の端々に保守的な祖母の影響が感じられる。
「そんなのおかしい」と強く言う人がいなければ、彼女たちはその価値観を“そういうもの”として受け取ってしまう。瑠美奈は祖父のことがきらいだけれど、沙耶はたぶん、祖母が好きだ。好きな人の言うことは、信じたい。瑠美奈だって、大好きな母や父が反論せずにいることを、覆してまで異議を唱える勇気はない。そうやって、みんな、黙る。黙って、不平等な価値観が脈々と受け継がれていってしまう。
だが物語ではそこに、詩音が現れる。突然、ボブカットを坊主頭に変えて、スカートではなくズボンを履いて登校してきたクラスメート。“女の子らしさ”から逸脱した詩音は孤立し、いじめに近い仕打ちを受けるけれど、わけも話さず、不機嫌そうに口を閉ざしたまま。そんな彼女に戸惑いながらも、瑠美奈は興味を惹かれ、少しずつ歩み寄っていく。
詩音が坊主にしたのは、理不尽な校則でしばる女子高の体質に反抗した姉に倣ってのことなのだけど、それを読んだときふと思い出した情景があった。中学1年生のとき、やはり女子校で先生に身なりを注意された先輩が、翌日、坊主頭にして登校してきたのだ。あわてふためく先生たちを見て、先輩は笑っていた。……衝撃を受けた。女の子が坊主になる、という選択肢があること。坊主になったところで、先輩のかわいさとカッコよさはなにひとつ揺るがないということ。そうやって、自分を貫いて戦うことは、誰しも等しく許されているのだということ。そのすべてに。
作中では、詩音もその姉も、もうちょっと苦境に立たされる。けれど、瑠美奈が詩音に触発されて“自分”を芽生えさせたように、物語に書かれていない場所で、彼女たちに勇気をもらった少女たちはいたはずだ。もちろん、読者のなかにも。
だから「言う」こと、そして「知る」ことが何より大事なのだ。この世には、当たり前からこぼれ落ちて見過ごされている人たちがいること。自分だって、いつその立場に陥るかわからないくらい、その境界線は曖昧だということを。