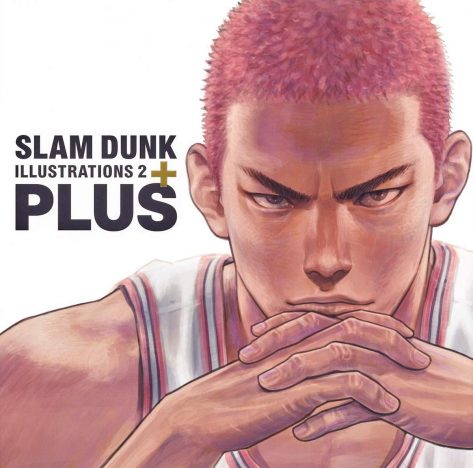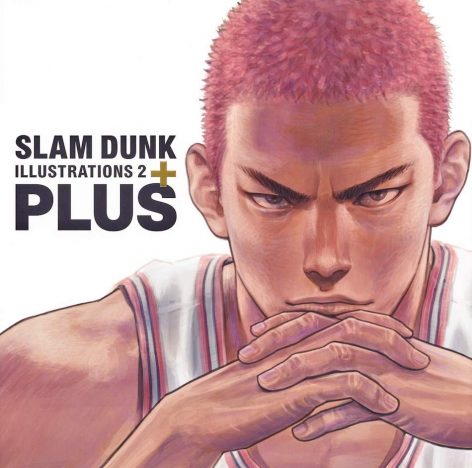『SLAM DUNK』は“漫画のタブー”に挑んだ作品だった? 絶対的存在になった理由とその影響
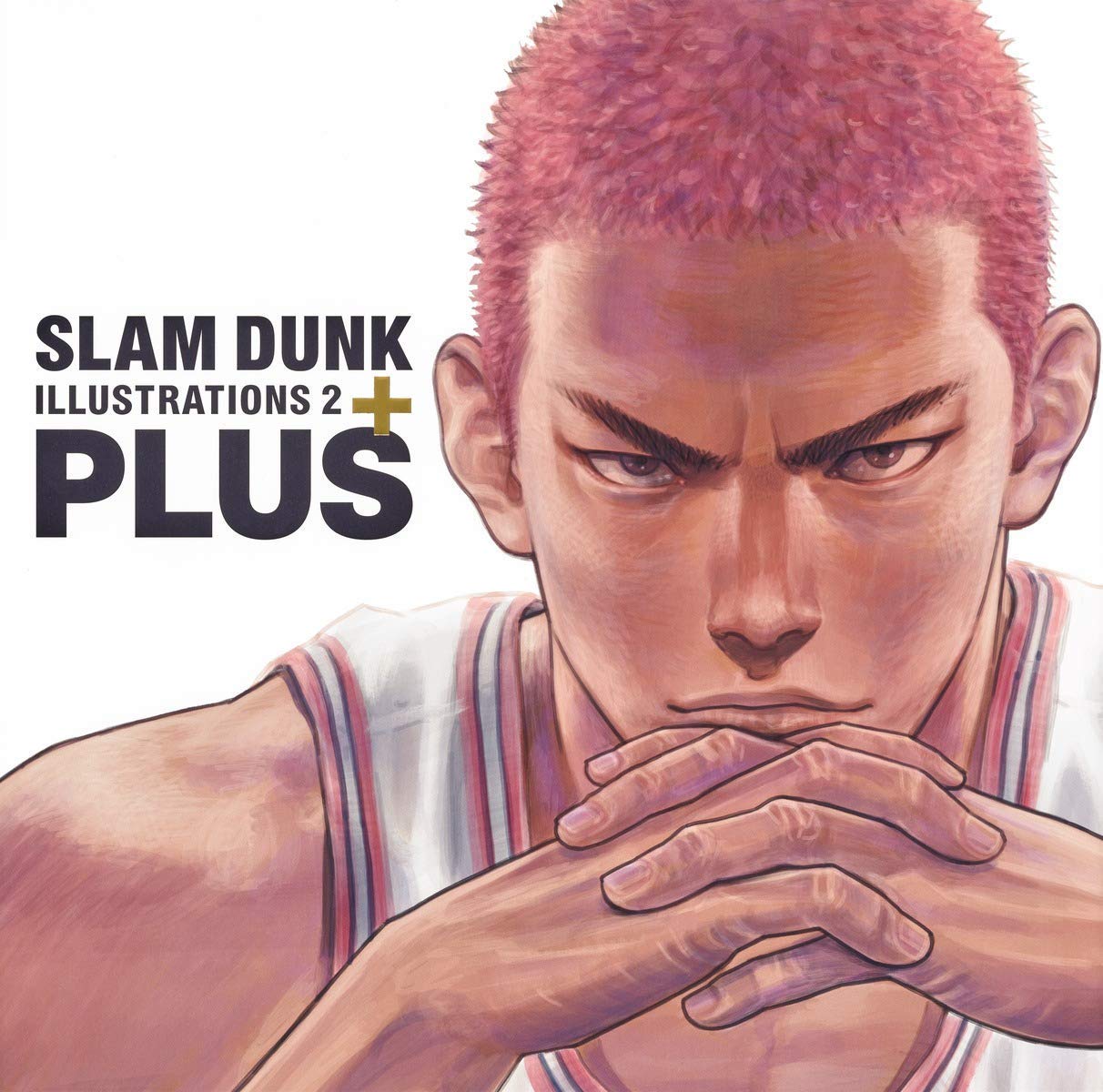
名作漫画の遺伝子
井上雄彦の『SLAM DUNK』は、『週刊少年ジャンプ』の1990年42号から1996年27号まで連載された、バスケットボール漫画の金字塔である。単行本の国内累計発行部数は1億2000万部以上といわれるこの怪物的ヒット作について、いまさらどんな内容かを説明する必要もないと思うが、念のために書いておくと、湘北高校に入学した不良少年の桜木花道が、ひょんなことからバスケットボール部に入部することになり、そこで才能を開花させていくある種のビルドゥングスロマン(成長物語)の傑作だ。
連載終了からおよそ四半世紀。いまなお、バスケットボール漫画といえば、この『SLAM DUNK』のタイトルを思い浮べる人も多いと思うが、なにゆえ同作はそこまでの絶対的な存在たりえたのか。それを本稿では考察してみたいと思う。
まず、考えられるのは、キャラが立っている、絵が良い、物語がよく練られている、ということだが、その条件を満たしている漫画なら他にもたくさんあるだろう。「友情・努力・勝利」という『少年ジャンプ』のヒットの法則(3大原則)を取り入れている点についても同様だ。漫画表現的には、例えば最終巻の湘北高校対山王工業戦における、セリフやナレーションを一切排除して絵だけで見せていく描写などはたしかに圧巻だが、その種の表現もそれまでのスポーツ漫画でまったくなかったわけではない(例えば、『がんばれ元気』の堀口元気対関拳児戦の描写などが、20 ページに渡りサイレントの表現で描かれている)。
また、三井寿の「バスケがしたいです……」から、桜木花道の「左手はそえるだけ」にいたるまで、さまざまな名ゼリフが心に残る作品でもあるが、それゆえにヒットしたのかと問われたら、それだけではあるまい、と答えるほかない。さらには、アニメ化で広く世に知られるようになったから売れた、という人もいるかもしれないが、そもそも原作がそれなりにヒットしていたからアニメになったわけであり、それ(=アニメ化)はあくまでも「より多く売れた要因のひとつ」程度に考えていたほうがいいと思う。
「バスケットボールはこの世界では一つのタブーとされている」
では、なにゆえ『SLAM DUNK』は、バスケットボール漫画を象徴するような絶対的な存在になりえたのか。それは、(文字に書いてしまえば当たり前のことのように思われるかもしれないが)同作以前にバスケットボールを題材にした漫画のヒット作がほとんどなかったためだと思われる。異論のある方もおられるかもしれないが、個人的には、『SLAM DUNK』以前のバスケットボール漫画のヒット作といえば、六田登の『ダッシュ勝平』くらいしか思いつかないのだが、こちらはどちらかといえばコメディ色の強い作品であり、あまり比較の対象にはならないだろう(ただし『ダッシュ勝平』は、最終章でいきなりシリアスな展開を見せるのだが)。
井上雄彦自身も、単行本の最終巻の「あとがき」でこんなことを書いている。
確かに連載開始当時はバスケットボール漫画は数えるほどしかなかったし、日本ではまだメジャーとはいいがたいスポーツでした。連載前のネーム(ちゃんとした絵を入れる前の絵コンテ)を作ってるときも編集者から「バスケットボールはこの世界では一つのタブーとされている。」と何度か聞かされました。コケるのを覚悟しろという意味です。(たぶん)
それでもバスケットボール漫画を描くということは、少なくとも自分にとってはごく自然なことでした。
『SLAM DUNK』31巻(集英社/ジャンプ・コミックス版)より
つまり、井上が新連載を始めるにあたり、狙いを定めたのがほとんど誰も手をつけていない「穴場」的なジャンル――さらにいえば、彼にとって情熱を注ぐことのできるマイナーな題材だったからこそ、結果的にまだ誰も見たことのない「新しいジャンルの漫画」を開拓できた(そして、その「新しさ」がヒットにつながった)のだとは考えられないだろうか。
これは、同じような条件下で始まった高橋陽一の『キャプテン翼』が、後にサッカー漫画のジャンルを牽引する革命的な作品になったことを考えても、ある程度は説得力のある見方だと思うが、いかがだろうか(『キャプテン翼』連載開始時、日本ではサッカーというスポーツはもちろん、サッカー漫画もいまのようなメジャーな存在ではなかった。高橋自身も、個人的に一番好きなのは野球なのだが、あえて、当時ほかに誰も描いていなかったサッカー漫画というジャンルに注目した、というような発言をいくつかのインタビューでしている)。
「偉大なもの、革命的なものは、ただマイナーなものだけである」という、ドゥルーズ=ガタリの本(『カフカ〜マイナー文学のために〜〈新訳〉』/宇野邦一訳/法政大学出版局)の有名な一節をここで引用するのも野暮な話かもしれないが、でも私がいいたいのはまさにそういうことで、いつの時代でも常に新しいムーブメントはマイナーな場所から生まれるのである。
さて、そこで次に考えたいのは、この『SLAM DUNK』のような、絶対的な存在が誕生した(してしまった)ジャンルの作品を、後に続く漫画家たちはどう描くべきなのか(あるいは手を出すべきではないのか)、という問題だ。これについてはおもしろい現象(?)があり、(私はかつて某週刊漫画誌の編集者だったから、裏事情をよく知っているのだが)凡庸な編集者というものは、あまり深い考えもなしに「○○(=圧倒的に売れた作品)と同じような漫画を描け」と新人漫画家にネタを振りがちであり、一方のいわれた方(漫画家)は、たいてい腰が引けるものだ。要するに多くの編集者は、常に柳の下の二匹目のドジョウを狙っており、漫画家のほうは何かの二番煎じと思われるような作品はなるべく描きたくない、というわけである(例えばいま、編集者から「日本刀で鬼と戦うヒーローの漫画を描け」といわれた新人漫画家の気持ちを考えればわかりやすいだろう)。
ちなみにこれまで私は、インタビュアーとして何人かの漫画家から、新連載を始める際、同じジャンルの先行作品に時代を象徴するような名作があった場合、どんなことを考えたかを聞いたことがあるので、いくつか以下に引用してみよう(そのうちのひとつはまさに『SLAM DUNK』が絡んだ例である)。
【ボクシング漫画『がんばれ元気』を描いた小山ゆうの発言】

いかに『あしたのジョー』から離れられるかというのが、最初にして最大の問題でしたね。あとボクシングじゃないけど、「父と子の話」という意味では『巨人の星』も好きでしたからね、そういう過去の名作とも違うものにしないといけないわけで。だからたとえば、星飛雄馬と違って元気はお父さんからスポーツを無理矢理やらされてるわけじゃない、とかね。
一方、ジョーというのはボクシングと出会わなければチンピラになってたような青年でしょう。そういうタイプのキャラと違う主人公はどういう人間だろうと考えたら、わざわざボクシングなんかしなくてもいい環境にいるのに、あえてそれをする優等生じゃないかと思ったんですよ。それと、従来のボクシング漫画は主人公が破滅に向かう作品が少なくないんだけど、『がんばれ元気』はひたすら主人公が登り詰める物語にしようと考えました。その代わり相手を叩きのめしてその人生も背負っていくというね。
『小山ゆうロングインタビュー』第2回/漫画家本vol.13『小山ゆう本』(小学館)所収より
【柔道漫画『帯をギュッとね!』を描いた河合克敏の発言】

柔道物を描くと決めたものの、小林まこと先生の『柔道部物語』と浦沢直樹先生の『YAWARA!』という同じジャンルの傑作が、すでに同時代の作品として存在しているわけです。このふたつには勝てないかもしれないけど、少なくとも肩を並べるくらいのものじゃないと、あとから出て来た作品としては意味がないわけですよ。
で、そうした先行作と被らないようにするためにはどうすればいいかと考えてて当時、上條(淳士)先生が面白いと言ってた松苗あけみ先生の『純情クレイジーフルーツ』を読んだら、主人公が1人じゃなくて4人の女子高生のグループがみんな主人公って話で。それを見て「5人の柔道少年のチームが主役で団体戦を戦う話」というアイデアが浮かんだんです。
『河合克敏 語り下ろし7万字超ロングインタビュー』第1回/漫画家本vol.5『河合克敏本』(小学館)所収より
【バスケットボール漫画『I’ll〜アイル〜』を描いた浅田弘幸の発言】

ただ、『I’ll〜アイル〜』についても『ヨシオ』(『BADだねヨシオくん!』)と同じで、最初あまり乗り気じゃなかった。NBAブームで、『SLAM DUNK』が売れてるから、バスケ漫画を描けってはっきりと編集者から言われました。(中略)最初「できません」とお断りしたんですけど、デビューからお世話になってた編集さんに「君らしくやればおもしろくなる」とも言われて。どうやったら自分らしいバスケ漫画が描けるかを考えました。そのうちに、だんだん試合や特訓がメインのスポーツ漫画でなく、日常生活の描写が多めの部活の青春群像劇だったら僕にも描けるかもしれないし、描きたいなと思うようになったんです。
『漫画を描いていない時も漫画家は漫画家』(後編)/『クリエイターズ・サバイバル アーティストの戦略教科書 第1回 浅田弘幸』(いちあっぷ)より
これらの発言から自(おの)ずと見えてくるのは、「隙間を狙うべし」というクリエイティブの鉄則ではないだろうか。小山も、河合も、浅田も、それぞれのジャンルに君臨している過去の名作とは違った切り口(=隙間)を自分なりに考え、結果的にそれが彼らの作品だけが持つ「新しさ」になった。当たり前の話だが、編集者に「○○みたいな漫画を描け」といわれて、そのまま○○のコピーを描くような人間は、「作家」ではあるまい(ただし、そうした劣化コピーの漫画が結構売れたりもするという、悲しい現実もあるのだが……)。いずれにせよ、この「隙間を狙うべし」という鉄則は、かつて井上雄彦や高橋陽一がマイナーなジャンルのスポーツに目をつけたのと、基本的には同じ考え方によるものだといっていい。