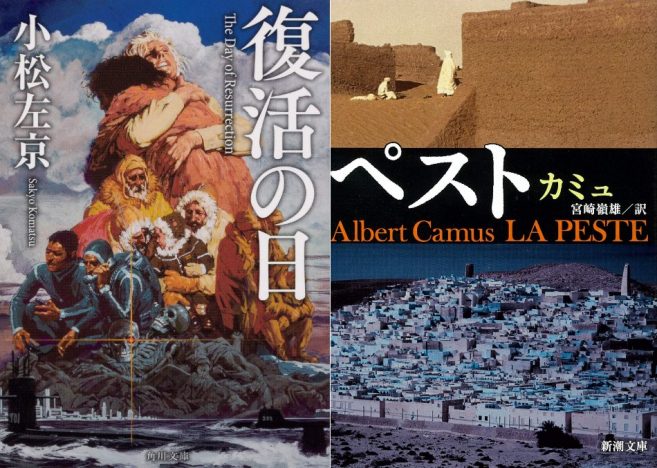福嶋亮大が語る、パンデミック以降の倫理と表現 「隣人愛という概念は、改めて注目すべき」

いかにしてコナトゥスと戦うか
ーー距離を破壊するような価値観を提示するものとして、どんな表現が考えうるでしょうか。

福嶋:ちょっと間接的にお答えしますと、病気にも時代性があるんですね。特に平成後期には、うつや発達障害のように感染しないタイプの病気が目立つようになった。文学もそれに連動しています。たとえば、村上龍は平成前期には『ヒュウガ・ウイルス』(1998年)で感染症を描いたけれども、平成末期の『MISSING』(2020年)では抑うつ的な作家を主人公にしています。
韓国生まれのドイツの哲学者ビュンチュル・ハン(Byung-Chul Han)は『燃え尽き社会(Müdigkeitsgesellschaft)』(花伝社より刊行予定)という本で、病気のタイプとして感染(infection)と梗塞(infarction)を分けていて、現代社会ではうつや発達障害を含めて、後者が優勢になっていると述べています。平成後期の文学的想像力も、おおむね「梗塞」タイプですね。しかし、今回のパンデミックはそれをすっかり引っ繰り返したところがある。今後は感染と梗塞、この二つのタイプの交差するところで、面白い表現が出てくるかもしれません。
ただ、日ごろ批評を書いていて思うのは、小説というのはどうしても個人の内面的な「梗塞」に向かいがちで「感染」を捉えるのは難しいということです。逆に、映画は初期から「感染」を撮ってきた。セルゲイ・エイゼンシュテイン監督の『戦艦ポチョムキン』に「オデッサの階段」という有名なシーンがありますね。恐怖が伝染し、動作が伝染し、群衆がパニックになる。こういう場面は映画的にはうまく処理できますが、小説的に効果をあげるのは困難です。いずれにせよ、病気のタイプからジャンルの性質なり時代の特徴なりを考えるのは、批評のプログラムとして面白いと思います。
--文学は梗塞的な表現が得意とのことですが、特に象徴的だと考えている作品は。

福嶋:平成文学との関わりで言うと、意外に大正から昭和への転換期は面白い問題を含んでいます。この時期には、内向的に自分の異常性を発見するような小説が多い。例えば、肺結核を患っていた梶井基次郎や堀辰雄は象徴的だと思います。興味深いのは、彼らは1918年のパンデミックのことは眼中になく、結核の話しかしていないことです。そして、結核は感染症ですが、彼らの表現はむしろ内的な「梗塞」に近いように見えます。
ーーその大正時代の精神は、平成の精神にも近いものがあると。
福嶋:今夏に平成文学論の本を出すことになっていますが、僕はそこで大正と平成をアナロジー的に結んでいます。大正にはデモクラシーの運動があり、ユートピア文学があり、大震災があり、インターナショナリズムが唱えられた。平成もインターネットによるデモクラシーがあり、ディストピアのモチーフが流行り、二度の大震災があり、グローバリズムが唱えられた。逆に、昭和あるいは令和に入ると、インターナショナリズムあるいはグローバリズムの限界が言われるようになる。パンデミック後の世界恐慌の可能性が語られるという意味でも、令和初期は昭和初期と似ています。梶井は「桜の樹の下には死体が埋まっている」という言い方で、当時の不穏な世界情勢を暗示的に語っていたと思います。
--表現のアップデートを考える上で、参照にしたい本はありますか。
福嶋:社会学者のウルリッヒ・ベックが言っていることですが、気候変動であれテロリズムであれ金融恐慌であれ、現代のリスクに対応するためには、グローバルな法を作る必要がある。その主張の核にあるのは、国家が自国を守ろうとするならば、まずは自国の主権をある程度譲り渡さなければいけないというパラドックスです。これは先ほどいったレヴィナスの隣人愛にも通じる考え方ですね。現実には各国は防壁をどんどん上げているわけですが、それではグローバルな問題を解決できない。
付け加えると、レヴィナスが過激なのは、コナトゥス(自己自身を保全しようとする欲動や努力)を解除しないと、倫理は起動しないと言っていることです。レヴィナスはこのコナトゥス、つまり自己保存欲求を相対化するために、隣人愛をもってくるのです。これは別に自己犠牲を訴えるものではなく「存在すること」を第一目標としないような倫理が要るのだ、という話ですね。個人にせよ、集団にせよ、おそらく今後は自己保存の要求が露骨に出てくるでしょうし、国家もそこに便乗してくる。そうすると、極端な管理社会化にも抵抗できなくなる。その意味でも「コナトゥスへの抵抗」というレヴィナスの議論をどう引き継ぐかが、パンデミック後の大きなプログラムになると思います。
■福嶋亮大
1981年京都市生まれ。文芸批評家。京都大学文学部博士後期課程修了。現在は立教大学文学部文芸思想専修准教授。文芸からサブカルチャーまで、東アジアの近世からポストモダンまでを横断する多角的な批評を試みている。著書に『復興文化論』(サントリー学芸賞受賞作)『厄介な遺産』(やまなし文学賞受賞作)『辺境の思想』(共著)『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』『百年の批評』等がある。