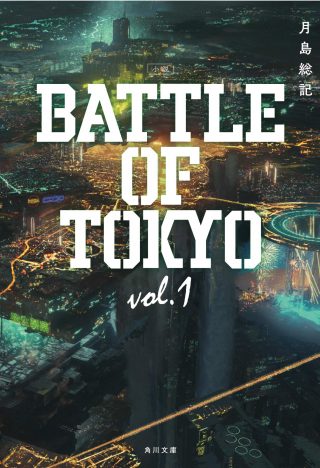小林直己が演じた“禎司”と小説の“禎司”の違いは? 原作『アースクエイクバード』を読む

筆者は、映画の中の禎司は、たくさんの小説や映画の中で女性が担ってきた「オム・ファタル/ファム・ファタル(運命の相手)」なのではないかと思っていたのだが、小説の中の禎司は、それとは別のことを象徴しているように思えた。単に「その実態が見えない」だけでは、「オム・ファタル/ファム・ファタル(運命の相手)」ではなく、もっと強い何かが存在している必要があるのかもしれない。
そう思えた理由はいくつかあるが、小説の中のルーシーは、雨の中でロマンチックな出会いをしたからこそ、禎司の美しさだけを見て、彼の言葉や意思を「無」にしてしまうような、ある意味盲目的な部分も持っている。それは、多くの男性が、女性を女神のように崇めるからこそ、皮膚の下にある思いや意思を見ないできたのと似ている。一方でルーシーは、禎司の表面を女神のように崇めるからこそ、彼の中身に対しては辛辣で「ありふれた男」であることも見抜いているのかもしれない。そして「ありふれた男」は、「ありふれた罪」と重なることで、より「雨」のような存在になっていく。それは、小説が禎司にもルーシーの側にある危うい感情に、目をそらさずに焦点をあてた結果でもある。
本作を見て、村上春樹の小説を思い出したという感想も見られたが、小説版のほうがその色合いは濃いのではないか。小説の禎司は、ルーシーの中で、ときおり降ってくる雨のような存在として、甘い感傷とともにこれからも蘇っては消えて、また蘇っては消えてというようなことを繰り返すのだろう。
映画の中のルーシーは、冷静に禎司を見ているし、禎司もルーシーのことを知りたいと思い会話もしている。彼の言葉も声も思いだせるほどはっきりと聞いている。しかし、だからこそ禎司の意思を持った行動や、その裏にある思い、多くは見えないが確実に存在している過去のトラウマに、どんどん揺さぶられ、冷静なはずなのに徐々に自分を見失っていくし、同じように冷静に映画を見始めた観客もルーシーの気持ちを追体験をしてしまう。小林直己が演じた禎司は、甘い感傷で終わってしまうような存在ではなかった。
だからこそ、ルーシーにも映画を見た観客にとっても、禎司を優しい雨のようなはかない存在と見るのではなく、忘れようのない「オム・ファタル/ファム・ファタル」として記憶してしまうのかもしれない。
映画版の中で雨が印象的に出てくるシーンがある。終盤で家を訪ねてきたリリーとルーシーが感情を高ぶらせ口論し、その後帰っていくリリーを、ルーシーが傘もささずに追う場面であった。その雨は、小説に出てきた雨とは違い、ルーシーやリリーの体を容赦なく濡らすほど激しいものであった。
■西森路代
ライター。1972年生まれ。大学卒業後、地方テレビ局のOLを経て上京。派遣、編集プロダクション、ラジオディレクターを経てフリーランスライターに。アジアのエンターテイメントと女子、人気について主に執筆。共著に「女子会2.0」がある。また、TBS RADIO 文化系トークラジオ Lifeにも出演している。
■書籍情報
『アースクエイクバード』
著者:スザンナ ジョーンズ
翻訳:阿尾正子
出版社:早川書房
発売:2019年11月6日
価格:880円(税込)