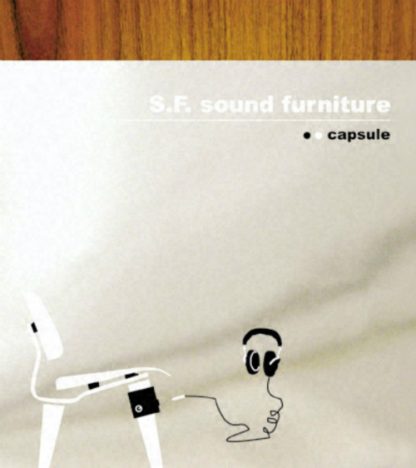CAPSULE 中田ヤスタカを紐解く“7つの質問” DTM先駆者が振り返る、特異な制作スタイルが常識になるまで

中田ヤスタカとこしじまとしこによる2人組ユニット、CAPSULE(カプセル)が6年ぶりに新曲「ひかりのディスコ」をリリースした。今年、結成20周年を迎えたCAPSULEは、パソコンとDAWソフトウェア完結による音楽制作の手法を世に広く一般化させたユニットだ。コンピュータミュージックの未来像をビジョンとし、トラックメイカー文化を広めたオリジネーターである。
そんなCAPSULEがヒストリーを重ねたことで生まれたアイデアが、自分たちのサウンドの過去と未来を融合すること。新曲「ひかりのディスコ」のリフには、10年前のナンバー「WORLD OF FANTASY」のフレーズがサンプリング感覚でフックアップされている。
MVでは、こしじまとしこが80年代に一世を風靡したHondaプレリュードを運転。カセットテープのインサートシーンや、腕にはCASIOデータバンク、足元にはオニツカタイガーが見える。しかしながら、80年代当時には存在しなかったレインボーブリッジが、まさに“ひかりのディスコ”状態で輝く。ノスタルジーと未来から生まれた少し不思議な近未来の風景。アンビバレンツな日本らしいポップカルチャーが、CAPSULE流のSFセンスで時間軸を超えて展開されていく。
さらに本作は、中田ヤスタカが敬愛する日本が世界へ誇るSF漫画家、弐瓶勉(にへいつとむ)総監修による劇場アニメーション映画『シドニアの騎士 あいつむぐほし』(全国映画館で6月4日公開)へ書き下ろした主題歌としても話題だ。考察ポイントが豊富な新曲「ひかりのディスコ」の話はもちろん、中田ヤスタカに変わりゆく音楽シーンの最前線や、トラックメイカーの心得など“中田ヤスタカに聞く7つの質問”として聞いてみた。(ふくりゅう/音楽コンシェルジュ)
「CAPSULEでは常に“デビューアルバム”を作り続けたい」
ーーCAPSULE、新曲6年ぶりなんですね。
中田:そんなにサボっていた気はしないんですけどね。あ、言い方が悪いですね(笑)。
ーーははは(笑)。アルバム『WAVE RUNNER』が2015年2月だったので、それ以来という。
中田:早いですね。
ーーその間、数々のプロデュースや、中田ヤスタカ名義でのソロアルバムやいろんな参加プロジェクトがありました。
中田:ちょっと旅に出ていたような感覚ですね。音楽的にはいろいろ作っていたので、6年はいつの間にかって感じでした。
ーーあらためて中田さんにとってCAPSULEとはどんな存在ですか?
中田:10年ほど前からCAPSULEとしての活動をだんだんしづらくなってきたと感じていました。CAPSULEって、自分が好きな、聴きたい音楽を思い立ったときに作ってリリースするユニットなんです。
ーー自分たちのユニットだからこそ制限や制約がないということですね。
中田:今でいえば、YouTubeに作品を投稿する、みたいなことに近いのかもしれないですね。
ーーあ、それはわかりやすい。
中田:そんな活動を続けていたはずなんですけど、CAPSULEを動かす流れみたいのができてしまって。海外のフェスに誘ってもらうなどの稼働も含めて、それらのステージ上の自分と、音楽制作者としての自分のバランスの難しさを感じながらの中で、一旦ソロ活動をやってみたんです。コラボなど中心にしながら、チャンネルを切り離そうとしてみた期間でした。とはいえ、だんだんとCAPSULEを必要としている空気感が整って、自然と今に至る感じなんです。
ーーなるほど。2021年のCAPSULEなのですが、新曲「ひかりのディスコ」という楽曲でエレクトロやEDM以降のセンス、“なつかしいあたらしさ”という感覚を提示してくれたのが嬉しかったです。
中田:ふくりゅうさんだったらわかると思うんですけど、前作アルバム『WAVE RUNNER』(2015年)は、アルバム『L.D.K. Lounge Designers Killer』(2005年)のときの気持ちみたいな感じなんですよ。当時、フェスとかDJの活動もあった流れの延長線上で音楽を作っていたんですけど、他にやりたいことがあっても、出演する場所が1、2年先まで決まっていることで、フェス向きな内容を作らざるえないという難しさを感じていたんです。もちろん自発的なんですけどね。今は枠組みを考えずに音楽だけに集中できるようになりました。
ーーコロナ禍に入ったことで、逆に創作の切り替えポイントを通過できたんですね。
中田:気持ちとしては常にデビューアルバムのような作品を作りたいんですよ。そんな感覚でCAPSULEは活動したくって。
ーーたしかに、「ひかりのディスコ」を聴くとフレッシュさを感じるんです。
中田:そうかもしれない。CAPSULEは、常に楽しさが大事かな。
ーーでは、ここから今回のインタビューの本題となる“中田ヤスタカに聞く7つの質問”に入りますね。
中田:はい、よろしくお願いします。
<質問1>デビューからDTMスタイルを貫き通した理由
2021年、時代は完全にDTM(※デスクトップミュージック、パソコンを利用して楽曲制作をおこなう音楽制作手法の総称)全盛期となりました。そんな時代を予言していたかのように、中田ヤスタカさんは音楽活動初期から自ら作詞作曲、そしてアレンジやミックスまで一気通貫で作品を手がけるトラックメイカーとして活躍されています。なぜ、いまのようなスタイルをデビュー当初から貫き通してこれたのでしょうか?
中田:僕はコンピュータミュージックにアイデンティティーを感じています。コンピュータのみでレコーディングが完結するということをやりはじめたのは、少なくともプロとして活動しているミュージシャンの中では相当早かったと思います。それは作業上面倒なこともわかっていて、いわゆるアーリーアダプター的なところがあって。効率性や楽ができるからPCを導入するという発想ではなかったんです。コンピュータを使うこと自体が楽しくて、多少不便でもコンピュータを使うことでしか生み出せない音楽を、自分の手でコントロールするという楽しみが強かったんです。
ーー今や、VOCALOID文化圏、TikTok文化圏、YouTube文化圏でDTM使いによる音楽は先んじて流通する時代ですけど、中田さんはDTM使いのイノベーターですよね。
中田:僕がソフトオンリーで、PC完結の制作スタイルに切り替えたときは、まだそうでない方が簡単だったんですよ。あと、PCをネガティブな意味でしょうがなく使うプロも多かった時代で。本当は大きいスタジオを借りたいんだけど、しょうがなく代用する、この予算だとPCで済ませておこうかなみたいな。でも、僕はポジティブにとらえていました。
ーーそれはどうして?
中田:自分が好きな時間に好きなだけ作業ができるという、精神的な面も含めて利点があったんですよ。パーソナルな感覚ですよね。もちろん、まだPCの処理能力も低く、固まったりして大変だったんですけどね(苦笑)。でも、自作PCでなんとか動かすみたいなことが、自分には合っていたんです。今は、機材が進化しましたけど。思えば、苦労しながら作業することすら楽しかったんですよ。
ーー音楽史における、昭和黎明期の職業作家(作詞家、作曲家、編曲家)による分業時代、70年代以降のシンガーソングライター時代、80年代以降にはバンド時代を経て、90年代以降は広告代理店を巻き込んだ音楽バブルが花開きました。そんななか、中田さんは自分の頭の中にあるサウンドを第三者を通さずにストレートにアウトプットができる自己完結型の“トラックメイカー”という表現スタイルを2000年代に確立しました。現在活躍する後発クリエイターへの影響も大きいです。現在のシーンを予見されていたのでしょうか?
中田:今でも続けているこのやり方を、僕はずっと普通だと思っていたんですよ。それこそ、今ではプロの世界でもDTMは普通の制作スタイルになったと思います。でも、当時は常識ではなかったんですよね。まず、2001年のCAPSULEのメジャーデビューでは、自分が非常識だったことを知ることからスタートしました。それこそ、アーティスト本人がミックスまでやる作品がメジャーでほとんど流通していない時代だったので。ましてや新人に任せるなんてデモテープまで、というイメージがあったんでしょうね。それは不満でした。変えていきたいと思いました。なので、2000年代は半分怒りみたいなモチベーションで音楽を作っていました。
ーーそれはパワーとなりますね。
中田:ちなみに、分業を否定しているわけではないんですよ。アーティスティックなエンジニアの方や専門的なミュージシャンの必要性は大事だと思っているので。とはいえ多様性じゃないですけど、みんな同じじゃなくてもいいんじゃないかなと思っていました。今だったら、たとえば歌い手さんがメジャーデビューするとしたら、これまで自分で録音して発表していたのに、いきなり大きいスタジオで大人に囲まれてマイクの前で歌うなんて変じゃないですか? そう思える多様性が僕のデビュー時にはなかったんですよ。それぞれの作り方が認められるように変えていきたいなと思っていました。