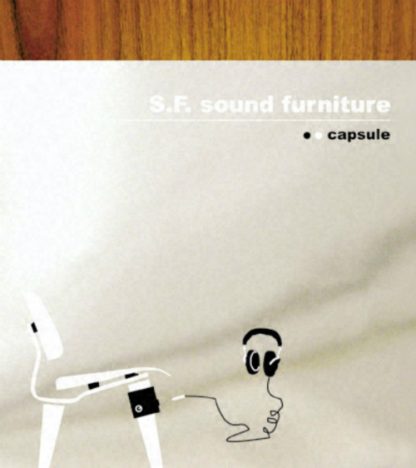CAPSULE 中田ヤスタカを紐解く“7つの質問” DTM先駆者が振り返る、特異な制作スタイルが常識になるまで

<質問2>中田ヤスタカの音楽に影響を与えたモノ
中田さんは、アイデンティティーとして“作品が主役という考え方”をよく過去の取材時にお話しされていたのですが、中田ヤスタカさんがこれまで影響を受けてきた表現者、アーティストについて教えてください。
中田:僕の場合は、たとえばファンとして音楽アーティストを追い求めるということを青春時代含めてやってこなかったんですね。よく“どんな音楽聴いているんですか?”と聴かれるんですけど説明するのが難しいんです。僕、音楽のリスニングのファンじゃないので、音楽を作ること自体が楽しみなんです。聴くということが、そこまで楽しみの中になかったんです。じゃあ、どんなものに影響を受けているかといえば、自分が楽しんでいる時にかかっていた音楽。それは映画だったりゲームだったり、ときには場所だったり。たとえば20歳前後の頃は、毎日原宿に自転車で行ってたんですけど、そんなときに自分の好きな服が置いてあるお店でかかっていた曲が自分の中のインプットになっていたんです。そこで“この曲なんですか?”、“どんなCDなんですか?”とは聞かないんです。“あ、なんかカッコいい曲がかかっていたな。自分も家に帰って早く曲を作ろう!”。そう思うんですよ。
ーー根っからの作り手なんですね。
中田:だと思います。なので、自分の曲を他の人の曲とスピーカーで聴き比べたりしないし、“この曲カッコいい”という印象をもらうこと自体がインスピレーションになるっていう。実際、印象を受けて自分が作った曲を、元ネタとなるサウンドとスピーカーで聴き比べたら全然違うものになると思うんです。感覚的なものなんですよね。
ーーうんうん、わかりやすい。影響といっても、具体的なコードやメロディ、歌詞の引用には結びつかないんですね。
中田:いまでも、そういう聴き方ってあると思うんですよ。たとえば好きなアニメを観て、劇中でかかっていた曲も含めて好きになるというか。それが僕の場合は原宿のお店だったり、ゲームだったり。小さい頃からゲームばっかりしてたんですよ(笑)。そういえば、ゲームから知識を得ることも多かったですね。ゲームとして終わらない、いろんなことを教えてくれるゲームってあったんですよ。高校生の頃にプレイステーションが発売されて、それまであまり洋ゲー(※海外生まれのゲーム)を知らなかったんですけど、デザインやサウンドで海外の雰囲気を自然と知ることになったり。それもインプットなんですよ。
ーーゲームカルチャーはテクノロジーのスピードが速くて、VRだったり現実を凌駕する方向へ進んでいますよね。
中田:そうですね。ある程度技術が通り越すと僕は逆にコンプレックスになるんじゃないかなと思っています。
ーーどういうことですか?
中田:アナログコンプレックス、ハードウェアコンプレックス的な。2021年以降、バーチャルネイティブな時代となると思うんですけど、いろんなものがリアルにあるのと変わらないことをバーチャルに体験していくじゃないですか? 音楽機材もそうなんですけど、たとえばPC画面の中にバーチャルなんですけどVST、『Virtual Studio Technology』というソフトがあって。たとえば、さらに進化して実際のスタジオ環境とまったく変わらなくなったときに、逆に実際のものを使っていないというコンプレックスが出てくると思うんです。
ーーああ、はいはい。
中田:モノを持ってみたいという欲が湧くんじゃないですかね?
ーーなるほど。あえて、アナログ盤や紙の書籍、カセットテープに新鮮な愛着を持つ学生やティーンも増えていますもんね。
中田:かつてでいうデジタルですらアナログな感覚になっている時代だと思うんです。デジタルとわからないデジタルも増えていくと思います。高解像度化して、すべてがハイレゾリューションの世界に飲み込まれていったら、人間としては区別がつかなくなりますよね?
ーーVRゴーグルで見る景色も8Kになったら、人間の視野と変わらないようになるといいますね。
中田:進化の方法としては正しいんですけど、結局新しいものが出るとそれを否定する人もいるし、受け入れる人もいるじゃないですか。でも、音楽業界ってレコードなどメディアを通じて音楽を楽しむようになったのって意外と最近なんですよ。レコードが流通するようになって100年ちょっとぐらいでしょ?
ーーCDなんて80年代後半に普及しはじめたぐらいで。
中田:とはいえ、音楽自体の歴史は比べ物にならないぐらいとても長いんです。そんななかで起きている、音楽メディアにおける新しい潮流と古い権威とのバトルって、冷静に考えてみるとそんなに違いはないんですよ。たとえば、現在では普通なモノで、発明された時は普通じゃなかったモノってたくさんあるじゃないですか。発明当時“ピアノなんて楽器じゃない”なんて言っていた人もいたと思うんです。そこで思ったのは、たとえばCD対ストリーミングサービスとか、どんなタイミングで自分が信じるテクノロジーが止まっていたのか、というのが対立構造が生まれる上でポイントになっているんじゃないかなって。
ーーおお、それは面白そうなお話で。
中田:懐かしさっていうのは、いつかの最先端で体験が止まっているんですよ。世の中に長く残って影響を与えていくものって、いつかの最先端なんです。そうやって考えると、感覚として新しいものが出たら多少不便でも使ってみようと僕は思うんです。作曲家とテクノロジーは密接な関係性なんですよ。僕は楽器のプレイヤーではないのですが、プレイヤーの方って、だれかが発明した楽器を誰よりも使いこなすことが目的になるんです。でも、楽器を作るときというのは、作曲者が今すでにある楽器では出ない音や手法を求めて、間違った使い方をするんですよ。それを製品化することの繰り返しで新しい楽器が生まれてきたんじゃないかなって。いまでもそんな欲があってこそ、新しいテクノロジーやジャンルは生み出されていくと思うので。なので、自分が音楽的な影響を受けているとすれば、それは憧れのアーティストではなく、楽器メーカーだと思っています。機材ですね。
ーーああ、そういうことですね。質問の答えだ。
中田:新しい道具から生まれる音楽というのは、実体験として多いんですよ。テクノロジーの進化で新しいことができるようになったこと、同時に生まれた制限が新しい音楽を生むんですよね。制限があっても音楽家は工夫をするので、それが時代のジャンルになっていくんだと思います。なので、制限がなくなっていくと何をしたらいいのかわからなくなってしまうかもしれません(笑)。「今はこれ」っていうトレンドみたいなものってあった方がクリエイティブは広がっていくんでしょうね。そのトレンドを生み出すのはある意味では楽器メーカーだと思っています。僕は普段、機材とコラボしている感覚すらありますから。強い影響を受けていますね。それこそ、自分で欲しい機材を作ってみたいと思うこともあります。