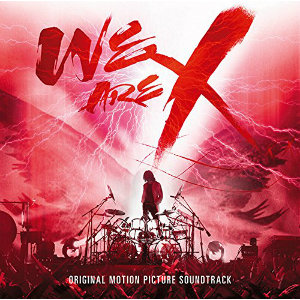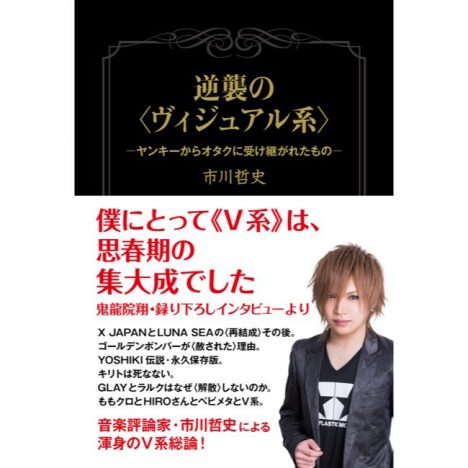目黒鹿鳴館は〈地下〉と〈地上〉を繋ぐトンネルである ジャパメタ~V系バンド、聖地としての存在意義

新型コロナ禍でライブハウスが絶体絶命なのは、言うまでもない。6月末の自粛要請解除を受け各店営業再開してはいるものの、ウイルスと共生できる奇跡の方法論は、なかなか見えてこない。ハロプロが先日、「マスク着用&常時着席&前後左右空席のお客さんに、持ち歌封印+J-POPのバラード曲を各メンバーがソロで歌う」という、3密回避ライブに果敢に挑んではいたものの、なんだろうこの徹底的な敗北感。夜明けはかなり、遠い。
それでも今年40周年の老舗ライブハウス・目黒鹿鳴館を救うべく、初ワンマンが鹿鳴館だったBABYMETAL(以下、ベビメタ)がその「聖地」での、結成10周年記念10days公演開催をアナウンスした。詳細はまだ不明だけれど、ライブハウス文化復興への強力な援軍には違いない。
言うまでもなく鹿鳴館とは、〈日本におけるヘヴィメタルの聖地〉である。
市民権があったとはお世辞にも言えないジャパメタバンドたちの主戦場だった、1980年代。ANTHEMとかACTIONとかDEAD ENDとかPRESENCEとか――私は非メタル洋楽ロキノン系評論家だったので、当時はまったく無縁の世界だった。わはは。
ところが80年代半ばから、XとCOLORが本拠としたことでインディーズロック色が加速度的に強まり、LADIESROOMやらD’ERLANGERやらZI:KILLやらTOKYO YANKEESやらGargoyleやらが割拠して、V系黎明期に。
するとXの大ブレイクで開幕した1990年代以降はもう、百花繚乱V系バンドの供給源としてフル稼働だ。LUNA SEAもGLAYもLa'cryma ChristiもPENICILLINもMALICE MIZERもSHAZNAも皆、まず鹿鳴館のステージに立つのを目標にした。
世紀を跨いだ2000年代も〈その後のV系バンド〉たちにとっての聖地に変わりはなく、DIR EN GREYにMUCCにメリーにシドにthe GazettEに人格ラヂオなどが後に続いた。関係ないが21世紀になった瞬間、それまでの英文字表記一辺倒だったバンド名に日本語表記が現れるようになった「事実」は、なかなか興味深い。文化人類学的にも。
そしてベビメタが出演した2012年以降は各種若手V系バンドのみならず、一般的な知名度は低いけどもメタルやらプログレやらに特化した〈ロック系地下女子アイドル〉たちが躍動できる、貴重な場として頼りにされている。なんと有益な。
あの〈バンドブーム〉と呼ばれていた時代、すべからくバンドは日本全国を廻り年間100本以上のライブをこなしていた。CDが売れてようが売れてなかろうが、「ライブを観せることが最高最強のプロモーション」と業界全体で信じられていたから、どんなバンドもライブ行脚の日々を積めた。特にブレイク前のバンドは、楽器・機材一式を積んだ中古のワゴン車をメンバーが交代で運転しながら、全国のライブハウスを廻るのが常。「メンバーと観客が同じ人数なんて」惨劇も珍しくなく、単にライブ経験を積む以上に精神修行の場だったと言える。
またいちアマチュアバンドにとって、レコード会社やプロダクションやメディアの目に留まるまで己れを叩き上げ続ける場もまた、ライブハウスだったはずだ。当然、店の厳しいオーディションに受からないと、出演することすらできない。そう考えるとかつては、自分のバンドで世に出るにはあまりに敷居が高かったんだった。
いまやメジャーデビューするよりも、却ってインディーズのままで活動する方が自由で経済的にもメリットは大きい時代。もしも〈音楽的才能〉が本当にあるなら、SNSのどれかでも上手に活用すればとりあえず自分以外の誰かに聴かせることが、とても簡単な世の中になった。他人の意見に一切振り回されることなく、自分の世界観を「まんま」伝えることができるとは――思えば遠くへ来たもんだ。
そういう意味では、鹿鳴館は〈最もライブハウスらしいライブハウス〉かもしれない。今回10days公演の〈聖地巡礼〉を果たすベビメタが鹿鳴館のステージに立ったのは、初ワンマンの2012年7月『コルセット祭り』と、一年後の『キツネ祭り』の実は二度しかなかったりする。私は後者のキツネの日を目撃したが、Xの「X」を徹底的にオマージュした「イジメ、ダメ、ゼッタイ」といい、「ドラムソロ後のYOSHIKI」を銅鑼を叩いて昏倒するSU-METAL+CO2を客席に噴射しまくるYUIMETAL&MOAMETALの合わせ技で再現してみせる出し物といい、最高の確信犯ぶりだったのを想い出す。吹いた。
ベビメタが、世界に冠たる〈カワイイ〉カルチャーの最終兵器になれたのは、「SNSで先行した海外メタラーの異常な熱情」に他ならない。しかしもう一つ付け加えるなら、鹿鳴館出演により「これもメタル」的御朱印を堂々いただいたからこそ、である。