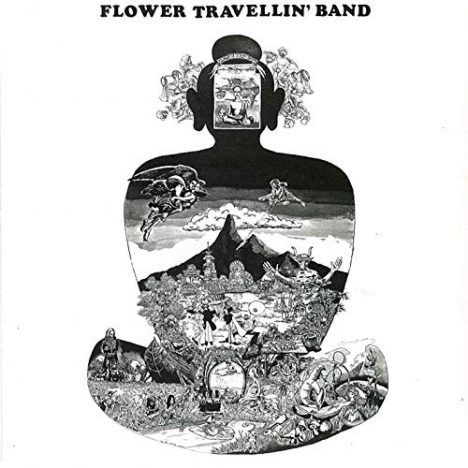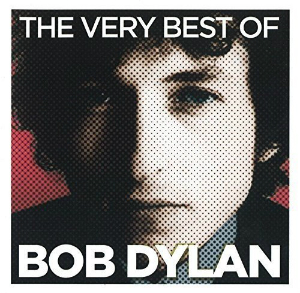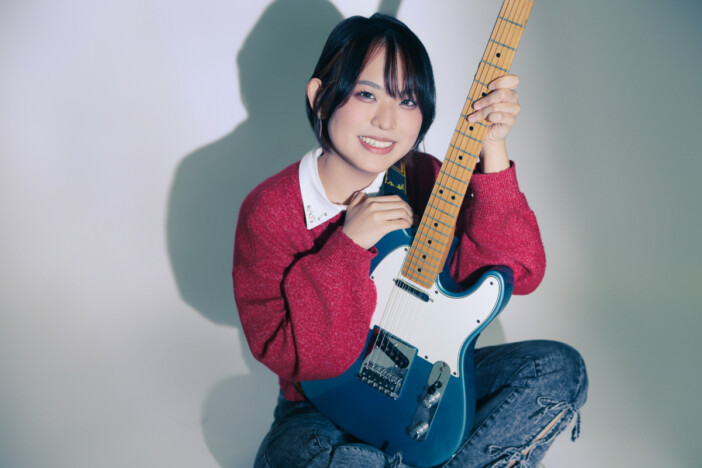近田春夫インタビュー「一番の理想は、聴いているだけで警察に捕まっちゃうような音楽」

近田春夫が、2月27日にベストアルバム『近田春夫ベスト〜世界で一番いけない男』、3月18日にビブラストーンの歌詞集『VIBE RHYME(ヴァイブ・ライム)[復刻版]』を発表した。今回リアルサウンドでは、そのベストアルバムと歌詞集をもとに、近田春夫のシンガー、作詞家、サウンドクリエイターとしての歩みを振り返る機会を得た。偶然にも取材日は、3月17日に亡くなった内田裕也のお別れ会が行われた日。喪服姿で取材場所に現れた近田春夫に、 長く交流のあった内田裕也への思いも語ってもらった。(編集部)
巧妙に戦うための言葉や音を見つけたい
ーー今日は内田裕也さんのお別れ会に参加されたとのこと、喪服でいらっしゃいますね。近田さんの音楽家としてのキャリアは、内田裕也さんとの出会いから始まったと伺っていますがーー。
近田春夫(以下、近田):そうなんですけど、実はあんまり悲しくはないんですよね。葬儀も明るい雰囲気で進行しまして。本人はそういう意識はないんでしょうけど、思わず笑みが溢れてしまうようなところがある人で、堺正章さんの弔事でも、会場がウケていました。最後は去年の大晦日にニューイヤーフェスティバル(ニューイヤーワールドロックフェスティバル)のステージの映像が流れましたが、そこでも、やはり皆さんウケていましたね(笑)。
ーー近田さんの最近のツイートには、「ユーヤさんには、アタマにくることもいっぱいありましたけど、子供の頃、初めてテレビで観た時から、僕ずーっと本当に心からユーヤさんが大好きでした」とありました。
近田:みんなそういう感じだったんじゃないかと思います。
ーー内田さんが体現されていたロックンロールというものを、音楽的な部分も含めて、近田さんも引き継いでいるのでは?
近田:いい影響も悪い影響も、色々受けたと思います。堺(正章)さんも、娘さんの也哉子ちゃんも言っていましたけど、存在自体が矛盾しているような人で、「音楽のこういう部分を学んだ」という具体的なことは言えないんですけど、それが裕也さんの魅力だと思うんですよね。ただ、憧れたし、すごく影響は受けているのは間違いなくて。一つ言えるとしたら、ステージのMCかな。オチのないような話だけど、なぜかそれがおかしい、という芸風は、ちょっと影響を受けたかもしれません。
ーーなるほど。それでは、2月に発売された『近田春夫ベスト〜世界で一番いけない男』について伺っていきます。ライナーノーツにもあるように、川口(ビクターの担当ディレクター)さんと一緒に制作されたこともあり、”シンガーとしての近田春夫”という、新しい部分に光を当てた作品でもあります。あらためて、幅広く音楽家として活動してきた近田さんにとって、「歌手」という部分はどんな位置づけなのでしょうか。
近田:それが、本当に川口さんと出会うまでは、自分の歌っている姿というものを捉えたことがなかったんです。人に楽曲を提供するときは仮歌を歌うし、音程やタイミング、発音も正確につかめるけれど、それがイコール歌い手としての能力かと言うと、それはまた別物で。自分が歌がうまいとは思わないし、過去の作品について「歌がいいから買った」という話も聞いたことがない(笑)。でも、ジューシィ・フルーツのライブにゲストで出たとき、リハーサルで昔の曲を歌ったら、それを見ていた川口さんが「すごくいいですね」とおっしゃってくれて。1〜2年前かな、そこからちょっとずつ意識するようになりました。
ーー歌うことは音楽家としてのご自身を構成するパーツの一つ、という感じですか?
近田:そうですね。どっちかと言えば、トータルで音楽を作り、キーボードプレイヤーであって、というなかで、「歌もやんなきゃいけないときがあるからやる」という程度の位置づけで。実際、ずっと歌っていなかったんですけど、カラオケでも歌うように楽しくやってみたら、昔より声が出てるな、とは思ったんですよ。それで川口さんと話しているうちに、「ああ、意外と俺の歌も悪くはないんだな」と、徐々に思うようになったという感じです。
ーー過去の曲を聴いても、中性的というか、少年性があるというか、瑞々しい魅力があります。
近田:今回のアルバムを聴くと、いまの声が一番いいんですよね。歳を重ねてだんだん声が出なくなったり……ということもあるなかで、ありがたいことに。川口さんに「歌がいい」と言われてあらためて聴いてみると、確かに年のわりに若い声をしているな、とは思いました。

ーーたとえば「星くず兄弟の伝説」など、かつての名曲をプレイバックされて、どんなふうに感じましたか。
近田:やっぱり、当時は歌に対して積極的な自信がなかったし、「音程が合ってりゃいいや」と、斜に構えている部分があったかなと。反省というのも変ですけど、いまみたいに堂々と歌っていれば、昔の歌ももうちょっと売れたのかなって(笑)。
ーー当時は、「歌ばかりでなく、トータルで音を聴いてほしい」という思いも強かったのでは。
近田:やっぱり、歌から音楽に入ってきたわけじゃなく、自分で作る曲は自分で歌ったほうが手っ取り早いという感覚で、便宜上歌い始めたというのが基本にあるから。カラオケもほとんど行ったことがないし、「歌と伴奏」ではなく、歌もバックの音も含めて「ひとつのかたまり」として、音楽を作りたかった。人の音楽を聴くときもーーもちろん、歌声が好きなアーティストもいるけれど、全体のサウンドを先に見てしまうタイプだと思いますね。
ーー今回のベスト盤も、歌にフォーカスしているなかで、やはりサウンドが楽しいですね。
近田:そう言っていただくと嬉しいですね。
ーー近田さんは「歌謡曲」をただ作ったわけではなく、ロックやパンク、ニューウェイブのフィルターを通して表現されてきた。
近田:そうですね。ロックが好きでずっとロックをやってきた人間だとしても、ものを考えるときは日本語だし、自分がカッコいいと思ってきた英語圏の音楽を日本語でやるときにはどうしたらいいのかと。そういうなかで歌謡曲というのは、日本語で表現する商業音楽として、優れた部分がある。そういう要素をどう取り入れたら、それが意味としてのロックになるのか、ということは考えていました。

ーーエッセイでも時々言及されているように、もう一方に「フォーク」という別の方法論があり、これは日本語が乗りやすいと。しかし、それは近田さんが選んだ道とは違っていますよね。
近田:やっぱり自分が好きなのは、踊りだしたくなるような音楽なんですよ。いまはダンスミュージックと呼ぶかもしれないけれど、ロックも本来そうで、ビートルズの時代から、クラブのようなところでお客さんが踊るために演奏されていたから。その意味で、フォークは踊るものではないし、サウンドにあまり意味がないんです。ロックというジャンルであれば、あのドラムはすごい、ベースがいい、ということがあるけれど、フォークソングに置いては、楽器演奏の意味や価値を、あまり人々が尊ばないというか。そこのところが自分にはどうしても退屈だと感じてしまって。歌謡曲にもそういう部分があるし、いろいろと矛盾もありますが。
ーーなるほど。歌謡曲のなかでも、やはり筒美京平さんは特別な存在なのでしょうか。
近田:そうですね、京平さんだけじゃないんですけど、鈴木邦彦さんだったり、村井邦彦さんだったり、60年代のGSから出てきた作曲家には、特に影響を受けていると思います。そういう人たちに共通するのは、もともとそんなに歌謡曲が好きじゃないんですよね。大学のジャズバンドでピアニストをしていたり、みんなそれじゃ食えないから、頼まれて、歌謡曲のようなものを書くようになって、という。例えば鈴木邦彦さんだったら、オスカー・ピーターソンとかバリバリの曲を弾かれる方ですし。京平さんもそうですけど、そんな人がなぜこんなに和風なものを書くのかという。あの方たちの音楽が楽しいのは、確かに旋律自体は小唄のように日本風のテイストが盛り込まれているけれど、編曲ができて、和声やリズムの関係から曲を立体的に作れるからで。メロディーを書くだけか、編曲までできるか、という違いが自分のなかでは大きいですね。グループサウンズは、例えば「エレキギターの音が生きる」という視点があるし、リスナーとして魅力的に感じるものですね。
ーーそうした歌謡曲の伝統はいまも続いているとお考えですか。
近田:いま話に出たような作家とは別の流れとして、70年代になって、いわゆるニューミュージックと言われる、どちらかと言うとフォークの人たちによる流れが出てきましたね。ユーミンとか、はっぴいえんどもそうなのかもしれないけど、それまでの水商売的で、夜の世界と相性のいい歌謡曲ではなく、昼間のキャンパスライフ、カタギの世界の音というか。いまのJ-POPがどちらの系譜に属するかと言うと、やはり後者であって。小市民的というと言葉は悪いかもしれないけど、「幸せ」みたいなことが大きな意味でのテーマになっていて、そういう意味では、歌謡曲の系譜ではないんじゃないかな、という気はするんです。

ーーそして近田さんご自身も、やはりニューミュージック、J-POPのラインにはいなかったと。
近田:僕はいなかったと思いますね。一番の理想は、聴いているだけで警察に捕まっちゃうような音楽なんですよ(笑)。僕はそれが一番カッコいいと思うんだけど、それは「歌手」だけじゃなくて。例えば、60年代にエレキバンドが流行り出したころ、「エレキギターを持ってたら不良になる」って言われてたんですよね。そういう反社会性であるとか、あるいは反逆性であるとか、そういうものが感じられる音楽が好きで。自分がズレているのかもしれないけれど、いまは本当にそういうものがない。
ーー今回の収録曲で言うと、例えば秋元康さんが作詞した「ご機嫌カブリオレ」は、いい意味でふざけていると言うか、いまおっしゃったようなノリがありますね。
近田:そうそう。やっぱり秋元康は、作詞家としてはすごいですよ。この「ご機嫌カブリオレ」っていう歌詞の何がすごいかっていうと、始まりの部分は、〈未来なんて何もわからないよ〉って、ものすごく壮大な、巨視的なことから始まるんですよね。そこから急に、雨が降ってきてついてない、という話になる。マクロからミクロまで自由自在に、視点の縮尺を変えていく。それでいて、どこから聴いてもやっつけにしか見えないという(笑)。この技術は本当にすごいと思う。そこに着地するまでにものすごい考えているはずなのに、誰もそれを感じない。そこに、あいつのプライドがあると思うんですよ。
ーーそこは近田さんと響き合ってる部分かもしれないですね。秋元さんは、近田さんのことを非常に尊敬していると聞きます。
近田:そうそう、でも俺はべつに尊敬してないよ。俺のほうが年上だから、こっちから尊敬しているとは言わない(笑)。どちらにしても、自分のスタンスとしてはずっと「ヤバいもの」が好きで、ただ、その「ヤバいもの」は時代や社会との関係において、一定ではないというだけだと思います。
ーーいま「ヤバい」と感じる表現はありますか?
近田:いまはわからないですね。いまのリスナーの人たちは、あまりそういう要素は求めていないのかもしれないな、という気はします。商売としてやっていくからには、そういう現実からも目は逸しちゃいけない。そのなかで、いまの「ヤバい」は何なのか、ということを見つけていこうと思って、いろいろ努力はしているんだけど。
要するに、自分にとっての「ヤバい」ことは、結局、単純に言ってしまうとやっぱり反権力、rebelということだと思う。ただ、ダイレクトに戦うのは嫌だから、巧妙に戦うための言葉や音を見つけたい、と思うんですよ。そして、何かを絶対的に否定するのではなく、常に相対的に捉えたい。例えば、何か自分にとって許せないことがあるとして、それをただ糾弾するんじゃなくて、「俺もやってるじゃん」とか。それをどこかで感じさせるものじゃないと恥ずかしくてできない、というのはあります。