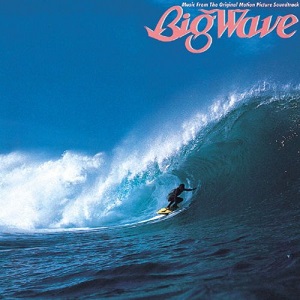『渋谷音楽図鑑』著者インタビュー
『渋谷音楽図鑑』牧村憲一が語る、2017年に繋がる「都市型ポップス」の系譜

「自分がかつてワクワクした音楽を同じようにワクワクしている若い人たちがいる」
ーーこの本が2017年に出版されるのは運命的だなと思いました。
牧村:ありがとうございます。僕もなんとなくそう感じています。
ーー小沢健二さんや小山田圭吾さんが数年ぶりに新作をリリースしたり、また星野源さんがきっかけで細野さんに若い世代からも注目が集まったりというのもありますし、一方でそこから影響を受けただろうceroやnever young beach、Yogee New Wavesも、コアな音楽ファンだけではなく、もっと広いところに届き始めてるタイミングだなと。
牧村:小山田くんと小沢くんは2人ともそろって今年のフジロックに出ますからね。それからnever young beachやSuchmosも、もはやメジャーの仲間入りをしてるし、新しい人たちが今年はぐーっと出てきていますよね。上半期が終わり、今は下半期に突入したけれど、2017年は音楽にとって忘れられない年になるような気がします。今年は何かが起こる年だって気配を感じていて。
ーー気配を感じたというのは、何か具体的なことがあったんでしょうか?
牧村:小山田くん、小沢くんの今年に入ってからの活動、さらには細野さんが新譜を作っているとか、今年初めには坂本龍一さんも8年ぶりのアルバムを出したとか。でも思い返すときっかけはDAOKOさんかな。
ーーDAOKOさんも「ShibuyaK」という渋谷の街を歌った曲がありますね。
牧村:2年前に片寄くん(GREAT3の片寄明人)がプロデュースやアレンジを担当していた作品(アルバム『DAOKO』)がきっかけで。片寄くんとショコラ(Chocolat & Akito)のコンサートに行った時にDAOKOさんを紹介してもらったんです。その前から「水星」を聴いていて、「面白いなあ、ラップということだけではなく、何だろうこの新しさと親しみ感?」と思っていた。それでDAOKOさんに直接聞いたら、彼女は両親の影響でシュガー・ベイブなどのレコードを聴いて育ったみたいなんです。その時に、「やっぱりチェーンみたく繋がってるんだ」と確信して、それ以降DAOKOさんの動きを追っているうちに、never young beachやcero、Suchmosらがどんどん視野に入ってきた。そうすると、「あれ? 彼ら彼女らがやってること、僕がよく知ってる感じだぞ」と。自分がかつてワクワクした音楽を同じようにワクワクしている若い人たちがいる。その共通項がすごく重要で、どうやらこの数年そういった動きが重なってきて、ついに2017年に若い人たちの大好きなものと、それをずっと守ってきた、持続してきた人たちが出会った。実際にフェスやイベントで誰々と誰々が会ったって記念写真がSNSにあがっていたりね。意図的に何かを仕掛けなくても、すでに混ざり合ってきてる状況ができあがってきているんです。
ーーnever young beachやYogee New Wavesは「シティポップ」「ネオシティポップ」という言い方もされていますが、この本では「都市型ポップス」という言葉を使っていますね。
牧村:70〜80年代は、「ニューフォーク」「ニューロック」といったように、“ニュー”をつける傾向にありました。「ニューミュージック」も、吉田拓郎から松任谷由実まで、それまでのいわゆる歌謡曲ではないものを全部ひとまとめにしていた。そのなかで、はっぴいえんど系列と呼ばれてる人たちをあえて分けるために使った言葉に、「シティ」という言葉がありました。1970年代に「風都市」という企画集団があって、これを二つに分けると「ウィンド」と「シティ」になる。彼らはマネージメント会社の「ウインドコーポレーション」と、音楽出版会社の「シティミュージック」を作った。この「シティミュージック」というのが、シティの始まりだったと思う。失礼な言い方だけど、「シティ」と宣言することで、四畳半フォークとか、一発成功型の地方との区別化ができるという、ある種の差別もあった。だから、僕はこの本ではそうした経緯を持った「シティ」という言葉を使わずに、「都市型ポップス」という言葉を新たに使いました。「都市」は東京だけじゃなくて、もちろん中小都市も含んでいる。もし、かつての「シティミュージック」について書いた本だとしたら、もっと偏った狭いものになっていたんじゃないかな。「都市型ポップス」というのは、偏ることなく、広範囲の音楽を示せて、志の高い音楽を全部受け入れられる言葉だと思っています。
ーー渋谷という一つの場所を拠点に、多くの人が集まってきて、結果的に大きなムーブメントが起こっていく。その場所のことを、この本の中では「磁場」と呼んでいますね。
牧村:僕の親は推理小説マニアだったんだけど、松本清張が推理小説やエンターテインメント小説だけじゃなくて古代史のことを書いている著作があって。そこから僕が影響を受けたのが、歴史ある神社の敷地を掘っていくと、前の時代の宗教の跡が出てきて、最後には一つの石にたどり着く。拝火教ですね。人が集まるのは、何か特別な意味がある場所だと思うんですね。それは渋谷の街にも適応できるだろう、と僕は考えました。ある地点を掘っていくと、それぞれの歴史の中で重要なものが護石のようにあるような気がしました。音楽の歴史の中でも、掘っていくことで出会うものがあるはず。それに出会えるのか、出会えないのか、出会っても気づかないこともあるはずだけど、僕はラッキーなことに渋谷の歴史の上で大事なポイントに何度も立ち会ってきたし、その度に「なんだろうこれは?」と好奇心が生まれました。その価値がまだ定まっていないなかでも、「自分の中のこのこだわりは何だろう?」「何が僕を吸い寄せてるんだろう?」と考えて、とにかく自分の感覚を信じてやってみようと思った。その結果が、レコードやレーベルを作ることに繋がりました。
ーーその「磁場」は70〜90年代だと公園通り、道玄坂、宮益坂を中心に存在しており、「ジァン・ジァン」「BYG」などの喫茶の名前がでてきます。今の渋谷にも音楽の磁場となる場所はあるのでしょうか?
牧村:それがなかなかわからないところですね。あえて一つ挙げるとしたら、現状ではスペイン坂のWWWやWWW Xではないでしょうか。磁場であるかどうかは別として、少なくとも集まりやすいということを叶えていると思います。出演者の負担額なども考えると、渋谷は場所代が高いんですよね。お客さんの数と、そこでかかるお金のバランスが取れるっていうのは渋谷のど真ん中だとなかなか難しいんですよ。
ーーその二つのライブハウスはもともと渋谷を拠点にしていたスペースシャワーが運営していて、面白いイベントをいくつも企画している。キュレーション的な動きも活発な印象もあります。
牧村:「ネオ渋谷系」みたいな言葉がもし成り立つとしたら、あそこが中心になってるのではないでしょうか。先ほど話したDAOKOさんも出演してますし、こけら落とし公演をceroがやったというのも。しばらくの間は、発信地になっていくのではと思います。