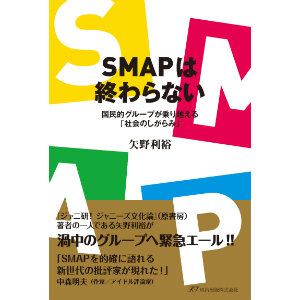栗原裕一郎の音楽本レビュー 第15回:矢野利裕『SMAPは終わらない 国民的グループが乗り越える「社会のしがらみ」 』
〈SMAP的身体〉とは一体何か 栗原裕一郎の『SMAPは終わらない』評
SMAPとクラブミュージック
SMAPのカジュアルな存在感は、音楽の面ではクラブミュージックへの志向性に現れていたと矢野は指摘する。少年隊とSMAPという対比は、取りも直さずディスコとクラブの対比でもあった。
「ディスコ的価値観を見事に体現していた少年隊のギラギラした衣装と比べたとき、SMAPがドレスダウンしているのは明らかである。ジーンズ? ネルシャツ? あるいは、着ぐるみ? クラブ・ミュージックを歌っていたSMAPは、ジャニーズ的なドレスコードをことごとく規制緩和し、もっと自由に、解放的に振る舞っていた」
80年代に興ったクラブカルチャーは90年代に浸透し、ディスコとは客層を異にする遊び場として定着していった。もっともジュリアナ東京がオープンするのはバブル崩壊後の91年で、ディスコからクラブへという移り変わりが90年前後にパタッと起こったわけではない点には注意が必要である。
本書は3部構成になっている。第1章はここまで紹介してきた矢野による〈SMAP的身体〉論。第2章は、橋本徹と柳樂光隆を招いての鼎談(第3章は鼎談を踏まえてのSMAPディスクガイド)、第4章はアイドル評論家・中森明夫と矢野の対談だ。
クラブミュージックとしてのSMAPは第2章で掘り下げられる。橋本徹は、ディスクガイド『サバービア・スイート』や一連の「フリー・ソウル」コンピレーションCDでクラブシーンを牽引した人物。柳樂光隆は『Jazz The New Chapter』でクラブミュージック以降のジャズの文脈を提示してみせて、日本のみならず海外のジャズシーンにまで影響を及ぼしている新進のジャズ評論家である。
以前、若杉実『渋谷系』の書評で「渋谷系とはアシッドジャズ、DJカルチャーだった」という話が出たが、この章で目論まれているのは、「フリー・ソウル」をクラブカルチャーのハブにして、SMAPの音楽を、渋谷系に象徴される90年代音楽の文脈に位置づけし直すことだ。
インパクトが大きくてもっともわかりやすい例は、「がんばりましょう」(94年)の元ネタが、ナイトフライトの「ユー・アー」(79年)だというものだろう。聴き比べれば「あ、これは引っ張ってますな」と誰もがうなずくに違いないくらいわかりやすい。95年に発売された『フリー・ソウル・アヴェニュー』の1曲目に収録されていて、ライナーで橋本はこういっている。
「オープニングはいきなりSMAPファン必聴のアーバン・ソウル(笑)。「がんばりましょう」のネタだね」
ごく大雑把な言い方で済ませるけれど、これは渋谷系の手法とされたやり口にほど近い。黒っぽいサウンドへの志向があった点でも90年代のクラブカルチャーとシンクロしており、SMAP以前のジャニーズ音楽とは異質である。
この鼎談では、クラブミュージックの流れと、SMAPの音楽性のアルバムごとの変化を対照し比較することで、彼らの同時代性と異質性が炙り出されていくことになるのだが、固有名詞やジャーゴンが遠慮会釈なく飛び交って(註は付けられている)、大変にハイブラウかつマニアックである。ここまで詳細にSMAPの音楽が語られたことは知るかぎりない。
SMAPファンでここで話されている音楽に精通している人はそう多くないと思われるので、若干ミスマッチな印象はあるものの、音楽性を真摯に検討し90年代音楽の中に置き直してみせたのは大きな進展というべきだし、ファンの納得度と満足度もきっと高いだろう。