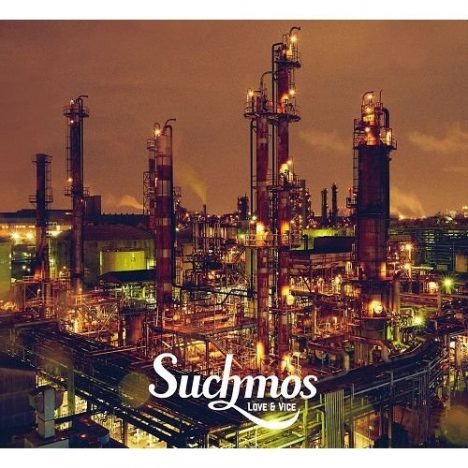レジーのJ−POP鳥瞰図 第9回
さかいゆう、LUCKY TAPES、Suchmos...「シティ・ポップ」ブームの中で、同時多発的に生まれた新しい音楽
さかいゆう『4YU』と「シティ・ポップ」という「タグ」
さかいゆうの4枚目のオリジナルアルバム『4YU』が2月3日にリリースされた。この人に関して語る際にまず触れたいのが、彼のボーカルについてである。精度の高い音程で発せられるクリアな歌声は、それがまるで一つの楽器であるかのようにどんな楽曲へもきれいに溶け込んでいく。とかく「主役として自分らしく歌い上げる」ことが褒めそやされる日本のメジャーシーンにおいて、音符を外すことなく曲の展開に応じて表情を変えることができるボーカリストは実は非常に少なく、その存在はとても貴重だ。それぞれの楽曲に異なるコンセプトを立てて制作されたという『4YU』においても、ジャジーな「WALK ON AIR」でパワフルな歌いっぷりを見せたかと思えば、男っぽいバラード「あるギタリストの恋」では哀愁たっぷりの湿った歌声を聴かせるなどボーカリストとして変幻自在の技を見せている。
デビュー曲「ストーリー」の冒頭、ピアノのイントロが鳴り響いた時からさかいゆうには「アーバン」な雰囲気が漂っていた。音楽的にリンクするアーティストを挙げようとすると、山崎まさよしや秦 基博といったオフィスオーガスタの同門ミュージシャンよりも山下達郎が先に思い浮かぶ。そして「アーバン」「山下達郎」というキーワードは、昨今もてはやされている「シティ・ポップ」という概念と非常に親和性が高い。そういう意味では、さかいゆうは以前から今のシーンにおけるバズワードになりつつある「シティ・ポップ」に連なる音楽をずっと鳴らしていたという見方もできる。『4YU』にはそんな潮流の中心人物でもあるmabanuaとAvec Avecが参加しているが、この人選はとても納得感があるし、さかいゆう自身が自分の資質をよく理解している証拠とも言えるかもしれない。それぞれとの相性は当然のように良く、ホーンが鮮やかなmabanua編曲の「SO RUN」から「東京の冬っぽい感じのイメージで」アレンジしたというAvec Avecとの共作「Doki Doki」に続く流れは、アルバムの幕開けにして大きなハイライトと言ってもよいだろう。
一方で気になるのが、この『4YU』が「シティ・ポップ好き!」を標榜する人たちにどれだけ聴かれているのかという点である。鳴っている音楽、参加しているアーティスト、まさに「ドンピシャ」な作品でありながら、(あくまでも肌感覚の域を出ない話ではあるが)そのスペックに相応な広がりを見せていない印象がある。
ここで考えたいのが、アーティストないしは作品に対して何らかのきっかけで付与される「タグ」の問題である。音楽そのものの善し悪し・好き嫌いを判断する前段階として、最近の多くのリスナーは「これは○○に属する、だから自分に関係がある」「これは××の領域の人、だから自分とは関係ない」という類の意思決定を(意識的に、もしくは無意識のうちに)行っている可能性が高い。もちろんこの手の行動は大昔からあったものと推察されるが、インターネットがもたらした「情報量の飛躍的な増加(だから選ぶのが面倒である)」「好きな情報のみフィルタリングできる仕組みの登場(だからそれを使って好きなものだけを効率的に知りたい)」という状況によってその傾向はますます強まっていると思われる。
さかいゆうはメジャーデビューから7年ほど経つ中堅のアーティストで、出自も含めて「J-POP的なフィールド」にいる人というイメージが強いはずである。よって、「シティ・ポップ」という「タグ」がつけられておらず、だから「シティ・ポップ好き」には届かない。かなり単純化したモデルではあるが、程度の差はあれこのようなことがそれなりの頻度で起こっているのではないだろうか。
記号化する「シティ・ポップ」において浮上する新たなターム
ここまで「シティ・ポップ」という言葉を注釈なしに使ってきたが、現時点においてこの「シティ・ポップ」という言葉に明確な定義を与えるのはかなり困難になっている。「シティ・ポップ」というコンセプトがややこしいのは、2010年代以降にこの言葉が使われるにあたって「1980年代ごろに “シティ・ポップ”と呼ばれていた音楽のリバイバル」「情報が溢れる現代の“街”で生きる若者が作る音楽」という2つの概念が混在し続けていることである。そうこうしているうちに、今では「何となくサブカルっぽい音楽」を指す記号としてざっくりと「シティ・ポップ」という言葉が使われるケースも増えてきた。人によっては星野源も水曜日のカンパネラも「シティ・ポップ」だったりするが、その区分けの是非に対して万人が納得する回答はおそらくどこにも存在しない。
日々曖昧さが増していっている「シティ・ポップ」という呼称だが、それはつまり「この傘に包含される音楽ジャンルがどんどん広くなっている」ということも同時に意味する。その中で個人的に気になっているのは、ともすれば昔は「ださい」と言われていたようなポップ成分が重要な位置づけを占めていることである。たとえばAORやフュージョンといったジャンルが提供していた「過剰なまでの洗練さ」と地続きのアーティストが増えてきているし、この括りでたびたび聴かれるホーンなどを導入した派手なサウンドは米米CLUB的でもある(1995年リリースのその時点でのベストアルバム『DECADE』を聴くと、今のシーンで志向されていることが先取りされているような印象を受ける)。はっぴいえんどに代表される「フォーキー」な要素のみをルーツとするのではなく、より「カラフル」(ある意味では「バブリー」)な意匠が自然に取り入れられているというのが直近の「シティ・ポップ」の流れとして指摘できるのではないだろうか。
象徴的だったのは、昨年の10月に公開された佐藤竹善(SING LIKE TALKING)とatagi(Awesome City Club)、角舘健悟(Yogee New Waves)、高橋海(LUCKY TAPES)による座談会である(http://natalie.mu/music/pp/singliketalking02)。AOR的な要素を持ったポップスを長期に渡って作ってきた一方でいわゆる「ロック論壇」からはほぼ無視され続けてきたベテランアーティストが尖った若手バンドマンとシンクロしているこの企画は、2010年代後半の「シティ・ポップ」というムーブメントが「これまでのしがらみやイメージを気にせず、偏見なく面白いものを集めた結果によって形成されている」ということをわかりやすく表している。リスナー側が「タグ」に囚われて自ら選択肢を狭めがちになるのとは対照的に、アーティストのスタンスはどんどん自由になっていっている。