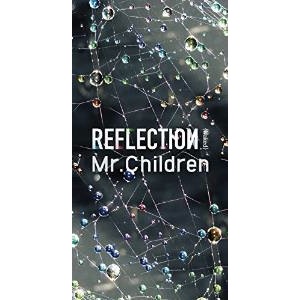Mr.Childrenが見せた「4人のロックバンド」としての覚悟 鹿野 淳が日産スタジアム公演をレポート

今回のステージは、メンバー以外にキーボードのサニーただ1人、つまりは5人だけがステージに立ち、スタジアムライヴを行っている。しかもそのサウンド演出、例えばシーケンスなどは最小限度に留められていて、つまりはメンバーの生の肉体から鳴らされるものが前面に立って響いて来るものになっていた。そうなると、歌、ギター、ベース、ドラムというオーソドックスな4ピースバンドから掻き出されるものは、とてもスタンダードなギターロックサウンドとなり、それが力強いナンバーの選曲と、4人の織り成すグルーヴやアンサンブルから強く発信されていたのだ。
そんな「4人だからこそ必然的にロックバンド然とする」のは、演出面でもそうだった。LED画面に出て来る映像やメッセージは、どれもこれも伝えたいことがはっきりしているものばかりで、誰もがわかる、息をのむ瞬間もあるようなハードな内容のものも多かった。
こういった劇場型なストーリーや演出は、言ってみれば伝統的なロックライヴそのもので、U2、もっと遡れば元祖スタジアムロックライヴのオリジネイターであるピンクフロイドのそれと通じるものでもあった。
ロックという、意味と意義に満ちた音楽のカルマや必然をどれだけ誰でもわかる形でドラマティックに演出するのか? それがスタジアムにおけるロックライヴの基礎にあるものだが、Mr.Childrenはその一番本質的なものをこの日の69000人にはっきりと浴びせかけていた。それは伝統的という言葉の意味とは裏腹に、今の時代とこの国のシーンにとっては、むしろラジカルで新しい感動のスタイルにさえ見えた。勿論、そのラジカリズムと感動は、彼らの楽曲の素晴らしさ故のものなのだが。
日本のバンドは芸能、メディア、ポップスというシーンの中にいるという意識が、売れて行く過程の中でどんどん強くなって行くので、その過程でロックバンドのカルマのようなものが漂白されたり薄まっていったりもする。しかし、彼らは原点に立ち返ったといってもいい今回のシーズンに今一度、ロックバンドとしてのダイナミズムと強さと美しさ、さらに言えば残酷なまでのリアリティを、生々しく突きつけるライヴを敢えて行った。これこそがデビューから23年、“innocent world”でのブレイクから21年を経て、なおも最前線でメガバンドで居続ける彼らの説得力なのだと、この日のライヴであらためて強く感じさせてもらった。
「これが、みんなの足音!」
今年の冬から春にかけてのアリーナツアーでは「これが、僕らの足音!」と告げていた桜井のMCが、「僕ら」から「みんな」に変わっていた。これは言うまでもなく、「再びここから、Mr.Childrenの新しい音楽と生き方が、みんなの生き方になるように」という願いと希望そのものが含まれているということだろう。
音楽は、創造力が一番心に近い所でダイレクトに伝わるものなんじゃないかとずっと思っている。だからこそ、ラヴソングが国家間や言語を超えて、時に生き死にに影響を与えるようなものになるんじゃないだろうか? 例えば、胸が張り避けるような曲の直後に、多幸感溢れる曲を歌う。そこで泣いた人がすぐに涙を拭きながらこの上ない笑顔を浮かべて一緒に歌う。こういったことも全部、音楽が生み出した創造力だと思う。
最近のライヴでは、どの曲でも盛り上がり、盛り上がらない曲が披露されている時は、盛り上がる曲を「待機」するという状況も生まれたりしているが、そういう中、笑って泣いて、鳥肌が止まらなくて震えた直後に満面の笑顔で両手を掲げて盛り上がるという今のMr.Childrenのライヴの景色は、音楽という創造力の共有を理想的な形で行っている。問答無用のベテランバンドが、現状のシーンを客観的に見つめ、そもそも音楽が持っているイメージ、創造力を喚起させるセット、演奏、ショーを披露する。天井知らずの夢だけでもなければ、ロックのダークネスだけでもない、スタジアムバンドならではの創造力が、本当に溢れている素晴らしいライヴだった。
僕が見た日の翌日のライヴは、豪雨にまみれた、彼らのライヴ史上でも間違いなく伝説になるものとなった。「物憂げな9月の雨に打たれて 歓喜に満ちた時間を想って歌い続けた」Mr.Childrenは、今年、『REFLECTION』というアルバムと、この「Mr.Children Stadium Tour 2015 未完」というツアーをもって、再び本当に大切な音楽の鍵を握るバンドとなった。
「未完」とあるように、今年のアクションは完結なき、始まったばかりのメッセージ、そして行動である。1日も早く次の音楽、そして次のライヴに期待したくなる一夜だった。
(文=鹿野 淳(MUSICA)/写真=石渡憲一)