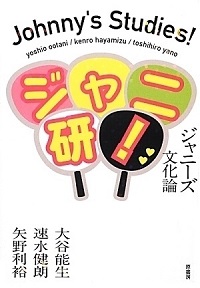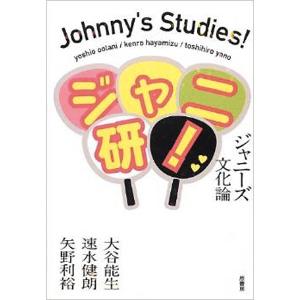矢野利裕のジャニーズ批評
SMAP『Mr.S』はなぜ1996年を想起させるのかーー森脱退がグループに残した刻印
前回記事の最後に、SMAPの新作『Mr.S』は90年代的である、という印象を書いた。この印象は筆者にとって、妙に感慨深いものとして残っている。もちろん、「90年代」と言ってもさまざまな切り取りかたがあるので、ここで言う「90年代」も一側面に過ぎないことは強調しておくが、そのうえで「SMAPと90年代」について書きたい。(参考:SMAPの新作は“実力派ミュージシャンの戦場”? 川谷絵音(ゲス乙女)、SALUなどの起用曲を分析)
90年代と言えば、世界的にクラブ・ミュージックが台頭した時代だったと言えるが、それは日本のポップス・シーンも例外ではない。もっとも、日本のポップスにおけるクラブ・ミュージックの影響は、80年代を通じて色濃くなっていく印象があるのだが、とくに90年代は、打ち込みのサウンドも一般的になり、中盤になる頃には、ハウスやテクノ、ヒップホップのヒット曲も出てくる。例えば小室哲哉のような存在は、このような時代に強い存在感を示した。一方、クラブ・ミュージックの影響をもう少し違ったかたちで表現した存在として、ピチカート・ファイヴや小沢健二などといった、いわゆる渋谷系の面々もいた。クラブ・カルチャーと密接な関係を持った彼らは、先行する音楽を引用・変奏しながら新しい音楽を生み出していた。このように90年代とは、クラブ・ミュージック的な発想が日本のポップスに流れ込んできた時代だった。
1991年にCDデビューしたSMAPとは、まさにこのような時代とともに国民的アイドルとなったグループである。SMAPは、同時代的な流れと呼応するように、デビュー当初からUKのハウスやニュー・ジャック・スウィングなどの意匠を取り入れていた。また、フリーソウルとして人気のナイトフライト「You Are」を引用した「がんばりましょう」(1994)、イントロにシカゴ「Saturday In The Park」を引用した「しようよ」(1995)など、渋谷系的な方法論で作られた曲もある。というか、そもそも90年代中盤までのSMAPには、フリーソウルの現代版のような曲が多かった。そのなかでも傑作は、小沢健二もフェイバリットに挙げた「俺たちに明日はある」(1995)か。この曲が収録されたアルバム『SMAP 008 TACOMAX』(1996)は、マイケル・ブレッカーやオマー・ハキム、ウィル・リーなどといった、ジャズ/フュージョン系のスタジオ・ミュージシャンを起用していた時期の作品である。『008』と同路線の『SMAP 009』(1996)以降、「青いイナズマ」(1996)「SHAKE」(1996)「ダイナマイト」(1997)といった歌謡ハウスの名曲連発によって、SMAPの楽曲は一気にプログラミング主体の音作りに移行するのだが、この時期あたりまでは、プログラミングとスタジオ演奏を併せた音作りをしている。SMAPの傑作アルバムは他にも挙がるかもしれないが、プログラミングと生演奏がバランス良く両立している『008』は、個人的に好きな一枚である。