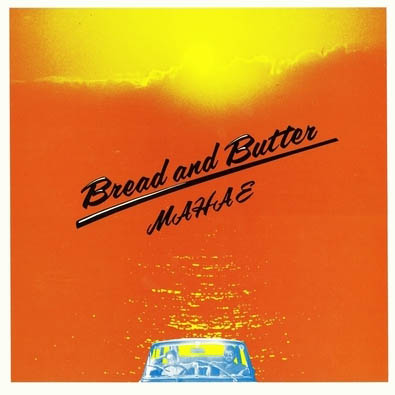栗本斉の「温故知新 聴き倒しの旅」
加藤和彦の“美学”が行き届いた名作『バハマ・ベルリン・パリ〜ヨーロッパ3部作』を聴く
別に今さら言うことでもないのかもしれませんが、アーティスト名や曲名にフランス語を付けることって、どう思いますか? 僕個人としては、口にするのがなんだかこそばゆくなってしまうんですよね。カタカナのままで読むと、ちょっと気恥ずかしくて、とはいえネイティブっぽく読むと(そんなことはできないんですが)それはそれでちょっと恥ずかしい。でも、そういったちょっぴり気恥ずかしい感覚を超越し、面喰らってしまうアーティストがいるのです。それが、今回紹介する加藤和彦。誤解を招かないように最初に言っておきたいのですが、僕はこの人の音楽がめちゃくちゃ大好きです。しかしながら、スノッブとでもいうのでしょうか、ちょっと斜に構えたオシャレ感覚に赤面してしまう部分が見え隠れしているのです。
そんな加藤和彦の世界観が顕著に現れた作品群があります。それが、俗に“ヨーロッパ3部作”と呼ばれている『パパ・ヘミングウェイ』(1979年)、『うたかたのオペラ』(1980年)、『ベル・エキセントリック』(1981年)の3枚です。タイトルからも浮世めいた感じがしますが、内容も負けていません。それぞれ、バハマ、ベルリン、パリでレコーディングされた作品で、当然のように曲名や歌詞の中にもフランス語をはじめとする横文字がずらりと並ぶのですが、「パリはもう誰も愛さない」とか「わたしはジャン・コクトーを知っていた」なんていうタイトルなど、普通に音読したら、少々赤面モノです。
しかし、ここまでは前置き。音楽的にこれらのクオリティは半端ないわけです。海外録音といっても、メインとなるミュージシャンは日本から連れて行っているところがポイント。アルバムによって微妙に人選は異なるのですが、坂本龍一、細野晴臣、高橋幸宏に加え、小原礼、大村憲司、矢野顕子、というYMO関連の人脈が参加。テクノやニューウェイヴの時代ならではのエッジーなサウンドをベースにしながらも、タンゴ、シャンソン、レゲエ、スカといったワールドミュージックのエッセンスをたっぷり振りかけ、おまけにオールドスタイルのスウィング・ジャズやクラシカルなストリングス・サウンドをそっと差し込むなど、当時の日本には存在しなかった独自の世界を築き上げています。もちろん、海外録音ということもあって、各場所それぞれの濃密な空気感を感じられるのも興味深いところ。