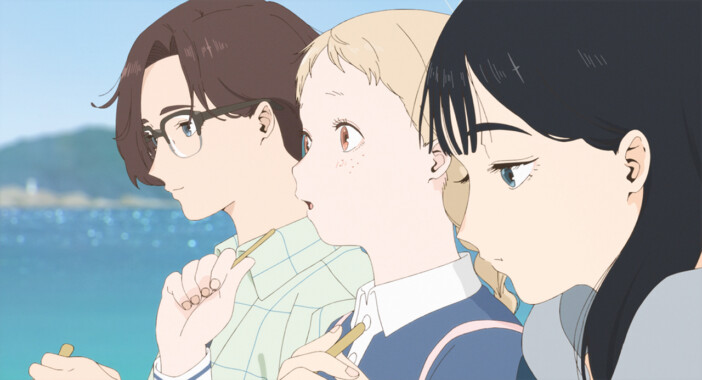『メダリスト』“さりげない”CG表現の新規性 いのりの成長とともに豊かになるカメラワーク

つるまいかだ原作による、フィギュアスケートを題材にしたスポーツアニメ『メダリスト』(2025年)。スケートを独学で学ぶ小学5年生の少女・結束いのりと、かつてスケートで挫折を味わうも彼女のコーチとなった明浦路司の師弟コンビが、二人三脚でオリンピックのメダリストを目指して奮闘するビルドゥングス・ロマン(成長物語)である。物語の題材からも、作中ではスケートリンク上でのフィギュアスケートのダンスシーンが毎回登場する。
『メダリスト』では、近年のスポーツアニメに見られるように、いのりたちのスケートの演技シーンやOP映像に部分的にCGを取り入れる演出が用いられている。本作の制作元であるENGIは、CGアニメーション分野のスタッフが多く在籍し、フル3DCGアニメ『楽園追放 -Expelled from Paradise-』(2014年)でチーフアニメーションプロデューサーを務め、グラフィニカから移籍してきた吉岡宏起が現在代表取締役に就く、もともとデジタルアニメに強いスタジオだ。
こうした、ストーリーや映像の見せ場となるキャタクターの動きだけをCGで表現するという演出は、『アイカツ!』(2012年〜2016年)や『ラブライブ!』(2013年〜2014年)など、主にアイドルアニメのダンスシーンにおいて2010年代初頭からテレビアニメで頻繁に見られるようになった。ちなみに、本作のシリーズ構成・脚本を手掛ける花田十輝は、『ラブライブ!』シリーズのシリーズ構成も務めている。

ただ、こういったセルアニメーション以来の手描きの作画表現と、コンピュータのアルゴリズムによって動きを生成する3DCGによる作画表現のミックスは、数年ほど前までは、印象のギャップがかなり目立つところもあった。例えば、その3DCGによるキャラクターの動きに感じる独特のぎこちなさや冷たさを、かつて土居伸彰は、「ゾンビ的」(『21世紀のアニメーションがわかる本』)とも表現した。しかし、昨今ではテクノロジーの発達と演出の洗練により、アニメのCG技術はほとんど違和感を抱かせないクオリティにまで達している。さらに、近年ではバーチャルカメラとモーションキャプチャ、ロトスコープなどの活用により、実写映画、あるいはオープンワールドのゲーム空間のようなよりリアルな身体表現やマルチアングルの空間表現が可能となった。
こうした表現上の革新による恩恵は、まさに『メダリスト』のようなスポーツアニメにこそ顕著だろう。『メダリスト』では、キャラクターの動きや空間のカメラワークがCG作画によって縦横に映像化され、特に画面の手前から奥に、逆に奥から手前に、という奥行きのある動きがスムースに表現されている。また、アニメの視聴者の視点があたかもリンク上でキャラクターと伴走しているのかのようなリアルな表現が可能になっている。
こうしたいわゆる「縦の構図」を採った奥行き表現は、昔のアニメ――具体的にはセルアニメーション時代のテレビアニメでは、相対的に不向きとされてきた。いうまでもなく、セルアニメでは、背景画の上に、キャラクターやモノの絵が描かれた複数のセル画を何層もレイヤー状に重ね、その真上から撮影台(アニメーション・スタンド)のカメラを動かしながら撮影することで作られる。したがって、日本アニメ研究の第一人者であるメディア研究者トーマス・ラマールもこのように書く。「セル・アニメーションでは、奥行きへの運動を扱うのが難しくなる。アニメーション・スタンドでは、多くの人が映画のトレードマークだと考えていることを正確に再現するのは困難なのだ。それは、イメージの世界の中へと向かう運動の感覚、すなわち奥行きへの運動の感覚である」(『アニメ・マシーン――グローバル・メディアとしての日本アニメーション』大﨑晴美訳、14頁)。

ラマールの学術的なアニメ研究では、このフラットで多平面的なイメージ群が水平方向にスライドしていくようなアニメ特有の空間構成が、「アニメティズム」という用語で定式化されている。それは、ラマールが「シネマティズム」と呼ぶ、奥行き方向へと収斂する映画カメラの単眼レンズ的なコンポジティングとは対照的な時空である。だからこそ、本来、キャラクターの身体が画面いっぱいに躍動することが魅力のスポーツアニメにしても、以前のテレビアニメではその表現がかなり制約されていた。そのために、戦後日本のテレビアニメでは、以前、私が『ブルーロック』に関するコラムで論じたように、「日本式リミテッド」などと呼ばれるリミテッド・アニメーションの技法を創造的に駆使した、止め絵、3回パン、画面分割、透過光などの独特の演出が編み出されていったのである。例えば、戦後日本のテレビアニメでアクションシーンや試合での投球シーンなど視聴者に強く印象づけたい決めのシーンでは、画面が止まったり、繰り返されたり、スローになったりする。よく言及されるところだと、スポ根アニメの『巨人の星』で、星飛雄馬がボールを投げてからキャッチャーのグローブに届くまでに時間が延々引き延ばされ、それだけで1話分が終わってしまう、みたいなアレである。
こうした時間表現を、精神科医でもある批評家の斎藤環は、通常の物理的・客観的な時間感覚である「クロノス的時間」と対比して、「カイロス的時間」と呼んだ(『文脈病――ラカン/ベイトソン/マトゥラーナ』)。ちなみに、戦後テレビアニメに見られるカイロス的時間の表現は、歌舞伎などの日本の古典芸能や、戦後の大衆文化ではおそらくマンガからの影響が大きいと思われる。
しかし、CGやデジタルコンポジットが浸透した21世紀のアニメーションでは、ラマールが論じたようなアニメティズムが技術的進化とともにアップデートされ、ある意味ではシネマティズムと接近するような新たな映像表現が見られるようになっている(ちなみに、かつて『新映画論 ポストシネマ』〔ゲンロン〕で、私はそれを「擬似シネマティズム」と呼んだことがある)。『メダリスト』のスケーティングシーンも、そうしたいわばポスト・アニメティズム的な表現の一つだと言っていい。