宮台真司は『サタデー・フィクション』に何を感じたのか? ロウ・イエ監督と考える美学的な生き方
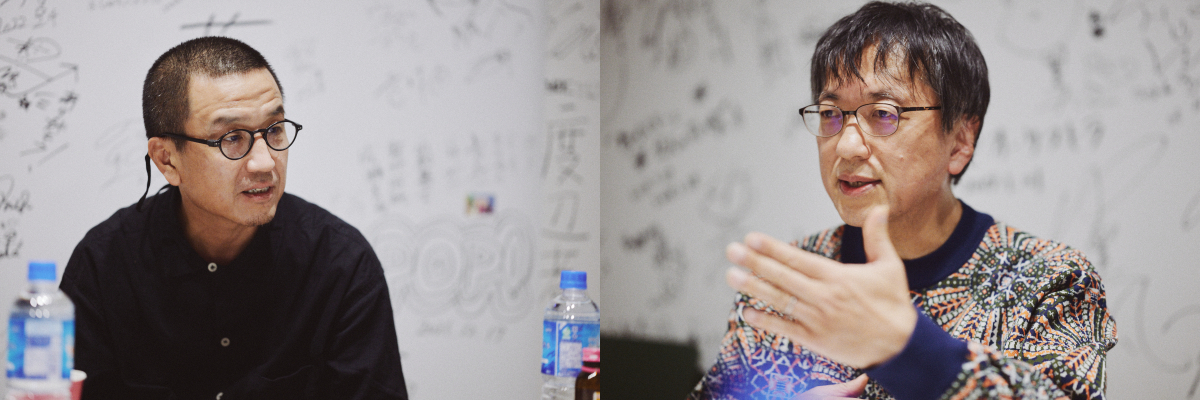
『サタデー・フィクション』は実に素晴らしい。ただ若い世代には「よくわからない」という人も多いでしょう。歴史を知らないからです。1941年12月8日が真珠湾攻撃、日米開戦の日であることを知らない人も多い。それにも留意して、僕の受け取り方を、「①上海とは何か? ②スパイにとって恋とは何か? ③良い社会で人は幸せか?」に分けて話します。
上海とは何か?
宮台:母ときょうだいは上海フランス租界で生まれ育ちました。母の父が上海自然科学研究所(本作がクランクインした場所)の教授でした。また、御両親が蘭心劇場(本作の舞台)に勤めていたロウ・イエ監督に似て、僕の母方一族も興行に関わっていました。母の母の父は戦間期の浅草で芝居小屋と映画館を5つ所有し、日本で最初の映画雑誌を出しました。
母(1935年生)より少し年長の、SF作家のJ・G・バラード(1930年生)と無呼吸潜水記録保持者のジャック・マイヨール(1927年生)が、上海の生まれ育ち。祖母もバラードもキャセイ・ホテル(本作の主要舞台)について語っていた。僕は、母と祖母から聞いた話とバラードとマイヨールが残した文章や発言から上海を想像してきた。一口で、幻影のような都市です。
バラードが語ります。蘭心劇場に集う富裕層には煌びやかな社交界があり、観劇や舞踏会が終わって外に出ると、多数の大人や子供が凍死している。子供だった自分には何がリアルで何がアンリアルなのか分からなくなったと。日本語で「リアル」を「実在」と訳しますが、正確には、実在すると感じるはずの事物(=現実)に、実在感が感じられなくなったのです。
社会学者のピーター・L・バーガーは誰もが実在感を感じる時空を「現実」(もしくは「至高の現実」)と呼び、誰もが実在感を感じるとは言えない時空を夢や虚構や妄想だとします。現実が「存在する」ように夢や虚構や妄想も「存在する」。「存在」概念は言葉で指示できるもの全てを含む。現実から実在感が消えれば、手触りは夢や虚構に近づく。存在しても実在感が欠けるからです。
思えば、バラードの全作品は、実在するはずの現実から実在感が失われる話です。現実に実在感を感じられずに海に潜るようになったマイヨールも、加齢で潜れなくなったら自殺しました。租界時代の上海で生まれ育った二人に共通して「何にも実在感が感じられない不全」があります。一口で言えば、虚と実の境界が曖昧で、人が影絵のように見えることです。
本作は上海租界の虚実混融を活写します。ラスト近くの蘭心劇場での横光利一原作『上海』の上演中の虚実混融が象徴的です。劇中劇の上演中、帝国陸軍が銃撃しつつ乱入する芝居が展開する場面で、現実の帝国陸軍が蘭心劇場に銃撃しつつ乱入します。本作の観客も、蘭心劇場の観客と同様、帝国陸軍の銃撃が虚なのか実なのか、分からなくなる。鮮烈な場面です。
この虚実混乱が、上海の虚実混乱イメージを隠喩する。本作が「スパイ映画」であることがこの虚実混乱を倍加します。役者は舞台で虚を演じますが、スパイは現実で虚を演じます。主人公ユー・ジンは舞台女優でもスパイでもあります。彼女の元恋人で『上海』を演出するタン・ナーの「上海に来たのは女優としてか? スパイとしてか? 」という台詞が象徴的です。
面白いのは、蘭心劇場の芝居に関わる人々が旧知の仲なのに、今は誰がどちら側のスパイか判らないこと。登場人物らにも観客にも次第に、ユー・ジンがフランス側、その元夫が中共側、ユー・ジンの付き人を志願するバイ・ユンシャンが重慶政府(国民党)側、プロデューサーのモー・ジンインは南京政府(日本)側だと判るけど、互いに実在が不確定なまま揺れるのです。
虚実が揺れる上海租界は、母方親族を通じて僕が伝え聞いた上海そのもの。そこを舞台に虚実が揺れる登場人物たちの交流模様が描く本作は、史実に即して歴史的に稀有な当時の上海の虚実混融を再現しつつ、そんな歴史的な虚実混融を人々がどう生きたかという疑問に真正面から答えます。僕にとって本作は虚構では済まない。こうした理解に誤解はありませんか?
ロウ・イエ:宮台さんのこの映画の見方に同意します。というのもですね、ユー・ジンはフランス人の義父・ヒューバートに「これは私が演じる最後の役目よ」と言います。それは彼女が「スパイ」としてなのか、それとも「俳優」としてなのか、そこでもう見分けがつかなくなっているということです。ユー・ジンの恋人であり演出家のタン・ナーも言います。「僕は駒に過ぎないのか」と。ヒューバートもまた「使者は紙面を知らず」という伝聞を打ちます。みんなそういうことと関連があると思います。
宮台:その虚実混融を、暗部の潰れたモノクローム画面と、揺れ続ける手持ちカメラが、効果的に体験させます。登場人物たちは絶えず不完全情報下で足掻きますが、観客も同じく不完全情報下で目を凝らす。登場人物たちにとっても観客にとっても、頼れるのは客観ではなく主観の情動です。情動の流れを、劇中で流れるジャズが劇伴として機能して印象付けます。
スパイの恋
宮台:次に「スパイの恋」。多くのスパイ映画がスパイの恋を描きます。最近ではブラッド・ピット主演『マリアンヌ』。スパイの密命は敵国の共同体に潜ること。潜って敵国の人に恋したふりをする内に虚実の境が崩れる。最後は密命を放棄して恋を貫徹せんとする。恋の貫徹は死を意味する。でもその死は挫折ではなく輝かしい貫徹だ……定番のストーリーです。
本作はイレギュラー。演出家タン・ナーが女優ユー・ジンに恋しつつ、疑い続けるからです。かつて恋人だと思ったのも勘違いで、スパイ活動の一環では? 上海に来たのもスパイとしての任務貫徹が目的なのでは? この未規定性がカセクシス(溜め)になって、最後の最後にカタルシス(浄化)が訪れます。この溜めと浄化を、タン・ナーと同じく観客も共有するのです。
「スパイ」と「恋」は対照的。おのおの取替可能性replaceabilityと取替不能性irreplaceabilityを隠喩します。スパイは取替可能な部品。死んだら別のスパイが送り込まれる。恋は違います。恋の相手は取替不能。だからスパイが恋を演じる時、本来は取替可能な相手を、取替不能と見做すが如く演じます。さてユー・ジンにとってタン・ナーは、取替可能か、取替不能か。
タン・ナーはかつてユー・ジンとは恋仲だったと信じようとする。だから再会して程なくキスをします。でも彼は疑念を抱き続ける。恋人に再会すべく女優として来たのか。密命を帯びたスパイとして来たのか。実際、元夫暗殺の謀略に加担した。だが蘭心劇場の大混乱後、全てが終ったら港湾のカフェで待つとの伝言。来る筈もないと思いつつ彼は待って待って待つ。
果たしてユー・ジンは密命を裏切り、日本人将校など並み居る敵を打ち倒し、満身創痍でカフェを訪れます。タン・ナーは彼女の本気の恋を知り、それが彼女の恋の貫徹となる。恋の貫徹と同時に彼女は死にます。長いカセクシス(溜め)の後、タン・ナーも観客も、カタルシス(浄化)を得ます。その意味で間違いなくバッドエンドではなくハッピーエンドです。
途中に出てくるニーチェの言葉も伏線回収されます。曰く、愛は過剰な贈与。見返りを求める交換ではない。元々は彼が神について言いたかったこと。信仰は過剰な贈与。見返りを求める交換ではない。愛は本物だったと伝えるためにだけタン・ナーの元に命を賭して赴いたユー・ジンの振る舞いが過剰な贈与。僕らに欠けている過剰な贈与を指摘されたと感じます。
ロウ・イエ:宮台さんのおっしゃるとおりです。愛というのはユー・ジンにとっては自分のためのものであり、タン・ナーとはそれは関係のないもので。スパイという身分の特殊性というのは、他人に与えられた任務を完結しなければいけないということ。常に他人のために任務を遂行して、自分を持たないんですよね。この映画の中で、ユー・ジンはずっと他人の道具であり、駒なんです。この映画の一番特別なところは、彼女が道具として任務を果たした後にあるのかもしれません。彼女が反抗するのは、任務を果たしたあとだということに皆さんお気づきになるかと思います。実は彼女の道具としての身分への反抗であって、愛のためだけではないのです。ユー・ジンは全編を通して、長い間道具として生きている。でも、最後に彼女が蘭心劇場に戻ってきたところが、自分で運命を決めた瞬間なわけです。それまで、舞台の外ではパスカルから指示を受け、舞台の上では演出家から指示を受けてきた。つまり彼女は、舞台の上でも外でも、道具としての役割を果たしてきた。最後の反抗は、パスカルからの指示への反抗でもあり、演出家への反抗でもある。彼女は離れないし、演出家の指示通りに芝居をしません。
宮台:相手を取替可能な道具として扱わず、過剰な贈与の相手として見做した時にだけ、自分も取替可能な道具であるのをやめられます。僕らは今、恋愛においてすら相手を取替可能な道具と見做す作法にはまり、それで自らを取替可能な道具に貶めています。ユー・ジンの髪型や佇まいが『攻殻機動隊』の草薙素子に似るので(笑)、日本人に突きつけられた匕首だとも感じました。

























