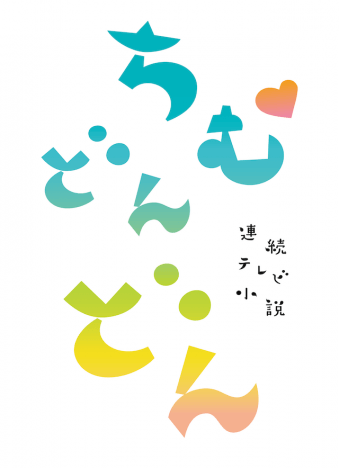『ちむどんどん』心がワクワクする物語の始まり ジョン・カビラの語りが温かい

雄大な自然に囲まれた沖縄本島北部のやんばる地域。そこで生まれ育った4兄妹の50年にわたる歩みを描く、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』がスタートした。亜熱帯の豊かな森と碧い海が織りなす絶景に佇む少女こそ、この物語のヒロイン・比嘉暢子(黒島結菜)だ。
彼女がシークワーサーの木に手を伸ばした瞬間、舞台は1964年へ。まだアメリカの統治下だったその場所で、小学5年生の暢子(稲垣来泉)は木になる果実に手が届かず悪戦苦闘していた。そんな暢子に父・賢三(大森南朋)は「まくとぅそーけー、なんくるないさー」と声をかける。真のこと、正しいことをしていれば、なるようになる。つまり、「人事を尽くして天命を待つ」と似た意味を持つ言葉だ。

「うちは世界中の美味しいもの、全部食べたい!」
沖縄が本土復帰を果たした1972年5月15日、父に語った夢への一歩を踏み出すことになる暢子。第1週はそんな彼女の後の人生を支える、家族と一緒に美味しいものを食べた子どもの頃の思い出が描かれていく。
穏やかで優しい父と、お人よしで明るい母・優子(仲間由紀恵)。2人のもとで比嘉家の元気な兄妹たちの個性は育まれた。長男の賢秀(浅川大治)はやんちゃで自由奔放な性格だが、動物が大好きで豚のアベベとアババを一生懸命世話している。
一方、長女の良子(土屋希乃)はしっかり者でみんなの頼れる存在。優しい“ニーニー”と“ネーネー”、そして病気がちで大人しい性格の末娘・歌子(布施愛織)の間に挟まれた次女の暢子は、美味しいものに目がない呑気な女の子に育った。

けっして裕福な家庭ではないが、食べ物を分け合い、足りないところを補い合って生きている。彼らが持つ助け合いの精神は村全体に根付いており、特に印象的なのは、“共同売店”の存在。明治の終わり頃に沖縄で生まれた相互扶助の仕組みで、住民自ら出資・運営を行い、みんなで地域の暮らしを維持してきた。
そんな沖縄独自の文化や風習に興味を抱き、本土からやってきたのが、民俗学者の青柳史彦(戸次重幸)とその息子・和彦(田中奏生)だ。生まれて初めて東京の人を見る暢子も興味津々。海で採れた新鮮な食材を「食べたら美味しくて、ちむどんどんするよ」と臆することなく和彦に差し出す。