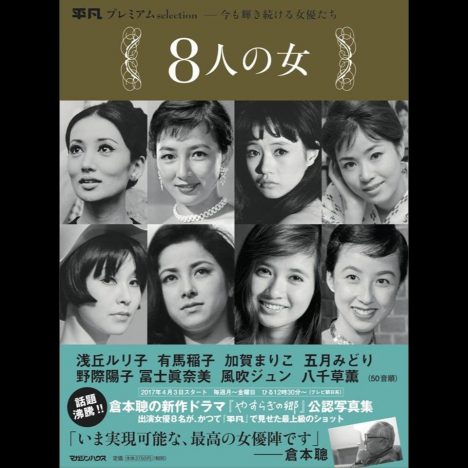俳優ビートたけしが見せた“父性” 『ゴースト・イン・ザ・シェル』の演技を読む

こんなに優しい表情の俳優ビートたけしを見るのは何年ぶりだろう。ひょっとしたら、『戦場のメリークリスマス』のラストシーン以来かもしれない。
ビートたけしは、(自分ではない)他の監督の映画に出るときは監督に言われた通りにする、と明言している(というのはつまり、北野武監督作品に出演しているときのビートたけしは、監督の指示に従わないこともある、ということなのかもしれない。実際、そのような北野作品が何本かある)。だから、これは、『スノーホワイト』で知られるルパート・サンダース監督からの要請なのだろう。
とはいえ、ビートたけしは必ずしも従順なだけの俳優ではないことを、「英語は嫌だと言ったら日本語で良いとなった」というエピソードで自ら明かしている。しかも、「セリフ覚えが悪いとか字が読めないとかいろいろ難癖をつけていて、しまいにはスカーレット・ヨハンソンが俺のカンペを持っていた(笑)。あれを写真に撮りたかった!」とオチまでつけて。
彼がハリウッド映画に出演するのはこれが初めてのことではない。もう20年以上前にロバート・ロンゴ監督の『JM』でキアヌ・リーブスと共演している。あのとき英語を話していたかどうか記憶にないが、タイトル通り東京が舞台で東京で撮影されたジャン=ピエール・リモザン監督の『TOKYO EYES』では日本語しか話していなかった。つまり、海外の監督の映画に出演しても、ビートたけしのフォームが明確に変わるわけではない。そもそもこの俳優にとって言語はさほど大きな意味を持たない。彼はどんな作品でも、セリフ回しをほとんど変化させないからだ。

これは北野武監督作品でも顕著なことだが、俳優ビートたけし最大の特徴は動き=アクションだ。彼は最短距離で、物事を「終わらせる」ことを、その動きの大命題にしているかのように映る。そして、表情は、悠々としていながら的確なそのアクションにただ「付随」しているだけで、セリフもまた、この動きに「同行」している。その素っ気なさこそが、この俳優のもっとも明瞭な持ち味である。言ってみればビートたけしは、こうした存在感のみで映画の中に鎮座しているし、そのことにこそ価値がある。
『ゴースト・イン・ザ・シェル』は、士郎正宗の漫画、というよりも、押井守監督のアニメーションとして著名な『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』の実写化だ。ビートたけしは、脳以外は全身「義体」のヒロイン(スカーレット・ヨハンソン)が所属する捜査組織、公安9課のボスを演じている。己のアイデンティティに揺れ動く主人公を支えるこの役どころは言ってみれば「父親」のようなものだ(ヒロインの「メンテナンス」を行う「母親」役はジュリエット・ビノシュである)。
ルパート・サンダースはビートたけしに、作品を司る「父性」を託したのだろう。そして、このオファーに、この俳優は意外なかたちで応えている。
おそらく、もともと英語で想定されていたセリフを日本語に変換したことが影響している。近未来の設定であり、公安9課のメンバーたちは電脳を通じて、離れていても会話ができることになっている。そのような状況下では、英語を話す者と日本語を話す者とが通訳を介さず、タイムラグなしのコミュニケーションを可能にする映像=演技にも説得力が生まれる。
スカーレット・ヨハンソンはフライヤーで次のように語っている。「たけしさんは映画の中では日本語を喋っていて、オフカメラでもあまり英語を喋らない。じゃあ、コミュニケーションが取れなかったというと、そんなことはまったくなく、同じ言語で話している感じがしていたの。私はそれが人間の言語だと考えた。純粋な人間同士のつながりのような感覚をおぼえたのよ。これは素敵な体験だったわ」
ヨハンソンはオフの話をしているわけだが、「同じ言語を話している」感覚は、劇中の演技からも汲み取れる。そして、この感覚は、全員が英語を話すのではなく、ビートたけしだけが日本語を話していることからもたらされている。この通訳なしの「共有」こそが、この映画で最も美しい瞬間であり、そこでは、彼が話す日本語も、心なしか、いつもより、ゆったりめである。