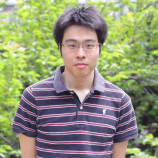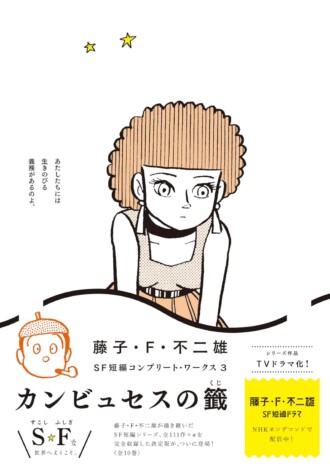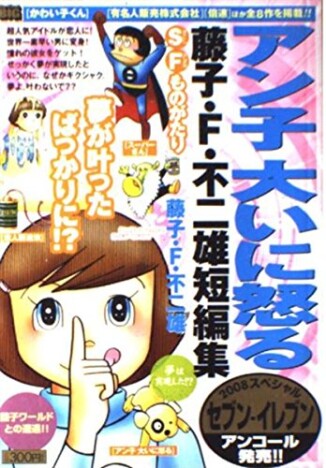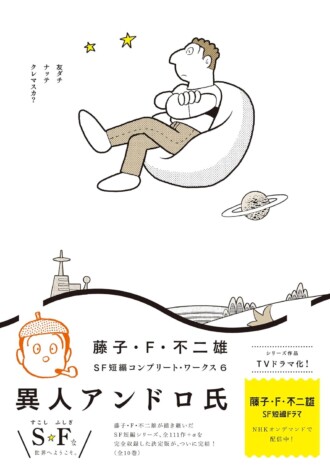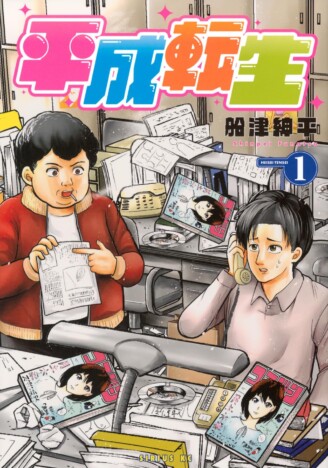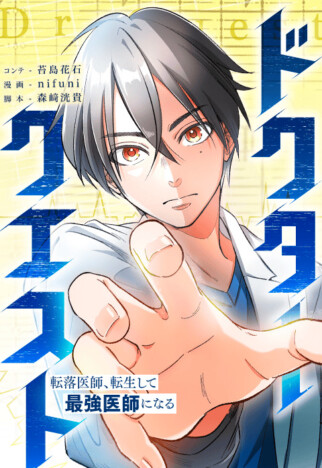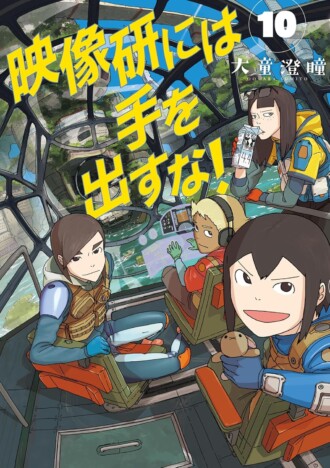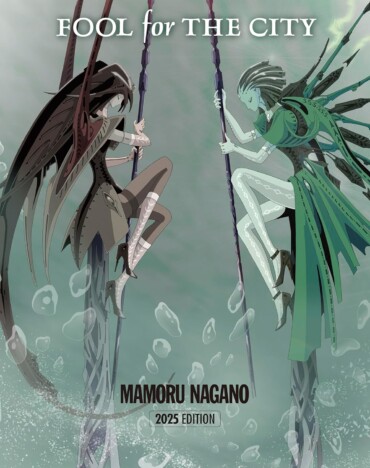藤子・F・不二雄にとってのタイムマシンとは? 人間の矮小な欲望を描き出す『あいつのタイムマシン』
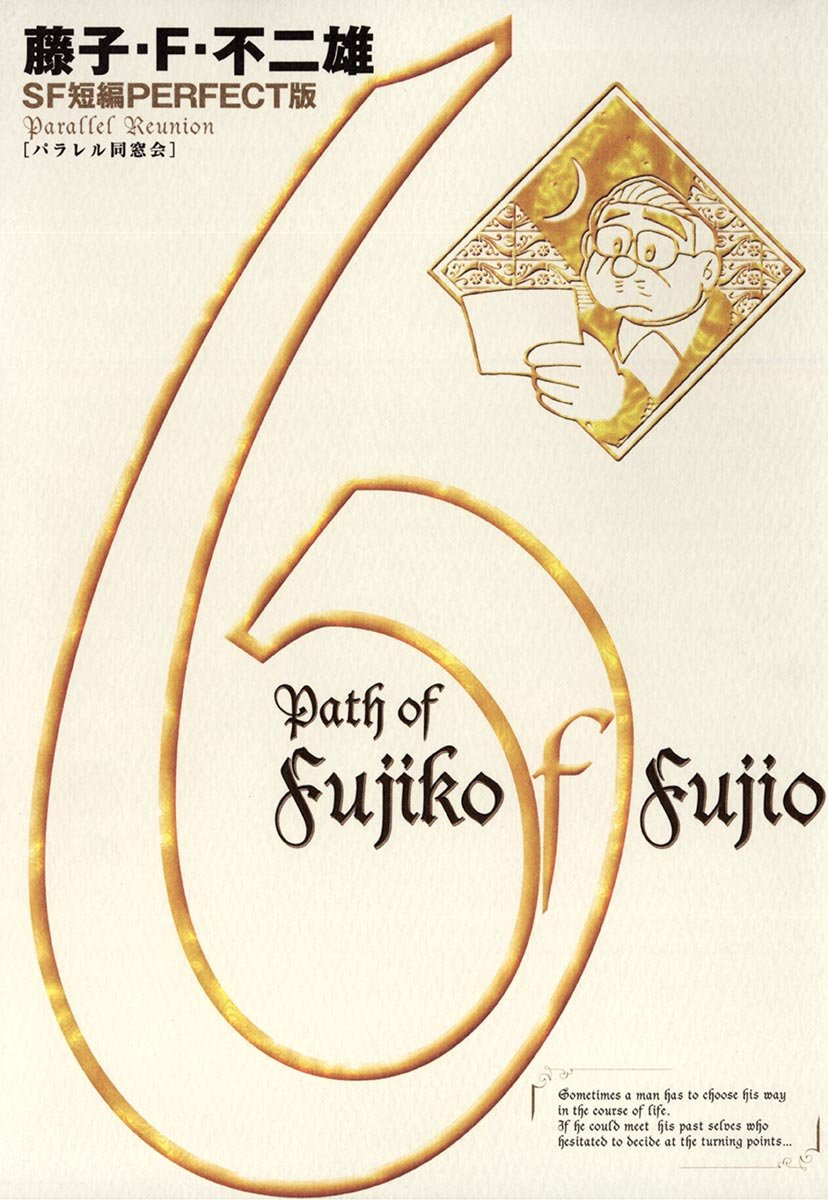
タイムマシンのマニュアルがあるか/ないかという点ではこの2作は対照的だが、『タイムマシンを作ろう』でもまた、タイムマシンが次第に完成へと近づく過程と、未来の松井が突然現れた理由が読者にわかるまでの過程は同期する。終盤で判明するその理由もまた、あまりにも平凡な、人間的な欲望に立脚している、そう言わざるを得ないものだ。
この2作に限らず、時間を飛び越えるという力を得たSF短編の登場人物は、しばしばその深淵さとは対照的な、矮小な自分たちの欲望をあらわにする。少年から老年までの「自分」が集まり、各々が「今の自分」の得になるような富の分配を主張する『自分会議』、過去を映像としてうつし出すことに成功した科学者が、自分がいないときの妻の動向を見ようとする『T・Mは絶対に』といった作品はその好例となるだろう。
「のび太の未来を変える」ことを作品の出発点とした『ドラえもん』や、歴史の隅で不幸な死を余儀なくされた人々を救出する、タイム・パトロール隊員の活躍を描いた『T・Pぼん』といった連載作品では、藤子・F・不二雄はおおむねタイム・トラベルについて肯定的な描写をしている(もちろん、タイム・トラベルを私利私欲のために使おうとして、しっぺ返しを食らうような描写もありはするが)。
しかし、大人向けのSF短編では対照的に、タイム・トラベルのような壮大な技術と対比した人間の矮小さを浮き彫りにすることで、人間へのシニカルな視点を提示し、それが痛快な魅力となる。『あいつのタイムマシン』もまた、そのような系譜に位置付けられる作品であり、『ドラえもん』におけるタイム・トラベルを「陽」とするならば、対照的なタイム・トラベルの「陰」の魅力を実感できる作品のひとつであると言えよう。
※なお、『あいつのタイムマシン』と『タイムマシンを作ろう』のもう一つの共通点としては、作中に『ドラえもん』が登場する点である。前者においては、正男がタイムマシンを題材とした漫画を編集者に見せた際、「ドラえもんならこれでもいいんだけど、うちの読者は大人だからもう少しリアリティが欲しい」と言われ、リライトを勧められる。後者においては、松井がぼろぼろの『ドラえもん』第1巻を持ち、これを読んでタイムマシン作りを夢見たあの頃は幼かった、などと友人・杉本と振り返る。つまり、両作での『ドラえもん』は「子ども」の象徴のような形で示され、両作の主人公たちとはすでに距離を置いたもののように扱われる。これは両作における「大人のタイム・トラベルを描くのだ」という、藤子・F・不二雄のスタンスの表明のようにも思えて興味深い。