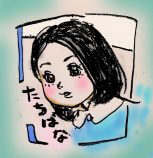松村北斗×上白石萌音のW主演で話題『夜明けのすべて』 原作小説で描かれた尊い関係性

原作で描かれる、恋でも友情でもない二人の関係性は、とてもコミカルに尊いものとして描かれていたが、映画では二人をとりまく人たちもみな、二人を見守り支えているのだということに気づかされる。たとえば、光石研演じる栗田科学の社長が、藤沢さんと山添くんが話しているのをさりげなく聞いているシーンがとてもよかった。おや、という表情で顔をあげて、少し聞いたらまた目を伏せて、自分の仕事に戻る。でもきっと、意識はほんの少し、二人に傾けたまま。たぶんほかの社員に対しても同じように心配りをしているのだろう。社長以外の人たちもみんな、さりげなく、言葉にはしないで、そっと互いを見守りあっている。なんて理想的な職場だろう、と羨ましくなるけれど、きっと気づいていないだけで、現実でも多くの人がそんなふうに他者を思いやっているんだろうと思う。
二人以外にも、原作ではさまざまな人たちが見えない痛みを抱えている姿が描かれる。弟を亡くした社長。姉を亡くした山添くんの元上司・辻本さん。足を悪くして施設に通う藤沢さんのお母さん。それぞれ理由は、大きくは語られない。それは、その人がつらくてしんどいことに、理由なんていらないからなんじゃないかと思う。痛みは、誰かと比較するようなものじゃない。自分にとって大したことがないように思えても、その人が抜け出せない暗闇にとらわれているなら、理由なんてどうでもいいのだから。
小説は、言葉を尽くすことでしか生み出せない。けれど言葉を尽くすことがすべてではないのだと、映画を観て痛感した。監督の三宅唱は、言葉ではなく映像と光の色で描写する。セリフや音は少なく、わかりやすい説明などほとんどないけれど、その描写から確かに伝わってくるものがあって、胸が詰まってしまうのだ。瀬尾まいこの小説ではいつも、人に対する信頼を感じるけれど、三宅監督の映画からも、受け手への信頼を感じる。よけいなことを言わなくても、ちゃんと、伝わる。私たちは「感じる」ことができる。想像して、他者を思いやることができるのだと。
言葉でしか伝えられないもの。映像だからこそ伝わるもの。小説と映画、それぞれの表現で描かれる『夜明けのすべて』を、一人でも多くの人に味わってほしいと思う。