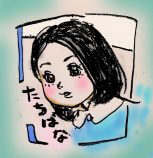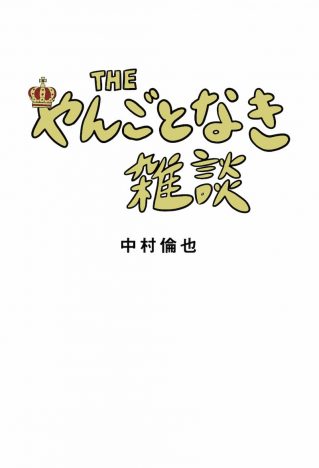「中村倫也」卓越した表現を生み出す方法「いろんな感覚を言語化しようとする意識は常にもっている」
「撮影されているときは、たいてい何も考えていない(笑)」
――『蓑唄』で、ドラマ『石子と羽男』についてお話ししているインタビューで、それに通じることをおっしゃっていました。〈もちろん脚本の面白さも重要だけど、現場で伸ばせることもあるし、軌道修正も出来る。だから、脚本が絶対だとは思っていない。〝人〟の掛け算と、個人がどこまでやれるかだと思う〉と。
W杯見てもそうじゃないですか。個の力がどんなに突出していても、それだけでは勝てないということを肌身で知っているんですよ。逆に、組織力だけが強くても、それだけでは勝ち上がれない。どちらも兼ね備えたチームだけが残る。仕事も、それと似たところがありますね。
――『蓑唄』のインタビューを読んでいると、『童詩』から十年、ずっとチームでお仕事されてきたプラスアクトの取材班に対する信頼感が伝わってきます。彼らだからこそ引き出せてもらえたものを、本作で感じることはありますか?
ほとんどが引き出してもらえたものだと思いますよ。僕、撮影されているとき、たいてい何も考えていないので(笑)。カメラすら、意識していないことが多い。それがこうして、一冊の本にまとまったのを改めて見返すと、いろんな角度から僕を切り取って、飽きさせないつくりにしてくれているのだから、ありがたいですね。
――中村さんの大切にしている「視点を一つにしない」ということが、ちゃんと共有されている証ですね。とくにお気に入りの一枚は、ありますか?
2019年に、額縁を使って撮影したやつですね。劇場には、プロセニアム・アーチという構造物があるんですけど、おもしろいもので、人 はみな、舞台上で起きることはすべて芝居だとわかっているのに、そのプロセニアム・アーチという額縁があるだけで、幕開きの照明や音の変化だけで、芝居という嘘を本気で信じようとしてくれる。それは想像力という、人間だけがもつ楽しみの一つなんじゃないかなと、前々から考えていたことが撮影に繋がりました。「額縁を使ってなんか遊んでみようぜ」くらいの気軽な気持ちで始めたことが、結果的にこの一冊にとって、けっこう大きなモチーフになったという意味でも、思い入れのある作品ですね。あともう一つ、気に入っているのが、真っ白な背景と服で撮影したやつなんですけど。
――2021年の作品ですね。それこそ、境界線が溶けているような、ちょっと幻想的な雰囲気の。
黒の額縁との対比を意識して撮影されたらしいです。そのときのインタビューでも言いましたけど、用意された空間と小物を見たとき、〝記憶の管理人〟という言葉がパッと浮かんだんです。小物一つ一つにまつわるストーリーみたいなのを想像しながら遊んでいるところを、自然と撮られていた感じ。現場で与えられたものと、自分のなかに生まれたもの、それによって起きたスタッフ含めての化学反応が、うまく嚙み合って遊べた作品なので、これも気に入っていますね。
「常に言葉や概念を頭のなかでこねくりまわしている」
――〝記憶の管理人〟というワードもそうですが、『蓑唄』を読んでいると、表情やたたずまいだけでなく、言葉の表現力も卓越しているのが伝わってきます。
単に、めんどくさいやつだからじゃないですか(笑)。常日頃から、言葉や概念を頭のなかでこねくりまわしているから。ただ、仕事に関すること以外で、本はまったく読まないんですよ。若いころは、手当たり次第に読んでいたんだけど。小説だけでなく、ビジネス書や自己啓発本、歴史、哲学に宗教、あとはサッカーの本も、それはもうジャンルレスに手を出していました。でも今は、年がら年中、セリフを覚えるために台本を読んでいるので、それ以外で活字を見るのがいやになっちゃった。
――そのかわり、自分の内側に蓄積した言葉で遊んでいる?
いろんな感覚を言語化しようとつとめる意識は、職業柄、常にもっているとは思います。たとえば現場で監督や共演者と話すとき、うまくかたちにならないからといって、自分が感じていることを伝えるのをやめてしまったら、仕事にならないじゃないですか。簡単には言葉にできないものをどうにかして表現していくのが、役者として必要だと思っているので、自然とそうなったという感じですね。あとはまあ……才能としか。

――今日イチの決め顔が出ました(笑)。
ま、そういう感じです(笑)。
――『蓑唄』の2019年インタビューで、他人からの誉め言葉も貶し言葉も重宝あっていいけど、気にし過ぎる必要はない、嬉しくてありがたい言葉でも、一つひとつを自分の中にとどめておくことはしない、とおっしゃっていました。こうして、しっかりとインタビューが残されることによって、ご自身の言葉に縛られる、ということはないんでしょうか。
背負わなきゃいけないくらい大仰なことは言いませんからね。身の丈にあわない言葉を発すれば、あとから自分を苦しめるだけだというのは、わかっていますから。だから人から「あのときこういうことを言っていましたよね」と言われても「ああ、まあ、言ってたんだろうね」と思うくらい。基本的に自分の言ったことは忘れちゃうので。
――忘れちゃうんですか。
セリフを自分のために使わない、という考え方が役者の世界にはあって。セリフを自分の役を表現するために使っているうちはまだまだ。セリフは、他の役を動かすために使うんだという意味で、経験とともに実感していくことなんですけど、インタビューのときも、自分を鼓舞したりよく見せたりするために言葉を使わないようにしているんですよね。読んでくれる人にどう結びついていくのか、考えながら話しているところがある。となると、自分自身に強固に結びついているわけじゃないから、忘れていく(笑)。
あとはまあ、言葉を発する時点で、自分の頭のなかにあるチェック機構を通過していますから。今は、十年以上も前の発言を引き合いに出されて、あれこれ言われてしまうこともある時代だけど、言葉を発するその瞬間に、ちゃんと誠意をもつことしかできないんだよな、と思っているので、過去の自分の言葉に触れても「僕の言いそうなことだな」「今もあんまり変わっていないな」というくらいで、気負ったり縛りつけられたりすることもないです。
――『蓑唄』はこんなにぶあついのに、たたずまいが風のように軽やかなのが、中村さんの不思議な魅力ですよね……。
『童詩』よりも100ページ以上増えちゃいましたからね(笑)。
「カラフルにいろんな色を繋ぎ合わせた一冊になった」
――タイトルは、中村さんの造語なんですよね。「蓑」はミノムシからとったと、由来についても本作のなかで語られていますが、どこからミノムシの発想が浮かんだんですか?
実は、『童詩』の刊行直後には、すでに浮かんでいたんですよ。つぎはぎされた着物を羽織った写真を見たときに、なんとなく「ミノムシみたいだな」と思っていたんです。だけど、まだ一冊目を刊行したばかりだし、二冊目を出すことになったらまた別のタイトルが浮かんでいるかもしれないし、と、いったん忘れることにした。で、今回改めてタイトルを考えることになって、やっぱりハマるなと思ったんです。そこから詳しく調べてみたら、松尾芭蕉が「みの虫の音を聞きにこよ草の庵」と句を詠んだように、昔は鳴くと思われていた。だったら「唄」とも合うじゃん、としっくりきたというわけです。
――じゃあ、もしかしてすでに三冊目のタイトルも……?
いやいや、もう十分でしょう(笑)。三冊目……があるかどうかはわかりませんが、まずは『蓑唄』、手にとっていただければ嬉しいです。ミノムシのパッチワークみたいに、カラフルにいろんな色をつなぎあわせた一冊になっていますので。
■書誌情報
中村倫也 続きの本『 蓑唄 』
撮影:sai、宮脇 進
ワニブックス刊
スタイリスト:戸倉祥仁(holy.)
ヘアメイク:ヘアメイク=松田 陵(Y's C)
中村倫也 衣装クレジット(税込み)
カーディガン ¥38,500 シャツ¥60,500
共にmeagratia
パンツ ¥36,300 RYU
全てTEENY RANCH
その他スタイリスト私物