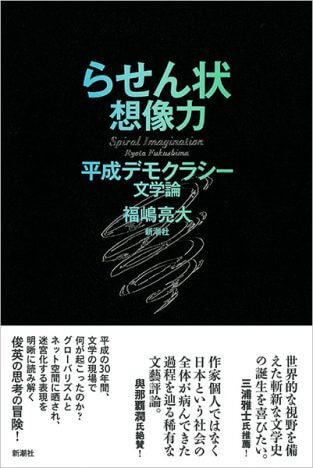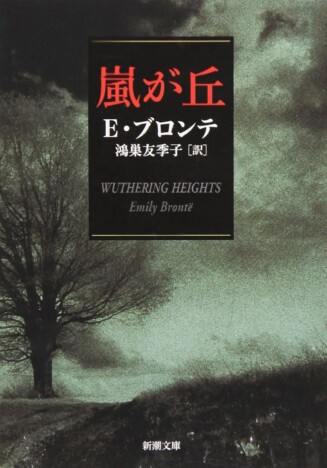もし村上春樹(偽)が村上春樹ライブラリーを訪れたら? 新たな文化拠点・早大国際文学館レポート

早稲田大学国際文学館、通称・村上春樹ライブラリーが昨秋に同大敷地内にオープンした。国内外で刊行されたすべての村上春樹作品をはじめ、村上氏から寄託・寄贈された執筆関係資料、書簡、インタビュー記事や書評、レコード・CDなどを所蔵している。そんな新たな文化の発信地に、村上氏の文体模写で知られるライター・神田桂一氏が登場。館内をめぐった様子を(一部フィクションを含む)レポート記事でお届けする。(編集部)
ハルキワールドを目指して
「次の駅は高田馬場、高田馬場駅だ。西武新宿線と地下鉄東西線に接続している。石神井公園や中野に行きたい人はここで乗り換えたらいい。だけど、そうじゃない人は──これは僕の個人的な見解に過ぎないんだけど──そのまま乗っていればいいんじゃないだろうか。
あるいは飯田橋方面に向かう人が、気分転換に地下鉄に乗り換えてもいい。もう外の景色を見るのがうんざりだ、なんて人もいるだろう。僕は窓から見える風景を眺めるのが好きだが、そうじゃない人もいることはわかっている。
繰り返しになるが、次に着くのは高田馬場駅だ。今は時速80キロほどで走っていて、池袋・上野方面に向かっている。この電車にずっと乗っていたら──それはとても奇妙に聞こえるかもしれないけれど──いずれこの場所に戻ってくる」
いささか難解な電車アナウンスが流れていた。
「わからないな」
僕はつり革を持ったまま、はっきりとそう口に出して言ってみた。乗客の何人かが、怪訝そうにこちらを見た。でも、今の僕にとってそれは、取るに足らないものだった。
高田馬場駅に着くと、僕は電車を降りた。向かう先は、早稲田大学にある村上春樹ライブラリーだった。僕はそこで、ライブラリーの事務長と会う予定になっていた。
それは2022年のことで、北京で冬季オリンピックが行われた年でもあった。中国では、習近平が台湾に睨みをきかせ、ロシアではプーチンがウクライナに戦争を仕掛けようとしていた。
村上春樹ライブラリーは、白に流線形のオブジェが印象的な建物だった。それはまるで、南極の天体観測所を想起させた。設計は建築家の隈研吾。世の中の建築家には、隈研吾とそれ以外という分類が―好むと好まざるとにかかわらず―存在している。
さっそく中に入って、事務長と挨拶をした。西尾さんといった。西尾さんは、事務長というより、どちらかと言えば、水族館のラッコの飼育係に見えた。
「これからどうされますか?」
西尾さんが単刀直入に聞いてきた。
「これは一つの参考意見として聞いてほしいんですが――館内を案内してほしいんです」
僕が、緊張しているのか、ふてくされているのか、どちらともいえない表情でつぶやくと
「あなたは不思議な人ですなあ。でもそういうところ、気に入りました。案内しましょう」
西尾さんは、まるで鎌倉の大仏が微笑んだときのような表情を見せた。
「いえ、僕は平凡が服を着て歩いているような男です。靴底だって擦れているし、シャツだってシワだらけでアイロンもかけてない(本当はアイロン掛けには全部で10の工程がある)。気の利いたことひとつも言えないし、今日のお昼は松屋のカレーです」
「行きましょう」
西尾さんは僕を館内に促した。
まずはハルキワールドへの入口と呼ばれるのれんをくぐった。すると、デビューの1979年から現在までのすべての村上春樹作品が壁一面に並べられていた。すべて初版あるいは初期の装丁のものだという。わりに長時間眺めていても飽きることがなかった。

その他、52カ国もの国で翻訳されている各国の翻訳本が並べられていた。ある国では表紙が違い、ある国ではタイトルが違った。それはとても空虚な音色で僕に響いた。でも、結局のところ、僕にはどうしようもないことなのだろう。
部屋の奥にいくと、村上春樹がかつて、千駄ヶ谷で経営していたジャズ喫茶「ピーターキャット」の椅子が飾られていた。僕は椅子に座ると、カバンからトーマス・マンの『魔の山』を取り出し、パラパラと読んでみたが、まったく頭に入らなかった。読書というものは、しかるべき場所で、しかるべき時間に、しかるべき態度でするものなのだ。